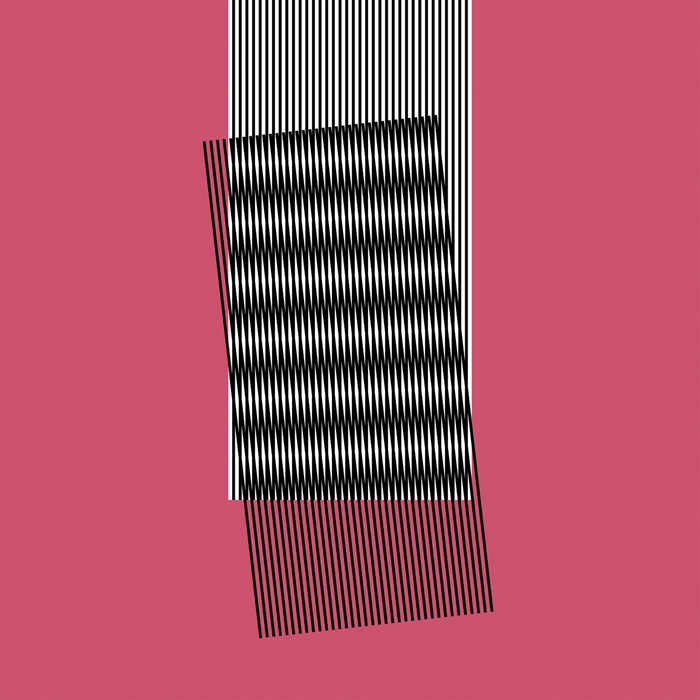
2015年は、ホット・チップにとって結成15周年にあたる年なのだそうだ。多くの人にとって、ホット・チップの存在を発見したのはイギリスでニュー・レイヴの嵐が吹き荒れていた2006~07年頃、2ndアルバム『ザ・ウォーニング』収録の“オーヴァー・アンド・オーヴァー”や“ボーイ・フロム・スクール”といったクロスオーヴァー・アンセムを通じてだろう。その頃から数えても約10年、彼らは一貫して時流のトレンドとは付かず離れずの距離を保ちつつ、エクレクティックで温かみのあるダンス・ポップをクリエイトし続けてきた。中心的存在の一人であるジョー・ゴッダードが「短距離走じゃなく、マラソンのようなものだ」と語っているように、彼らのキャリアは目を見張るようなピーク・ポイントこそないものの、代わりのいないユニークな存在としてシーンに確固たるポジションを築き今に至っている。
6作目となるこの『ホワイ・メイク・センス?』も、メンバーのソロやサイド・プロジェクト関連の動きを経た約3年振りの作品とは思えないくらいに気負いなく、他では得難いホット・チップの魅力が発揮された一枚である。メインストリームで猛威を振るうEDMから、ディスクロージャーを旗頭としてハウス/ガラージとR&Bの折衷的展開が進むUKシーンまで、ポップ・ミュージックのエレクトロニック化が世界的に著しく進行中なのはもはや周知の事実だが、本作で彼らはあくまで独立独歩の姿勢を貫き、結果として現代のエレクトロ・ポップに対する批評性を忍ばせることにも成功しているように思える。
一聴して耳を惹かれるのは、かつてないほどに削ぎ落とされた、シンプルだが躍動的なプロダクション。多層的な処理に数多くのフックが詰め込まれていた前作『イン・アワー・ヘッズ』とは対照的に、音数はぐっと絞り込まれ、生ドラムが刻むファンキーなハウス・ビートを基調としてゆったりと時間をかけながら高みへ導いていくような楽曲が並ぶ。ダフト・パンク『ランダム・アクセス・メモリーズ』以降の潮流とも共振する方向性だが、その中心にアレクシス・テイラーの所在なさげな歌声が据えられることで、エレクトロニクスの中に宿る人肌の温もりがより一層強調されている。
デ・ラ・ソウルのポスがゲスト参加した“ラヴ・イズ・ザ・フューチャー”や、粘っこいクラビネットの旋律がスティーヴィ・ワンダーを髣髴させる“スターティッド・ライト”を筆頭に、ダンス・ビート一辺倒ではなくヒップホップやソウルまでを横断する折衷性も健在。また、エレクトロニック・プロダクションを背にしたエルトン・ジョンといった趣もある“ホワイト・ワイン・アンド・フライド・チキン”や“ソー・マッチ・ファーザー・トゥ・ゴー”のようなバラードも、アルバムにクラシカルでありながら未来的な味わいを加えており、ホット・チップならではの個性を際立たせている。
オープニングを飾る“ハラチ・ライト”でアレクシスは歌う。「機械は素晴らしいけれど、最高なのはそれに命が宿るとき」――この言葉が、彼らの追求するエレクトロ・ポップの精神と信念を象徴しているかのようだ。僕らにとって大事なのはインスタントな快楽よりも、そこに注ぎ込まれた人間性の方なのだと。
DJコーツェ、ゴンザレス、アーランド・オイエ……彼らは、多くのリスナー、なかでもヴァイナル・ユーザーの間で、短くない期間、この人の名前あれば間違いないし、といった支持を受けている存在だ。いずれも記名性の高いサウンドを持ち味としつつ、オリジナル曲のみならずコラボレーションやリミックス・ワークなどでも、個性と同時代性とポップ・ソング・マナーの全てを落としこんだ、フック満載の良い仕事ぶりが光っている。彼らのサウンドには、つねに既存のサウンドからはみ出る多面性、特にポップ・ミュージックとクラブ・ミュージックの境界を撹乱する仕掛けがある。それがゆえに、10年以上に渡り、ジャンルを跨いで、聴き手を熱狂させ続けているのだろう。
ロンドン・ベースの5人組、ホット・チップもまた、上記のカリスマたちと並ぶ、ぶれることなく高水準のサウンドをキープしているアクトだ。流暢にメロディを操るアレクシス・テイラー、主宰レーベル〈グレコ・ローマン〉でも外さないジョー・ゴダード、そしてダンス・ミュージック・バンドとして地球一と言ってさしつかないライヴ・パフォーマンスに、その評価は揺るぎないものとなっている。
そして、最新アルバム『ホワイ・メイク・センス?』においても、やはり彼らは裏切ることがない。エレクトロニック・ダンス・ミュージックとしての側面は若干希薄で、いわゆるフロア・アンセムといった曲は、カリブー~フォー・テット・ラインのテクノ“ニード・ユー・ナウ”くらい。UKガラージ/R&Bからの反響もうかがえるステッピーな“ラヴ・イズ・ザ・フューチャー”、クラビネットがご機嫌なファンク“スターティッド・ライト”、艶やかなストリングスが配されたアーバン・ソウル“ダーク・ナイト”と、全体としては、ブラック・ミュージックへの傾倒が印象深い。生ドラムのまろやかなビートを基調に、緩急自在にグルーヴを操るライヴ・バンドとしての側面を打ち出した作品だ。
とすると、『ストップ・メイキング・センス』めいたアルバム・タイトルも含め、今作はホット・チップ版トーキング・ヘッズ・レコードと勘ぐってもしまうが、やはりどこを切り取っても彼ら印なのは、さすがの一言。ひ弱なくせにやたらセクシーな、アレクシスの歌声が乗ったら一目瞭然なのは言うまでもないが、サウンドにおいてもそのカラーは健在である。キレの鋭い音処理と、それにより作られた音の隙間ならではのバウンシーなリズム。ブヨブヨと動くシンセ・ベース。それらが耳に飛び込んでくれば最後、聴き手の感覚はもう彼らの思うままだ。
これまでの魅力を一切目減りさせることなく、最新作ならではのフレッシュ切り口もしかと貫いた今作は、もはや彼らにとっては横綱相撲のようだ。つまり、当たり前のようにホット・チップの傑作である。むしろ、この破錠のなさだけが唯一好き嫌いの別れるところかもしれない。しかし、10年間にわたり、我々のなかに築き上げられてきた、彼らへの絶対的信頼は、今回もまた、少しも揺るぐことがない。
