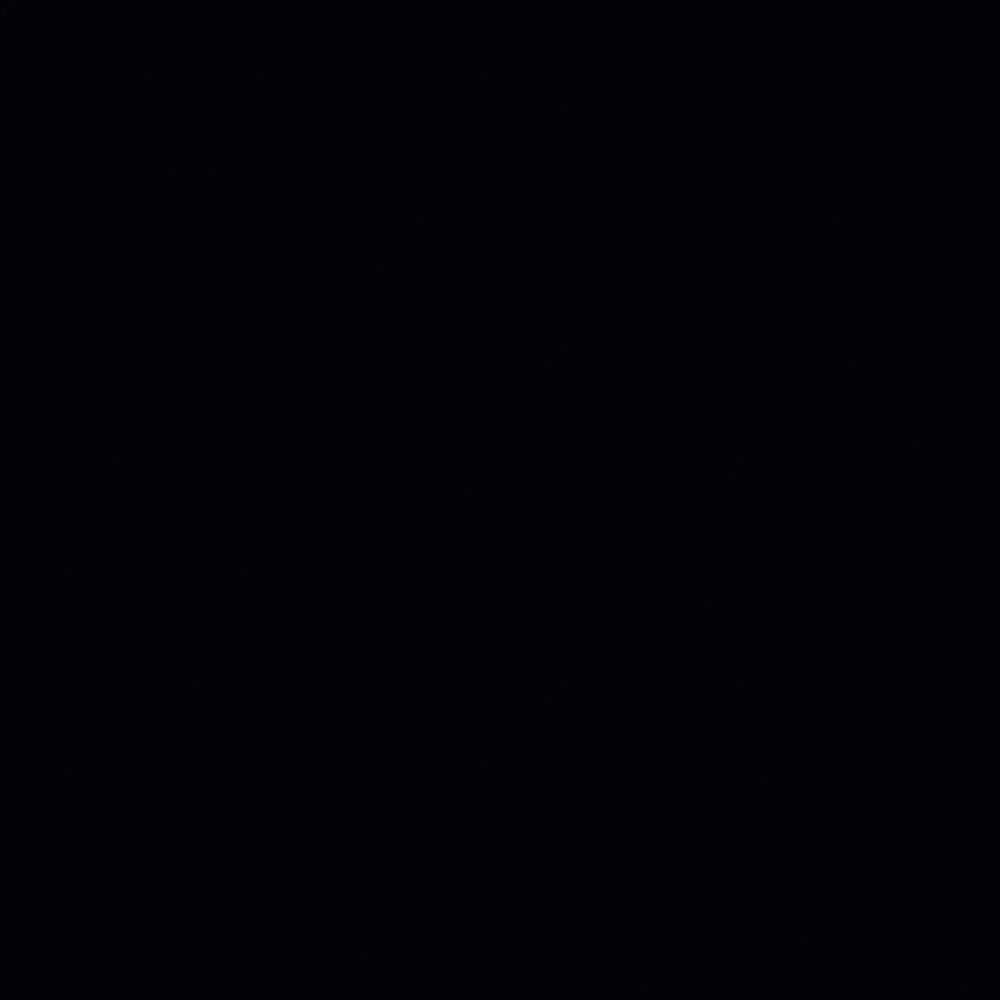
カニエ・ウェストにハマるのは「沼」より「渦」に巻き込まれる感覚だ。ズブズブと深みに嵌るのではなく、積極的に巻き込まれに行く感じ。渦中にいるあいだは周りの声は届かないし、どこにたどり着いてもと構わない、とまで思える。亡き母ドンダ・C・ウェストさんのファースト・ネームを冠した『ドンダ』をリリースするまでの数年間は、激しめの「ハリケーン・カニエ」とも呼べる騒ぎが続いていた。ヒールっぷりに惹かれたのか、ドナルド・トランプ元大統領へすり寄ったり、それに飽きたら大統領選に本気で出馬してみたり、公衆の面前でナーバス・ブレイクダウンを起こしたと思ったらキム・カーダシアン・ウェストと別居から離婚へ流れたり。「本日のカニエ」のニュースにお腹いっぱいになりながら、「私たち、新しいアルバムを聴きたいだけなんです!」との本音を周りに言いづらい期間を耐えたファンも多かったのでは(皆さま、お疲れさまでした、待った甲斐がありましたね)。
『ドンダ』は、クリスチャン色を強めてゴスペルの世界に寄ったものの、どっぷりヒップホップ、ファッション、投資など世俗のカルチャーに浸かっているため(というより、カニエ自身が世俗カルチャーそのものだ)、中間地点を模索した仕上がりになっている。音楽的には『ライフ・オブ・パブロ』以前も含めたカニエ・サウンドと、ここ5年の「神様、ありがとう!」サウンドの折衷型で手を打った作品とも言える。「前とは変わったんだ/新しい俺になったから/慣れてくれ(It ain’t how it used be /This the new me/ So get used to me)(“ピュア・ソウル”)と「新生カニエ」を宣言するのだが、ハレルヤ一辺倒だった前作『ジーザス・イズ・キング』よりも自分の言葉で語っている分、「変わってないじゃん」と思う箇所が多く、かつそれが(それで)いい。
なにしろ、パイプ・オルガンの音を響かせ、サンデー・サーヴィス・クワイヤーのコーラスを多用した荘厳ともいえるサウンドに、夫婦喧嘩の顛末をラップしているのだ。「神様はリモコンを持っている」(“リモート・コントロール”)など、その解釈は合っているのか、とキリスト教門外漢の私でも思ってしまうリリックもある。時折、出てくる「デビル」は聖書通りの悪魔ではなくて、誘惑に弱い自分を指しているように取れる。それでも、カニエは本気で祈っている。その祈りが強いので、『ドンダ』はカニエ・ウェスト流のゴスペル・ラップとして機能している。
30人以上の客演を招いてカニエが挑んでいる隠れテーマが、キャンセル・カルチャーへの逆襲である。リリックの内容は亡き母への追悼と、キムへのメッセージが多めではある。だが、最後のリスニング・イベントでホモフォビックな発言のせいで活動が滞っていたダベイビーと、性的虐待、および暴行というかなり重い疑惑を背負っているマリリン・マンソンを招き、“ジェイル・パート2”にまで参加させたのは、「人間を裁くのは神様であるべき」という信仰心と、だれにも自分を消させはしない、という強い決意の現れだろう。マンソンを呼んだのは明らかに悪手だが、そこは一旦おいてキャンセル・カルチャーとカニエについて少し考察したい。
「キャンセル」との予約を取り消すような軽い響きのせいで、日本での理解にズレがあるようだが、実態は「ボイコット」を促す動きだ。その人物の存在と作品全てを否定しよう、と主にネットで呼びかけるムーヴメントでヴァイラルになると恐ろしい効果を発揮する。だから、キャンセル・カルチャーのやり玉に上がった表現者は並々ならぬ恐怖心を抱く。ラップ・ゴッドことエミネムでさえ、しょっちゅう曲のテーマにしているほどに。カニエはキャンセルされつつ、その話題性をスニーカーやクロージング・ラインの富に換金できた(ように見える)珍しい人である。彼は米大統領選という世界秩序にかかわるイベントを撹乱させた大迷惑野郎ではあるが――本気にする人が少なかっただけに――それが罪かといえば違うだろう。『ドンダ』の制作期間、カニエはこのままキャンセルされ続けるのでは、という恐れがあったのではないか。とくに前半で聴ける怒りに満ちたラップは、家族とファン・ベースをいっぺんに失いそうな恐怖心の裏返しだと私は取った。実際、アメリカの媒体のレヴューはキャンセル・カルチャーを意識したような強い拒否感がにじむ文章が目立った。
美しい調べに満ちた『ドンダ』ではあるが、聴いていて救われた気分になりかけたら、すぐに突き放される。全体に漂う空気が不穏だし、カニエ自身も、主役を食う勢いでいい仕事をしている客演のラッパー陣も総じて攻撃的だ。“ヘヴン・アンド・ヘル”の終盤で「神様は俺が防弾ベストをつけているのを知っている」と断ったあとで「音楽でみんなを救うんだ(Save my people through the music)」と真摯な言葉を吐いたと思ったら、「Let it grrat!(ガンガン音を立てろ!)」と、絞り出すような声で剣と盾がぶつかり合う音をくり返し模している。怒りと紙一重の祈りが込められた、この部分は何度聴いても鳥肌ものだ。だから、元気はもらえる。このアルバムはめくるめく2021年のカニエ渦(禍、ではない)であり、聴いているあいだは目の前の風景を変えてくれる。天才プロデューサー、カニエ・ウェストに求めるのはその一点であり、ありがとね、と思いつつ、ファンは向こう数年カニエ劇場につきあう英気を養うのだ。
カニエ・ウェストの『ドンダ』は、ストリーミングが集計対象に含まれるビルボードのゴスペルおよびクリスチャン・アルバム・チャート、あるいはそれぞれのソング・チャートで大健闘中で、アルバムでは1位を、ソングでは収録曲の9割がランクインし、しかも、その多くが1位(“ハリケーン”)以下上位をほぼ独占したまま1ヶ月が経過している。その一方で、ゴスペル・エアプレイ・チャートでは、彼の曲は上位40曲に1曲もなく、ダウンロード数の単純集計によるセールス・チャートでも同様の傾向を見せている。ちなみに、HOT100でも、同じく収録曲の9割はチャート入りしているが、30位までに全曲が並んでいるわけではない。
これは、カニエの楽曲のストリーミング回数が、ゴスペルあるいはクリスチャン・ミュージック基準では、通常のランクイン曲と比べ桁違いに多いことに起因していて、ゴスペル・リスナーに圧倒的に支持されているのとは少し違うだろう。ここまでで類推できるのは『ドンダ』は、ひとまず、キリスト教信者よりも、カニエ教信者に厚くサポートされているということ。
つまり、今回のアルバムが出る前に、彼が「今後はゴスペルしか出さない」と言おうが、世界中のカニエ教信者は聴くし、他方、他人を誹謗中傷するような表現が結構あるのでは、と訝しむキリスト教信者(の音楽ファン)は、聞く前に踏みとどまってしまうかもしれない。そのあたりを最初に意識して作られたのが、2019年の『ジーザス・イズ・キング』だった。そこには、その手の表現や言葉は基本的に用いられていない。そして、そのアルバムが、2021年にグラミーのベスト・クリスチャン・アルバムに輝いたのだ。
ただ、収録曲のひとつ“ハンズ・オン”では、サンデー・サービスを地道に続けていたカニエがクリスチャンであることを認めたがらないクリスチャンに向け、手を差しのべよ、と歌っていた。また、クリスチャンおよびゴスペル・ラップに特化したメディアも、カニエの新作の告知こそすれど、それ以上の扱いはないような状態だ。ゴスペルとの関係において、前作の時点で既に彼は、特別な(どこにも帰属できないような)立ち位置に置かれてしまったのではないだろうか。
そして、それは、前作と『ドンダ』との間で発表された“ウォッシュ・アス・イン・ブラッド”にも表れていたと思う。様々な暴力を記録したフッテージを編集したミュージック・ヴィデオにも目を惹かれたが、そこで、カニエは、あまりにも罪深き「サグ・ライフ、仕方なく売人を続ける生活、大量虐殺、奴隷制」を挙げ、「すべての罪から、イエスの血がわたしたちを清める」と説き、いかにもゴスペルだ。そして、ビートはインダストリアル・トラップというか東アフリカの〈ニゲ・ニゲ・テープス〉発のエレクトリック・ミュージック的な先鋭的なものだ。これは、特別な立ち位置に置かれた彼だからこそ可能だった曲だとも言える。
仮にそうだとしても、この曲の次に出した“ナー・ナー・ナー”とそのリミックスを『ドンダ』リリースの直前にストリーミングから削除したのは、「露骨な表現を含む内容や歌詞」を有する楽曲に該当のおそれあり、を示すEの表示はなくとも、リリック内容的に『ドンダ』の収録曲のそれらとそぐわないとの判断からだとしたら、彼は彼なりに、クリスチャンや、キリスト教に関心を抱いてくれそうなリスナーの存在を意識していることになる。『ドンダ』には、E表示のある曲は1曲も入っていない。
その上で、ゴスペルの限界を試すというか、うまく行けば、許容範囲の拡大を目指したい。そんな意欲が、『ドンダ』には、前作と違ってはっきり見られる。しかも、それがわかりやすい。“オフ・ザ・グリッド”ではフロウ(と“テル・ザ・ヴィジョン”ではポップ・スモーク)ごとブルックリン・ドリルを投入する一方で、教会音楽に欠かせないオルガンも要所要所で入れ込んでいる。特に後者は、『ジーザス・イズ・キング』では1曲のみだったため目立つ上に、例えば、“ジュンヤ”では狂ったようにループさせている。ゴスペルの構成要素としてすぐに思い浮かぶオルガンを、既存のイメージに依存しているように見せかけ、実はそこからの解放を狙った意図は、インダストリアル・テクノのゲサフェルスタイン(過去には“ブラック・スキンヘッド”等の制作に参加)をプロデューサーに迎えた“ジーザス・ロード”やラストの“ノー・チャイルド・レフト・ビハインド”にも込められていると思う。
さらに、カニエは、教会での体験の再現を考えたのか、宗教的興奮状態に達した会衆のひとりが、聖霊の賜物とされる不可解なことばを語り続ける「異言」(スピーキング・イン・タングス)の音声をサンプルしている。カニエは、この事実にすぐ気づくクリスチャンを求めているのか、それとも非日常的なこの事態に興味を抱くクリスチャンではないリスナーを求めているのか。
こうしたリスナーへのなぞかけみたいなものは、『ドンダ』への客演者リストから嗅ぎとることもできる。“ジーザス・ロード”のジェイ・エレクトロニカといえば、自らが属するネイション・オブ・イスラムにおいて反ユダヤを意味する表現を、サイモン・ウィーゼンタール・センターの副所長名指しのツイートで使っていた。“ジェイル・パート2”のマリリン・マンソンは、3人の女性から性的暴行で訴えられ、ダベイビーは、HIV感染者や同性愛者への差別発言により「キャンセルされ」謝罪や償いに奔走しだした。“ビリーヴ・ホワット・アイ・セイ”のブジュ・バントンといえば、1992年の“ブーム・バイ・バイ”がホモフォビアだと叩かれ続けれ(2019年に自ら各ストリーミング・サービスから取り下げ)た。“ニュー・アゲイン”のクリス・ブラウンといえば、リアーナに暴行を働いた。彼ら全員をこのアルバムに招いたカニエ自身、2018年には、「自ら選んで奴隷になったのでは」発言で、キャンセルされた。「すべての人が罪をおかした……」とは聖書の言葉だが、その罪の最新版が「キャンセルされるような行為をすること」であるかのようだ。そういったすべての人たちが正しい人として神に認められるのも、「キリストによる贖い」があったからだと、カニエも聖書通りに続けたかったのだろう。
ただし、キリスト教に関心がなければ、アルバム全体を使った、という意味では、こうした大がかりな計画も、当事者たるカニエによる「キャンセル・カルチャー批判」と理解されるにとどまってしまうだろう。逆に、クリスチャンで且つポップ・ミュージック事情に詳しいリスナーなら、そういうことか、と膝を打つことだろう。少なくとも『ドンダ』は、クリスチャンとキリスト教に関心を持ちそうなリスナーの存在は意識している(“ジーザス・ロード”や“ロード・アイ・ニード・ユー”等のタイトルは、それらを何度も唱えてくれることを願ってのものだろう)。同時に、ここが難しいところなのだろうが、既存のゴスペル・ミュージックの限界というか境界の拡張を念頭に置いていることは伝わってくる。しかし、その限界や境界の設定地点については、こぢんまりとまとめた前作からは大きく踏み出してはいるためか、それなりに苦慮(深慮)しているような気配がある。もっとも、その苦慮(深慮)から、フレッシュな楽曲が生まれる可能性があることを『ドンダ』は聴かせてくれもするのだが。
