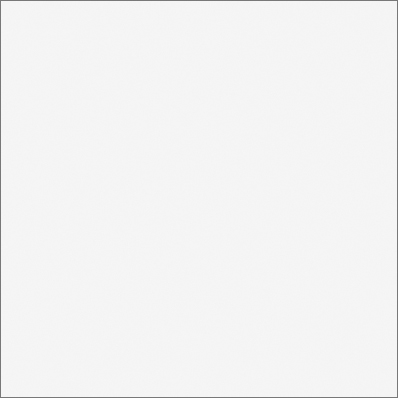
テレビ・ドラマ『アトランタ』の主人公アーン、つまり俳優ドナルド・グローヴァーの顔を見て何回爆笑したか。とりわけ面白いのは、ちょっと調子の悪い時の表情。コメディアンにも色々なタイプがあると思うけど、顔というか表情の面白いのは基本ではないでしょうか。ポップ音楽の興味があり『アトランタ』を観たことがない人には、大学中退の主人公が従兄弟のラッパーのマネージャーになろうとし、アトランタのストリートと元カノの周囲を徘徊するこのコメディをこの機会に観始めることを強くお勧めします。
もちろん『アトランタ』が広く成功した魅力を持つことが出来たのは、ドナルド・グローヴァー、つまりアルバム『3.15.20』のチャイルディッシュ・ガンビーノの表情だけではなくて、大きな都市の人々が――通常“ゲットー”と呼ばれるような環境とそこにいるような人々も含め――いかにモニターのこちら側と変わらないコミュニケーションをしているかを露わにしたことに大きく拠る。人種を含めて適度にステレオタイプ化された登場人物たちは右往左往しながら、決していつも難しい単語は使わないのだが、見上げる目つきや手の動かし方まで含めてニュアンス豊かに何を感じ考えているかを表現する。物語はもちろん、そのように彼の地の暮らしをディコーディング(通常日本語では、デコーディング)し拡げて見せたことが魅力の核にあるという意味で、このドラマはオフビートなヒューモアに溢れている。私たちみんなの実際の生活と人生がオフビートであるように。
『3.15.20』は、ほぼ10年間続けているグローヴァーのラップ/ポップ音楽のプロジェクトの最新作で、日本でも音楽ファン以外に広く知られるようになったグラミー賞4部門を獲得の2018年の”ディズ・イズ・アメリカ”以後初めてのアルバムだ。このアルバムを賞賛する人もいるだろうし、そうでもないと考える人もいるだろう。そのことは、このアルバムのみならずチャイルディッシュ・ガンビーノの音楽の底に流れるある種の憂鬱さ、この形容が極端ならば居心地の悪さをどう感じ受けとるかに関連しているように思える。例えば、5分足らずの“42:26”、原題“フィールズ・ライク・サマー”が始まって1分以上経過したところでそれはラップにお馴染みの“サマー・アンセム”などではなく地球温暖化を憂う歌であることが分かること。例えば、『アウェイクン、マイ・ラヴ!』以前の作品からも繰り返し表れるコーラス/合唱は、束の間であっても忘我の境地を約束しない。むしろ、合唱を忘我の境地と結びつける人たちがいたことを聞き手に意識させる。もう一つ、例えば、愛する人に語りかける曲だと思われる“24:19”を最後まで聞いてほしい。
付け加えるなら、チャイルディッシュ・ガンビーノの音楽はヒップホップのフォーマットをも使った何か別のモノだ。舐達麻の“GOOD DAY”のような曲と比較してもそれは明らかだ。知性をそこに存在させ感じさせながら聞き手に快哉を叫ばせる構造をヒップホップは確立したので、それは遠近法を利用したディコーディングとは別のことだ。ポップ音楽の専門家たちは彼の音楽作品をどう考えるか?
最後に、真っ白で何も描かれてないジャケット?に、リリース年月日をアルバム・タイトルに、タイムスタンプを曲名にしていることについて。色々な解釈が可能であろうし、複数の理由があるだろう。でも、ポップ音楽における“コンセプト・アルバム”なるものは(ある程度)幻想の産物だという示唆のように思えた。そして、それも、ドナルド・グローヴァーではなく、チャイルディッシュ・ガンビーノの名の下でリリースされ宣告されたのである。
これから始まるレヴューは、チャイルディッシュ・ガンビーノのキャリアにおける最高傑作は『ビコーズ・ジ・インターネット』(以下『BTI』)であるという大前提に基づいたものである。この意見に同意できるようなリスナーなら、本作『3.15.20』を一通り聴き終わった時点で、『BTI』と本作には、まず、不可思議なサウンド(エフェクト)で始まり、それと同じ音で終わる、共通点があることに気づくだろう。もっとも聴く前であっても、収録曲の大半がタイムスタンプをそのまま曲名にしているのは、『BTI』で収録曲順にタイトルの頭にローマ数字をふり(第何章の部分は割愛されているとはいえ)例えば「第1節」にあたる曲であることを明示していたように、アルバム全体がひとつながりで、ひとつの作品なのが一目見てわかる。この点を加えずとも、楽曲群の構造や採用したサウンドだけで、どちらも“実験的”だと形容したくなる作品でもある。
例えば、『BTI』収録の“II. Zealots of Stockholm(Free Information) ”は、甘い歌声とメロディで始まったかと思いきや、それが1分半も続かないうちに、狂暴なベースドロップが乱入し(デス・グリップスか……)、不穏な重低音を背にビーノがラップ、キーロ・キーシュの台詞のような声を挟み、ラップと共に聴こえるのは最初のパートのコードを押さえるピアノに変わり、加工された声がしゃべるアウトロ、さらに、飛び立ってゆく航空機の音へと続く。
2013年リリースのこの曲が、こうした込み入った構造をとり、航空機の音まで入れたのにはわけがある。『BTI』には同名の脚本があり、そのなかで、アルバム収録曲を再生する箇所が逐一指定されている。脚本では、主人公ザ・ボーイ(といっても年齢は20代半ば)は客死した父親の遺骨を受け取りにストックホルムへと旅立つ。このあたりで脚本はすでに半ばも過ぎていて、もう一波乱の後、物語はさらに新たな展開を見せると思いきや、それをぶったぎるかのような、かなり唐突な結末を迎える。そのため、今に至るまで、このザ・ボーイの生死については取り沙汰され、あの〈ラップ・ジニアス〉主催でビーノの協力を得て、問題の“結末”の続きを書いたオリジナル脚本コンテストが実施されたこともあった。
こうした経緯に少なからず興味を示していたリスナーであれば、非常に低い音量ではあるのだけど、本作で最初に耳に入ってくる音が、フラットライナーに転じた瞬間の心電図のアラーム音に似ているような気がしたかもしれない。この音で始まる1曲目の“0.00”なるタイトルには、単なるタイムスタンプ以上の意味が込められている可能性すらある。『BTI』の幕切れで繰り返されるのが「You are here now. You have to help me」なら、本作冒頭の「We Are We Are We Are」で一セットのフレーズは、まるで過去・現在・未来それぞれの世界に存在している人たちが一斉に、ザ・ボーイに存在確認を促しているかのようだし、どちらの声にもエフェクトがかけられている。
ARアプリを通じてリリース済の、次の“アルゴリズム”がタイムスタンプ表題に変えられていないのは、ビコーズ・ジ・インターネットという表題との親和性からか。ここでは歌声がテクノロジーに侵食されたかのようだ。初出時は、ルドヴィック・ヨランソンが映画『ブラックパンサー』のスコアで聞かせたダンサブルなビートを、例によってビーノと相談して改良したものと思い込んでいたが、この曲の制作陣に彼の名前はない。果たしてスーパー・コンピューターのパワーにただ単に踊らされているだけでいいのか? アウトロには、心臓の鼓動を思わせるビートと子供の声が聞こえる。
次もタイムスタンプではなく“タイム”と名づけられ、この中の短いサビの部分(もう“時間”がない……と)を、少年と少女が教会内であどけない声で歌う姿をビーノ扮するデニが見守る場面が出てくるのが、映画『Guava Island』だった。そこから、このフル・ヴァージョンに、クワイア(デビュー作『キャンプ』でのそれよりは控えめではある)と相手(役)の女性(ただし、リアーナではなく、アリアナ・グランデ)が加わっているのも理解できる。同時に、デニのみならず、『BTI』のザ・ボーイの立場からしても、アルゴリズムに左右されたくない自分の残された「時間」も気になるところだろう。
このザ・ボーイは、ドナルド・グローヴァー自身を下敷きにしている面もあり、アトランタ育ち。クワイエットストームなR&Bの趣さえある“12.38”の後半に登場する21サヴィッジも英国出身ながら育ったのはアトランタ。ドナルドはこの地との関係を同名のドラマによって広く知らしめることができた一方、ビーノはオリジナル・アルバム中に限った場合、アトランタと直結できる要素を前面に出したのは、実は今回が初めてだ。
その『アトランタ』に出てくるブラック・ジャスティン・ビーバーが歌いそうな軽快なファンク“19.10”は「思い出す、あれは6歳の頃、父さんが……」と始まる。「父と子」を主題のひとつとしていた前作『アウェイクン、マイ・ラヴ!』のサウンド選択の理由が、実はファンク好きだったビーノの父の趣味を直接踏襲したものだったことが、あらためて、ここにも息づいている。それ以上に、この曲で気になるのは長めのアウトロで聞こえる、何かが生成あるいは規則的な運動を繰り返しているさなかに生じているような音だ。それと同一ではないものの、同種の音がイントロとアウトロで聴こえるのが『BTI』なのだ。この音の繰り返しは『BTI』の記憶の反芻なのだろうか。『3.15.20』に『BTI』がまるごと含まれているとも言えそうだ。
アウトロの意味は、微妙に揺れるオートチューンにフランク・オーシャンっぽさがあり、カリフォルニアへ行ってしまったあのコの記憶をよみがえらせる次の“24.19”でより重要になる。本作のタイトルは『3.15.20』。ところが、同日にdonaldgloverpresents.comで発表され限定12時間連続ストリーミングされたヴァージョンでは、この曲の6分43秒地点、つまりアウトロの途中から1曲目が始まっていたのだった。具体的に言うと、“24.19”の6分43秒地点から聞こえてくる1分近く続く苦しげな息づかいをアルバム全体のイントロとしていたのだ。“ディス・イズ・アメリカ”のミュージック・ヴィデオを覚えていたら、ここでの荒い息づかいをあのラスト・シーンの続きと考えたくなるだろう。それを促すかのように、このイントロと直結する“32.22”では、暴動でも起きたかのような、そして、クリッピングあたりのインダストリアルな感触を粗削りにしたようなサウンドが飛び出す(3月15日の時点で公表されたアルバムのアートワークのものとおぼしき下絵も、ここに対応しているようにも思える)。と同時に、この荒々しい息づかいは、生死の境をさ迷い、しばし息を吹き返したザ・ボーイの声かもしれない。
しかし、世の中では、限定ストリーミングをおこなった3月15日の12時間のあいだだけでも、激しい呼吸困難を引き起こす新型コロナウイルスの脅威は高まるばかり。荒々しい息づかいで始まるアルバムなど出せるのだろうか。そこで、急遽、ある意味苦肉の策として考え出されたのが、収録曲も収録時間も全く変えず、該当箇所をアルバムの中間部近くまで後ろにずらし、どこかでハサミを入れ、そこからあとの部分をアルバムの前半の空いた箇所に移動することだった。
問題はどこにハサミを入れるか。つまり、どこをアルバムの冒頭に持ってくるかだ。結果的に選ばれたのは、アルバム冒頭で聴かれるのと同じ音が5秒ほど続いた後の箇所だった。3月15日公開時には繋がっていた部分に思い切ってハサミを入れたのだ。それにより、アルバム全体が、フラットライナーに転じた瞬間の心電図のアラームを思わせる音で挟まれることになった。すると、あわせてわずか10秒ほどの「時間」のなかで、生死の境をさまようザ・ボーイの、もしかしたら人生の走馬灯なのかもしれないし、過去・現在・未来の時空を超えた魂の彷徨かもしれないものが展開されているアルバムとの見立てもできる。
このザ・ボーイとは、ドナルド・グローヴァーから彼自身の弱さや現実や理想や夢を託されたキャラクターであり、それを肉体化したものが、チャイルディッシュ・ガンビーノだと考えれば、アルバムの後半の収録曲の並びも厚みを増してくる。ビーノ流“カントリー・ラップ”とも言える“35.31”の終盤では、今まで歌っていた曲が逆再生される。かつてアウトキャストは“シー・リヴス・イン・マイ・ラップ”のビートを同一アルバム収録の“ヴァイブレート”で逆再生していた。ビーノとラップとカントリー(地元)をつなぐのはアウトキャストなのだろうか。ところが、この逆再生が、あのクイーンの多重録音風ハーモニーに転じて始まる“39.28”、そして、2018年には“フィールズ・ライク・サマー”(サビメロが“ラヴ・ドント・リヴ・ヒア・エニモア”のそれを想起させる符合が上手い)としてリリースされ、さりげなく且つ大胆に気候変動を取り上げた“42.26”へとつながり、2018年以降のトレンドが集約されるかたちとなる。『アウェイクン、マイ・ラヴ!』では「ビーノとその子供」から訴えられていた自尊心の大切さというテーマが次の“47.28”では、肉声を加えることで「ドナルドとその子供」という設定で更新され、ラストの“53.49”では、“ディス・イズ・アメリカ”よりもパワフルに「あらゆる瞬間に愛はある、太陽の元では、ボーイよ、俺は自分のやりたいことをやった…おまえも自分のやりたいことをやれ」と熱く歌い上げている。ザ・ボーイから見れば、成長し、子を持つ父となった未来の自分がドナルド・グローヴァーということになるだろう。
本人の発言通りなら、本作はチャイルディッシュ・ガンビーノとしての最後のアルバムということになる。彼はこのままいなくなってしまうのだろうか。だが、ここまで書いてきた見立てにならうなら、10秒程度の間に心臓ショックも与えられただろうし、その反応を「記録した」のが、当初アルバムのイントロとされていた部分なのかもしれない。さらに、このアウトロの終わった途端に蘇生措置を施したなら、完全に息をふきかえすかもしれない。はたして、それは、チャイルディッシュ・ガンビーノなのか、ドナルド・グローヴァーなのか。
コロナウイルスによる被害拡大のさなかで急遽収録曲順をかえ、アルバムのアートワークを白一色(今、この色から何を連想するだろう?)に変えた『3. 15. 20』ではあるが、それでも、アルバム全体の内容や状況や予想できる先行きは不透明で、いぜん予断を許さないものであり、厳しい状態なのは、今の世の中の現状と重なる。しかし、そういったことよりも、結果的に終盤で畳み掛けられることになった、前向きなメッセージのほうに、強いアクチュアリティを感じなければいけない。
