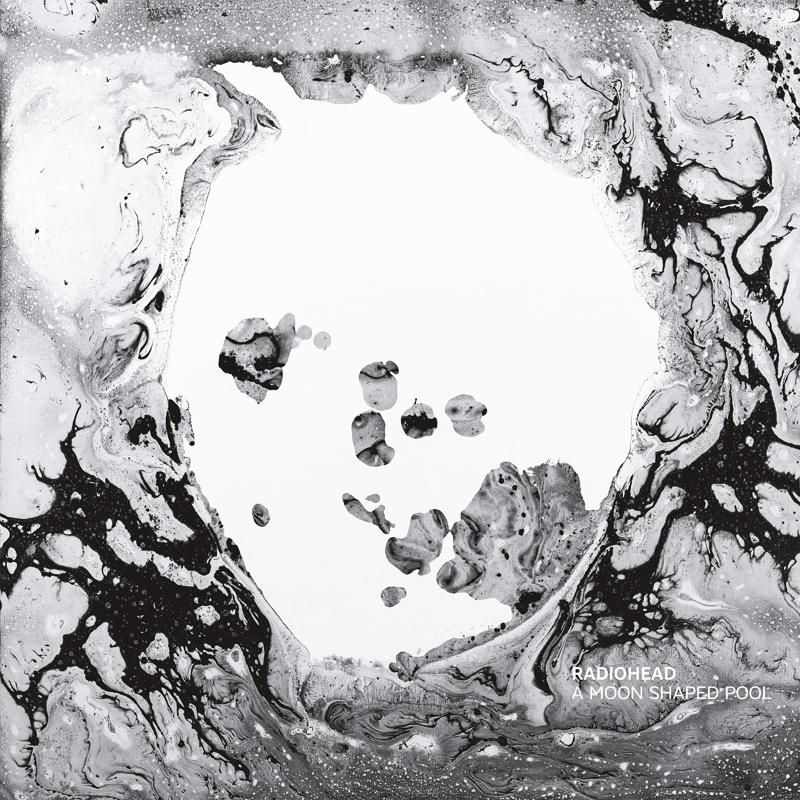
本作を一聴した最初の感想は「ジョニー・グリーンウッドのアルバム」だということ。“デイドリーミング”のミュージック・ヴィデオを手掛けているポール・トーマス・アンダーソン作品をはじめとしたサウンドトラック、ドイツの老舗クラシック・レーベルである〈グラモフォン〉からリリースされたナショナルのブライス・デスナーとのスプリット・アルバムなど、すでにクラシックの作曲家としての地位を確かなものとしているジョニーの手腕が、ロンドン・コンテンポラリー・オーケストラによるストリングスとコーラスが重要な役割を果たしている本作に大きく反映されていると考えるのは、ごく自然なことだろう。
一方、トム・ヨークはといえば、近年のソロおよびアトムス・フォー・ピースではビートの追求に執心し、「もはやレディオヘッドには興味がないのでは?」とも揶揄されていたが、一昨年の『トゥモローズ・モダン・ボクシーズ』では作風がアンビエント寄りに変化し、この路線とジョニーの作曲能力の融合に新しいレディヘッド像を見出したのかもしれない。ブラーが昨年発表したオリジナル・メンバーによる16年ぶりの新作『ザ・マジック・ウィップ』は、デーモン・アルバーンではなく、グレアム・コクソンが主導権を握ることで完成まで漕ぎ着けた作品だったが、それにも似た変化がバンドに起こったとも言えよう。
その上で本作が特に刺激的なのは、音響的な側面からのクラシックの再解釈に挑んでいるという点。重厚かつ躍動感のあるストリングスのアレンジメントに加え、それらがアンビエント/エレクトロニカを通過した耳によって電子音と共に立体的に配置されることによって、未知なるリスニング体験を生んでいるのだ。そういった意味で本作は「15年後の『キッドA』」、もしくは「バロック時代のレイ・ハラカミ」といったところ。楽曲全体のポリリズムな構造と鮮やかな転調、穏やかなサウンドスケープからサイケデリックな終盤へと移り変わっていく展開が見事な“デイドリーミング”は特に素晴らしい。
よって、このアルバムをクラブ・ミュージック育ちのミュージシャンによるジャズの再定義の一方で起こっている、クラシックの再定義の流れに位置づけることは勿論可能だろう。チェンバー・ポップとポスト・クラシカルの融合とも言うべきニコ・ミューリーとOPNの共演や、最近だと〈クランキー〉から〈4AD〉に移籍し、ヨハン・ヨハンソンをアレンジャーに起用して、聖歌隊をフィーチャーしたティム・ヘッカーの新作『ラヴ・ストリームズ』などと、本作は確かに時代感を共有している。
ラストの“トゥルー・ラヴ・ウェイツ”にも触れておきたいが、個人的にはレディオヘッドのレア曲の中では収録が噂されていた“リフト”の方が思い入れが強いので、その点は少々残念な気持ちもある。しかし、「Empty all your pockets/'Cause it's time to go home」や「Today is the first day of the rest of your days」というラインを持つ“リフト”がアルバムの最後に収録されるとなると、なんだかバンドが折り返し地点を曲がるような雰囲気を醸し出してしまうだろう。もしかしたら、実際ここ数年のトムにはそんな気分もどこかにあったのかもしれない。しかし、ジョニーの助力もあって、またしてもキャリアを推し進めることが出来たからこそ、“リフト”ではなく、“トゥルー・ラヴ・ウェイツ”がクロージング・ナンバーに選ばれたのではないだろうか。
“トゥルー・ラヴ・ウェイツ”で繰り返される「Don’t Leave」や、“デイドリーミング”のビデオに象徴されるように、今もレディオヘッドは帰る場所のない迷子のままなのだ。
始まりは、やはり『キッドA』だったのだと思う。それは、ギター・ロック・バンドが、「非ギター・ロック」との付かず離れずの距離感と緊張関係のなかで、その「非ギター・ロック」からの刺激や応答を対象化することでいかにして「ギター・ロック」を拡張させることが出来るか、という。至極簡略すれば、そのケース・スタディの実践であったレディオヘッドにとっての2000年代の起点となった『キッドA』において、あのテクノやIDMや同時代のエレクトロニック・ミュージックと縦横に組み交わしたエクレクティックなサウンドスケープをもたらした、デジタル・テクノロジーの敷衍と飽くなきスタジオ・ワークの探求。はたして『キッドA』とは、つまるところトータスの『ミリオンズ・ナウ・リヴィング・ウィル・ネヴァー・ダイ』や『TNT』を視界に意識した、レディオヘッドなりの「ポスト・ロック」への意趣返しだったのだと、今にしてあらためて思い至る。そして、いつだったかデーモン・アルバーンが「バンドってある地位まで到達してしまうと、それ以上自分たちを作り替えていく能力を失ってしまう」と彼らについて評した言葉とは真逆に、『キッドA』から『ザ・キング・オブ・リムズ』まで含めた5枚のアルバムとはまさに、レディオヘッドというバンドをみずからの手でその内外から作り替えていくために費やされた過程を記録したドキュメント、に他ならない。
『キッドA』を機に度合いを深めたデジタル・テクノロジーやスタジオ・ワークへの傾倒は、しかし、単に音楽性のレンジやヴァリエーションにおける「拡張」を促しただけに留まらない。言うまでもなく、それはバンドの演奏面、その意識や錬度にも当然大きな影響を及ぼしている、と見るのが妥当だろう。
たとえば『キッドA』(と直後の『アムニージアック』)に続く『ヘイル・トゥ・ザ・シーフ』と『イン・レインボウズ』の2枚のアルバムは、一見して与える「ギター・ロック」への回帰や揺り戻しとの印象とは裏腹に、もはやハードディスク・レコーディングやポスト・プロダクションと対等に置かれた関係において捉え直された生演奏の可能性、という意図をこそそこに汲み取られるべき作品だったはずだ。そして決定的だったのは、トム・ヨークがレッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーらと結成したプロジェクト、アトムス・フォー・ピースだろう。トム・ヨークがラップトップで作った「ソロ」・アルバム『ジ・イレイザー』の楽曲を「バンド」で披露する(ことをそもそもの目的に結成された)という、すなわちエレクトロニック/デジタルなマテリアルをライヴ・インストゥルメンタルによってリコンストラクトしていくそのプロセス(アルバム『アモック』の制作でもその手順が踏まれた)が意味していたこととは、言うなればデジタル・テクノロジーを対象化することで果たされた生演奏の「拡張」、に等しい。翻ってレディオヘッド本体への波及は想像に容易く、その成果は、サンプル・ビートやループが網の目状に走るマシーナリーなリズム・ストラクチャーを骨組みに通した次作『ザ・キング・オブ・リムス』が雄弁に物語っていた通りである。
そうしてレディオヘッドが2000年代を通じて繰り広げたワーク・イン・プログレス。むしろ、その試行錯誤や紆余曲折の過程をこそ作品にして成否を問いかけてきたようなこれまでの張り詰めたムードは、このニュー・アルバムにはほとんど感じられない。「洗練」とか「円熟」といった言葉は軽々しく持ち出されるべきではない。ことは承知の上で、しかし、エレクトロニックな音響的要素とバンド・サウンドがもはやスムースに撹拌され、互いを含み合う入れ子構造をなしたようなダイナミクスは、積年にわたる彼らのトライアルが行き着くところまで行き着いたことを窺わせて余りあるものだろう。とりわけ、この10余年をかけてトム・ヨークが方々に足を延ばしてまで会得に勤しんだ現行クラブ・ミュージックやビート音楽のマナーをいかにして5人ないし6人のロック・アンサンブルに落とし込むか、というアイデアは『イン・レインボウズ』の“15ステップ”しかり、前作『ザ・キング・オブ・リムス』の“ロータス・フラワー”しかりひとつの懸案だったわけだが、今作の“フル・ストップ”はその最適解を示し得ていると言えるのではないか。かたや、シンコペートする乾いたビートを追いかけてギター・ソロが長回しのように続く“アイデンティキット”は、派手さこそないが、近作以降のミニマルに徹せられた演奏の習熟度を窺わせる佳曲だ。
一方で、この『ア・ムーン・シェイプト・プール』は、レディオヘッドによるアンビエント/モダン・ドローン・アルバムである、と言ってしまっても構わないかもしれない。そうした現代音楽やクラシックの意匠とは言うまでもなく、機能和声や対位法に対する意識付けによって拓けたバンド演奏の自由度、何よりエレクトロニック・ミュージックへの傾倒によってそれこそ『キッドA』を境にして彼らのなかで大きく押し広げられた領域だったわけだが、今作では近作に増してその特色が顕著に際立っている。勿論、だからと言ってこれは「純正」のアンビエント/モダン・ドローンとは異なる。あくまでそれは、バンド・サウンドを軸に構築された音のレイヤーによってテクスチャーと響きが与えられるものであり、まるでティム・ヘッカーがプロダクションを手がけたフェアポート・コンヴェンションかのような“ザ・ナンバーズ”、抑揚を排した演奏と魔術的に織りなす“ティンカー・テイラー・ソルジャー~”は、ソロ・ワークでもサイド・プロジェクトでもない、レディオヘッドという不動の共同体でこそ成し得た極み、と言いたい。そして、その曲作りの核を担うトム・ヨークとジョニー・グリーンウッドの才気は、現代音楽やクラシックとジャズやエレクトロニック・ミュージックのクロスポイントから目覚ましい音楽が次々と登場しているこの2016年において、タイヨンダイ・ブラクストンやフローティング・ポインツことサム・シェパードといった俊英と切磋琢磨するような瑞々しさをまだまだ感じさせてくれる。
ポール・トーマス・アンダーソンが制作した“デイドリーミング”のMV。あてどなく徘徊するトム・ヨークが最後にたどり着いた雪山を見て、『キッドA』のジャケットに描かれていたあの雪山を連想したのは、自分だけだろうか。「もう引き返すことは出来ない」。トム・ヨークが歌っている。『キッドA』は、確かに始まりであり、ターニング・ポイントであったが、同時に「帰還不能点(the point of no return)」でもあったのだろう。であるとするなら、はたしてこの『ア・ムーン・シェイプト・プール』というアルバムは彼らにとって、これまでの長く険しい航路の末にようやく手をかけた到達点なのか。それとも、ふたたび新たな「帰還不能点」を意味する作品なのだろうか。少なくとも、ひとつの、大きな区切りとなるであろうことは、間違いなさそうだが。
ポール・トーマス・アンダーソンが監督した“デイドリーミング”のヴィデオが本作のモードとテーマのある側面をはっきりと示している。ドアを開けても開けてもどこにも辿りつけない、孤独で甘美な白昼夢……。PTA作品として見るならば2000年前後の(フィオナ・アップルに代表される)彼のミュージック・ヴィデオや『マグノリア』辺りのポップさやカラフルさではなく、『ザ・マスター』と『インヒアレント・ヴァイス』の間のどこかにあるようなサイケデリックなムード、あるいはジョアンナ・ニューサム“サポカニカン”のヴィデオとの連続性として捉えられるだろう。つまり、間違いなくレディオヘッドとPTAの「いま」を懸けて制作されたヴィデオだということだ。実際“デイドリーミング”はあまりに滑らかな撮影と編集の呼吸に思わず嘆息する一本で、『ア・ムーン・シェイプド・プール』のエレガントな導入として抜群のものだ。ジョニー・グリーンウッドを媒介として時折交わりながら、同時代をそれぞれの軌跡で辿ってきた両者の満を持しての邂逅としても、感慨深いものがある。
“デイドリーミング”はとくに“サポカニカン”と対比が顕著だ。カメラとの親密でチャーミングな視線のやり取りが魅力だった後者と異なり、トム・ヨークはヴィデオの終わりまでほとんど画面のこちら側に目をやることはない。このことから自分に連想されたのはむしろPTA作品よりもネメシュ・ラースローの『サウルの息子』で、同作はアウシュビッツで起こる殺戮を今様のリアルタイム性の強い撮影で描いたものだが、そこでは主人公サウルの周りで起こる虐殺からはピントが外されている。サウルは現実離れした暴力に焦点を当てて見つめないことで、なんとか正気を保とうとしているのだ。いっぽうでトム・ヨークはあちこちをワープしながら歩き続けているが、同様に、周りで起こっていること――「世界」――から隔絶されているようだ。『サウルの息子』も“デイドリーミング”も、観る者は映像の終わりでようやくじっくりと視線を合わせることができるが、そこで彼らはどこまでも「ひとり」だ。
オープニング、弦のスタッカートが鮮烈な印象を残す“バーン・ザ・ウィッチ”が、現在の荒れに荒れるヨーロッパの状況に影響を受けていることはじつにレディオヘッドらしいが、『ア・ムーン・シェイプド・プール』は“バーン・ザ・ウィッチ”に代表される悪夢のような現実と“デイドリーミング”に代表される物悲しい白昼夢が境目なく混ざり合った作品であるように感じられる。レディオヘッドの徴が刻まれたフラジャイルなピアノ・バラッドにフォー・テットとブリアルの音響がどこか「ゴーストリーに」溶け込んでいる“デイドリーミング”にしても、バンドの重要な影響元のひとつであるクラウトロック的反復とベース・ミュージックが一体化したような“フル・ストップ”にしても、ほとんど冗談のような分厚いストリングスが曲を飲み込んでいく“グラス・アイズ”にしても、エレクトロニカのざわめきとフォークが混ざり合ってオーケストラと緩やかに上昇する“ザ・ナンバーズ”にしても……いささか危険なほどの陶酔が横溢している。『ア・ムーン・シェイプド・プール』は、大きく言ってリズムのアルバムだった『ザ・キング・オブ・リムス』に対して弦のアレンジメントと和声の作品であり、そして――2010年代にクリシェになり下がった言葉を敢えて使うならば――バンド史上もっともピプナゴジックで、そしてドリーミーなアルバムである。だがその夢は、たんに心地いいものではけっして、ない。
たとえばグリフ・リスがヨーロッパの混乱に心を痛めながらも“アイ・ラヴ・EU”であくまでも慈愛を示したのに対して、“バーン・ザ・ウィッチ”でカルトな恐怖映画『ウィッカーマン』を参照するのは非常にレディオヘッド的だと言える。かつて『ボディスナッチャーズ』を引用していたことを思い出すまでもなく、この世界で現実に起こっていることはレディオヘッドにとって――あるいはトム・ヨークにとって、突飛なSFやホラーのように悪夢的なことなのだろう。言葉や描かれる情景は断片的だが、人びとの大規模な移動がパニックと不寛容を導いていることを描いていると思しき“グラス・アイズ”や、取り返しのつかない環境の変化がいままさに起こっていることをどこか呆然と眺めるような“ザ・ナンバーズ”は、グローバリズムが壊し続ける世界から彼らが相変わらず目を逸らせないことを示している。そして、アノーニ『ホープレスネス』のような直截的な政治性や覚醒はなく、そこにゆっくりと溺れていくようですらある……。あるいはそこではまた、かつて掴んでいたはずの愛と呼ばれたものがいつの間にか手からこぼれ落ちている(「この愛が冷えていくのを感じる」“グラス・アイズ”)。
だからこのアルバムは、還るべき場所がいつまでも見つけられない彼と彼らとわたしたちのサウンドトラックなのだろう。リッチなストリングス・アレンジにおいて“スペクター”との繋がりが感じられること、エンニオ・モリコーネからのかねてからの影響、スティーヴ・ライヒやエリック・サティへの目配せ、それにもちろん、PTA作品のサウンドトラック・ワークとの接続など、ジョニー・グリーンウッドの活躍がかなり前に出た作品であり、であるがゆえに、レディオヘッドというロック以外の音楽からのインスピレーションを飲み込み続けた「ロック・バンド」が手がけた、サイケデリックなアート映画につけられたオーケストラ作品のようである。はっきりとした物語もなければはじまりと終わりも判然としない、甘くて優雅で恐ろしい、永遠に醒めない夢のような……。
それでもこのアルバムの「終わり」に“トゥルー・ラヴ・ウェイツ”が選ばれたことは、バンドにとっても聴き手にとってももっとも感傷的な出来事だろう。それはライヴ盤『アイ・マイト・ビー・ロング』収録のヴァージョンにおけるライヴ的高揚とは真逆のインティメットなコミュニケーションを聴き手に求めるラヴ・ソングであり、だから本作がトム・ヨークのパーソナルな別離にのみ囚われたものではけっしてないことがこの曲を聴けばわかる。おそろしく優美な鍵盤の囁きと、まるきり子どものように、しかし同時に子どもを寝かしつけるように繰り返される「行かないで」。だがすべてのものは去り、愛は喪われ、世界は破壊され続けている。そしてわたしたちは、最後の一音が鳴ったときにようやく、この音楽と見つめ合うことができる……そこではわたしたちもまた、どこまでも「ひとり」だからだ。“デイドリーミング”の映像のように雪に閉ざされた誰もいない洞窟のなかで、とても孤独で美しく、悲しくて、優しい音楽が鳴っている。
