
ディアハンターは、アルバムごとにコンセプチュアルなアイデアを打ち出し、次々と姿を変えていくアーティスト。これまで1枚たりとも同じアルバムは存在しません。それ故に、「いつの時代のディアハンターが最高か?」の答えは、リスナー1人ひとりで違うはず。
そこで〈サイン・マガジン〉では、極めて多面的なディアハンターというアーティストの魅力を紐解くべく、3名のライターそれぞれにベスト・アルバム3枚を選んでもらいました。三者三様のアングルからディアハンターの作品をランク付けし、位置付けることで、バンドの多彩な魅力を改めて浮き彫りにします。
この企画の最後を飾るのは田中亮太氏。さて彼が選ぶトップ3とは?(小林祥晴)

ソングライターとしてもフロントマンとしても、ルックを含めあまりにカリスマティックであるため、ディアハンターと言えば、まずブラッドフォード・コックスに目が行ってしまうのも無理はない。だが、覚えておいてほしいのは、このバンドは決してワンマン操業ではないということ。2008年作『マイクロキャッスル』に収録されたキャリア屈指のキラー・チューン“ナッシング・エヴァー・ハップント”がジョシュア・フォウヴァーとモーゼズ・アーチュレタのリズム隊による作曲であることは忘れるべからず。
その観点から言えば、この『ハルシオン・ダイジェスト』は、チーム・ディアハンターとしてもっともバランスのとれた作品。まず、ベン・H・アレンをプロデューサーとして起用したことにより、プロダクションが整理され、格段に聴きやすさが増している。“グッド・ヴァイブレーション”的サイデリック・ドゥーワップの“リヴァイバル”や、サニーな“メモリー・ボーイ”など、ポップ・ソングとしても非常にウェルメイドな仕上がりだ。
そして、今作はロケット・パントによる2曲がまた良い。ブラッドフォードの才気とはまた異なった柔らかさな歌心があり、アルバムの要所で胸がキュンとなるそよ風を吹かせているのだ。
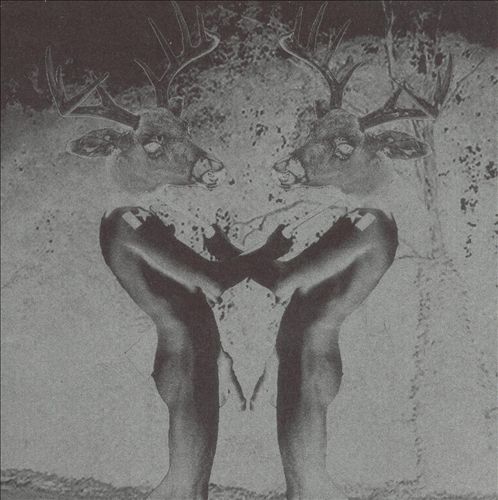
こちらは、そんなロケットが加入する前の1stアルバム。メロディとしての体裁をなさない――むしろ意識的に「良い曲」となることを否定するかのようなブラッドフォードの歌に代表されるグシャッとした音像。その密閉されたジャンク感は、押しつぶされ立方体となった金属ゴミを思わせる。加えて亡くなったオリジナル・メンバーのジャスティン・ボスワースへと捧げられた作品と言えば、えらくアングラでダークな音楽に思われるかもしれないが、誤解を恐れずに言えばこの作品は非常にチャーミングだ。プロデュースやポスト・プロダクションという意識に現在のバンドほど重点が置かれてなかったであろうがゆえの、ピュアなエモーションの炸裂が心地よくすらある。ディスコ・パンク~ポスト・パンクといった時代を感じさせる楽曲が目立つこともあり、ラプチャーの〈DFA〉以前の作品『アウト・オブ・ザ・レース・アンド・オントゥ・ザ・トラックス』にも似た健やかな初期衝動すら感じるのだ。なにより生々しさが魅力だが、“アドルノ”のグルーヴィなベース・ラインは“ステッピン・アウト”あたりも彷彿とさせ、最新作に通じるアーバン感も。

まったりとしたファンクネスとファニーなサウンド・コラージュがベック~フォレスト・フォー・ザ・ツリーズ的な90年代ネルシャツ・ポップ感さえも思わせたリード・シングル“スネイク・スキン”に嬉しい驚きがあった最新作は、筆者にとって一番のお気に入りとなった。
かつてのゲイズな要素はすっかり消え失せ、ひたすらに夢見心地のサイケデリック・ポップを聴かせてくれる作品だ。『ハルシオン・ダイジェスト』以来の参加となったベン・H・アレンによるプロデュースも相変わらず的確。打ち込みのビートや声のカットアップなどエレクトロニクスの要素もスペーシーなムードに拍車をかけ、ステレオラブのティム・ゲインとブロードキャストのジェームス・カーギルらゲストの人選も絶妙だ。ロケット作曲の“アド・アストラ”あたりはエール初期作と繋げることも出来そう。この快適なトリップ感はともすればサイケ探求者としてのバンドにとって彼岸への到達なのかもしれないが、自分にとってはタイム&スペース・マシーン的セーフティなチルアウト・ミュージックとして楽しい。
「いつが最高? 変わり続けるサイケ音楽の
万華鏡、ディアハンターの傑作アルバム、
トップ3はこれだ! その① by 天井潤之介」
はこちら
