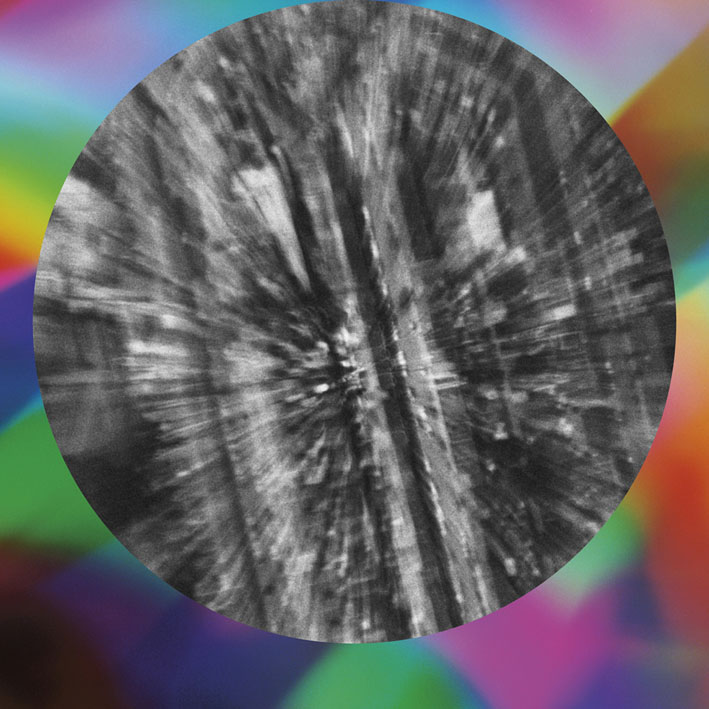
フォークトロニカのパイオニアとして名を馳せたフォー・テットことキエラン・ヒブデンはしかし、前作『ゼア・イス・ラヴ・イン・ユー』からダンスフロアへの情熱を自らの音楽の中にたぎらせるようになっている。最近は自主レーベル〈テキスト〉に活動拠点を切り替え、プロモーション活動もほとんどしなくなった彼が、その理由を自身の口から語っている記事を見かけたことはない。だが、公私ともに交流が深く、最近は同じくフロア志向を強めているカリブー/ダフニことダン・スナイスの発言は、ひとつのヒントになるだろう。
ダン曰く、5年前まで(2012年の時点で)ロンドンのクラブ・シーンでは何も起きていなかった。しかし、最近はポスト・ダブステップを中心に若手のいいDJやプロデューサーが次々と頭角を現し、面白いパーティも増えている。活気づいたクラブ・シーンには海外からも素晴らしいDJが訪れるようになり、とても勢いがあってエキサイティングだ。そして他の多くのアーティストと同じように、自分もまたその状況に影響を受けている――のだという。ダンの見方をそのままキエランにも当てはめてしまうのは、乱暴に過ぎるかもしれない。ただ、頻繁に同じパーティでDJをして、二人でスプリットの12インチまでリリースしている彼らが、ある程度そういった認識をシェアしていると考えるのは不自然ではないだろう。それに、ダンの発言を踏まえて『ゼア・イズ~』を振り返ると、なるほど確かに、と気付く点もある。
あの時点ではフォー・テット史上最もダンス志向のトラックだった“ラヴ・クライ”のリミックスをジョイ・オービソンとロスカに任せたのも象徴的だが、一番分かりやすいのは、くぐもった4つ打ちのメロウな8曲目のトラックを“プラスティック・ピープル”と名付けていることだ。これはキエランがレギュラー出演していたロンドンの有名なクラブの名前であり(小さいが、素晴らしく音響がいい)、ジェイムス・ブレイクが初めてダブステップに触れたことでも知られるFWD>>が開催されていた場所でもある。この曲自体はダンス・トラックではないものの、活況を呈するロンドンのクラブ・シーン、そしてポスト・ダブステップのシーンにおける重要拠点のひとつからわざわざ名前を拝借しているのだから、その入れ込みようも窺えるのではないか。
傍から見ていると、現在のイギリスはポスト・ダブステップの熱狂も一段落したように思える。だが、それでもキエランのダンスフロアに対する情熱に翳りはないようだ。というのも、オリジナル・アルバムとしては3年ぶりとなる『ビューティフル・リワインド』で、彼はダンス・ミュージックへのアプローチをさらに深めているからである。
本作のリード・トラックとして公開された“クール・FM”とは、90年代前半に実在したジャングル/ドラムンベース主体の海賊ラジオ局の名前だという。その事実に加え、「美しき巻き戻し」というアルバム・タイトルから推察しても、作品全体として当時のクラブ・カルチャーへのオマージュになっていると考えておかしくない。実際、“クール・FM”はフォー・テット流のベース・ミュージックに、ラジオDJのトークが曲に割り込んでくるときのような「ヘイ、ヘイ、ヘイ」という掛け声のサンプリングを被せたナンバーであるし、アルバム冒頭の“ゴング”はジャングルとジュークとガムランを繋ぎ合わせたようなトラックだ。ストレートに当時のレイヴ・ミュージックを連想させる曲はどこにもないが、それでもいつになくプリミティヴで性急な新曲の数々は、ある意味では20年以上前のダンス・トラックに近いムードを思い起こさせる。
と同時に、アルバムにはフォークトロニカ時代からのファンも満足させるような、繊細な美しさを湛えたメロディアスなトラックも少なからずある。しかし、本作はベッドルーム・ミュージックとダンス・トラックの間で上手くバランスを取ったという印象ではない。それに、エレクトロニカの淡い白昼夢の奥からダンスフロアの暗がりへの欲望が湧き上がり始めていた『ゼア・イズ~』ともまた手応えが違う。今のキエランの興味はもっとダンス・ミュージックへと振り切れている。不思議とそんな確信を抱かせるものだ。
もっとも、そういった嗜好の変化が、今年10周年記念盤がリリースされた『ラウンズ』や、第二期フォー・テットの代表作『ゼア・イズ~』を超える魅力を放つまでにはまだ至っていない。意図的なものなのか、かなりラフに作られているようなのも気には掛かる。だが、『ゼア・イズ~』のハイライトが本作の前哨戦のようでもあった“ラヴ・クライ”だったことを踏まえると、ひるまず現在の路線を邁進し、ひとつの到達点と呼べるような傑作を物にするのを待ちたい。
フォー・テットことキエラン・ヘブテンといえば、個人的にはやはり、2000年代の終わりにプロデュースを手がけた一連のサンバーンド・ハンド・オブ・ザ・マンの作品が印象深い。サンバーンド・ハンド・オブ・ザ・マンといえば、当時のフリー・フォーク勢の中でも、たとえばジャッキー・O・マザーファッカーやノー・ネック・ブルース・バンドと並んで最もフリーキーでハードコアな一群に挙げられたコレクティヴである。かたや、当時のヘブテンは、ブリアルとのスプリット盤をリリースするなど、初期のいわゆるフォークトロニカなスタイルからUKクラブ・シーンへの接近/ダンス・ミュージックへの傾倒を顕著に見せ始めたタイミングだった。その巡り合わせの妙もさることながら、それこそ2010年代を迎えて〈ノット・ノット・ファン〉や〈RVNG〉が提供するようなサイケデリックとエレクトロニックの混淆――サン・アロウとM. ゲディス・ジェングラスとザ・コンゴスの共演盤『FRKWYS Vol. 9: Icon Give Thank』を連想させる瞬間も――を予見させた両者の見事な邂逅に、なにより強く惹かれた。とくに〈エクスタティック・ピース!〉からリリースされた2作目の『A』は衝撃的で、それは自分の中でフォー・テットのイメージを大きく変えるものだった。
そうしたヘブデンの、ある種のプリミティヴなサウンドへの志向とその相性の良さは、サン・ラやフェラ・クティともプレイしたジャズ・ドラマー、故スティーヴ・リードとの本名名義による共演盤(2006~)においてすでに示されていたとも言えなくない。インプロヴィゼーションに応じるヘブデンの荒々しく多彩なエレクトロニクスは、前後してリリースされたフォー・テット名義の『エヴリシング・エクスタティック』におけるトライバルなビートやユーフォリックなサイケデリア――アニマル・コレウティヴとヴァシュティ・バニヤンを結びつけたのがヘブデンだったことを思い出されたい――とパラレルな関係を描いていた。いや、そもそもフォー・テットの評価を決定づけた2001年の『ポーズ』を聴き返せば、そのエレクトロニクスと生楽器のあわいを飾る自然音のフィールド・レコーディングに、テクノやIDMに対する野性/野生の響きともいうべきサウンドへのヘブデンの関心を確認できるだろう。先だってリリースされたオマール・スレイマンのアルバムのプロデュースも、ヘブデンにとっては、おそらくそれらの延長線上に意識されたものなのではないか。
といった感覚の耳には、本作はきわめてスムースに聴こえる。ムスリムガーゼをカットアップしたような“ゴング”は格好のイントロダクションだが、マシーナリーな4つ打ちにジャングルのサンプリングを和えたインダストリアル風テクノ“クール・FM”、パーカッションとマリンバがシンコペイトする“エアリアル”をはじめ、随所に横溢するのはプリミティヴでコンシャスな身体感覚。あるいは、“クラッシュ”や“ユニコーン”ではフォー・テットらしいアブストラクトやチルアウトな感覚も打ち出されているが、たとえば“パラレル・ジャレビ”のようにミニマルでもオリエンタルな女性ヴォーカルを被せられることで、それは一転して辺境サイケの装いも帯びる(※ちなみに「ジャレビ」とは中東で庶民的なお菓子の名前)。ハード・ミニマルな“ブックラ”は本作中で最もクラブ・オリエンテッドなトラックといえるが、ここでも女性ヴォーカルのカットアップやインダストリアルなノイズが強烈なフックとなっていて、クローザーの“ユア・ボディ・フィールズ”は、まるでシンセウェイヴに対するヘブデン流のニュー・エイジ解釈とでもいった趣だ。
もちろん、こうした要素はこれまでも散見されたものだろう。ただ、前作の『ゼア・イズ・ラヴ・イン・ユー』やシングル集『ピンク』で露わとされた近作における(ベッドルームから)ダンス・フロアへの転回をへて、クローズアップされるかたちで顕在化した側面もあったに違いない。そしてやはり、前述のヘブデンのサイド・ワークは、伏線とは言わずとも補助線を本作に引くものとして再考の余地があると考える。野放図で繊細、野蛮で優美なダンス・レコードだ。
