
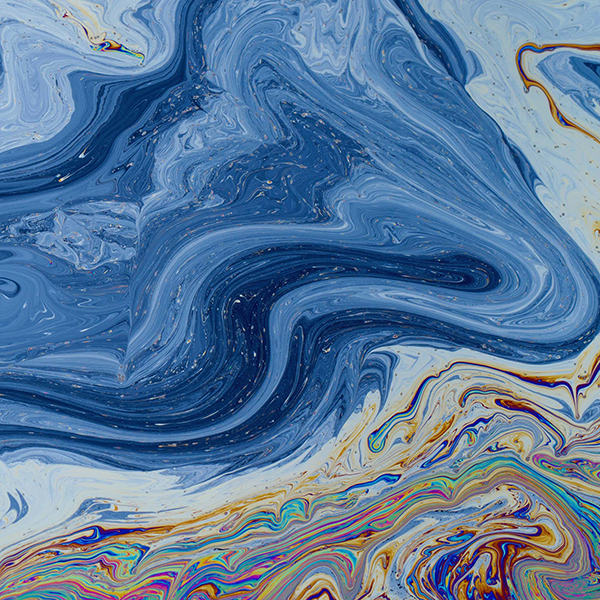
たった5週間程度で制作された『クラッシュ』について、フローティング・ポインツことサム・シェパードにインタヴューした際、彼はこう述べていた。「『エレーニア』を作ってから『クラッシュ』を作るまでに4年空いたんだ。その4年間で僕は多分『クラッシュ』を作るためのアイディアを作りあげていたんだと思う」。つまり『クラッシュ』は、4年間分のアイディアが5週間という短い期間を経てアウトプットされた作品ということになる。ヴァラエティに富んだ緻密さがパンキッシュな衝動によって磨き上げられた本作は、サム・シェパード自身が本作を原点回帰的と言っているように、フローティング・ポインツ初期のサウンドを思わせるダンサブルな快楽がブラッシュアップされた形で楽しめる一方で、“ファレーズ”や“レクイエム・フォー・CS70・アンド・ストリングス”でのポストクラシカルを連想させるシンセとストリングスのユニークな融合にも挑戦している。また、本作には“エンバイロメンツ”(環境)、“シー・ウォッチ”(地中海の難民を救助する非政府組織の名前)という楽曲があり、アルバム・タイトルも『クラッシュ』(破壊)であることから察せられるように、ポリティカルなムードが備わっていることも重要なポイントだ。つまり『クラッシュ』はフローティング・ポインツが混迷の時代を直視しながら踊り続けることを選び、そのうえで新たな一歩を踏み出した作品といえるのだ。(八木皓平)
listen: Spotify

ヘラヘラした笑顔で欠けた前歯をさらしながら、ガンギマリのハイテンションでラップしていた男は、もうこの世にはいない。歯を直して髪を小綺麗に整えた今のダニー・ブラウンは、躁と鬱の間を揺れ動きながらドラッグに固執していた以前の彼とは全く別人のようだ。まるでスタンダップ・コメディアンか名バイプレイヤーのような外見の変貌は、今作に抱く印象とそのまま直結している。前作『アトロシティ・エキシビション』で片腕的な役割を果たしたポール・ホワイトやフライング・ロータスらの参加はあるものの、全体の基調を決定づけているのはエグゼクティヴ・プロデューサーを務めたQ・ティップならではのサウンド・プロダクション。前作を特徴づけていたエレクトロニック・ミュージック的な尖鋭性、ナイン・インチ・ネイルズやジョイ・ディヴィジョン譲りの内省的な文学性は消え失せ、代わりに90年代ゴールデン・エイジを髣髴させるクラシカルなヒップホップが展開されていく。齢38にして、ようやく彼は足元に絡みつく「オールド」ダニー・ブラウンから解放され、「オールド」になっていく自分を受け入れたのだ。(青山晃大)
listen: Spotify

フォンテインズ・D.C.のグリアン・チャッテンは、くぐもった低い声で、なかばしゃべるように歌う。その歌い口に抑揚はなく、ほとんど詩の朗読に近い。憂うつやあきらめ、知性とちょっとした怒りが、おさえきれずに染みでた声と表情でチャッテンが聴き手に吹き付けるのは、ダブリンの路上、いや、地べたから舞い上がる、乾いた埃をはらんだ詞である。「ラジオはひたすら失踪中のモデルについてしゃべっている/罪みたいな顔と、ジェイムズ・ジョイスの小説みたいな心を持った」「あんたがロックスターでも、ポルノスターでも、スーパスターでもかまわない/いい車を手に入れたら、どっかへ行ってくれ」「タクシードライバーは二つの銃身に装填するための名前を持っている/彼は『英国人どもめ、出て行け!』と吐き捨て、ただキャロルズ(アイルランドの過激派ナショナリストが愛好する煙草)を吸っていた」(“ボーイズ・イン・ザ・ベター・ランド”)。「死は、あんたの仕事のルーティンにふりかかる/そして、あんたの教会と女王様には、さらに激しくふりかかる/借家のある風景にも激しくふりかかる」(“ザ・ロッツ”)。吟遊詩人の国で生まれたこの5人組は、アイルランド人らしく詩とロックンロールへの愛情によって結ばれている(グラストンベリーのライヴで彼らが引用していたのは、独立戦争で散った戦士たちに捧げたルーク・ケリーの詩だった)。その演奏は実にそっけなく、彼らが奏でるのは、まるでヴェルヴェット・アンダーグラウンドとテレヴィジョンとジョイ・ディヴィジョンが、いっしょに鳴っているかのように聞こえるロックンロールだ。やがて、不愛想でとげとげしい音の間隙とチャッテンののっぺりとした歌のなかから、心をつかんで離さないメロディが立ち現れる。しかたがない。わたしがきらいな言葉を彼らにあげよう。“ボーイズ・イン・ザ・ベター・ランド”は、“リバティ・ベル”は、“ハリケーン・ラフター”は、“チェックレス・レックレス”は、まちがいなく2019年に生まれた新たなロック・アンセムである。(天野龍太郎)
listen: Spotify

新世代の台頭とローカル・シーンの充実は正比例する。サウス・ロンドン然り、アイルランドのダブリンやデンマークのコペンハーゲンはその近年における好例だ。ただし、ご存知アデルやキング・クルールを輩出した名門ブリット・スクール出身のかれらは、そうした地元の連れ合い同士の「バンド物語」とは無縁に等しい。いうなれば、音楽を生業とするため養成されたエリート予備軍。いわく、飽くなきインプロヴィゼーションの演習を通じて鍛え上げられたプレイヤビリティとソングライティングの成果が、今年のマーキュリー・プライズにもノミネートされたこのデビュー・アルバムだ。サヴェージズやアイドルズを起点とした2010年代の英国ポストパンクの先端にも位置づけられるそのサウンドは、しかし、数多のジャンルと紐付けされる情報過多で過密な代物。プログレッシヴでノイジー、かつファストでミニマル。一気呵成で手数に富み、荒削りだがコントロールされた演奏は、若干20歳前後とは思えぬほど――いや、チャーチ・ミュージックに従事した経験やUKジャズのコミュニティとも繋がるバックグラウンドが物語るように熟(な)れている。そして、それがギター、ベース、ドラムといういたって古典的なロック・バンドのフォーマットで実演されている事実。本作とかれらのブレイクには様々な示唆と可能性を見出すことができるのではないか。加えて、本作をはじめフォンテインズ・DCやブラック・カントリー・ニュー・ロードなどこの界隈の作品を手がける今年のキーマンとして、プロデューサーのダン・キャリーの名前もぜひ記憶に留めておかれたい。(天井潤之介)
listen: Spotify

デビュー以来、自らが先頭に立ってラップ、ロック、ポップの壁をすべてなぎ倒してジャンルレスの時代をもたらした後に、その未墾の地で、誰の顔色も気にせず着の身着のままリラックスして作り上げたアルバム。まあ、そうなると想像以上にトラディショナルなシンガーソングライター色が強く出るのね、というのは発見ではあったものの、24歳というキャリア的にも「ここからまだどこにでも行ける」という正解を引き出してみせた文句なしの3rdアルバム。昨年のドレイク『スコーピオン』同様に勝ちすぎたアーティストの勝ちすぎた作品へのクリティックの無風ぶりや音楽ファンの風当たりの強さはいつものことだし、本作がここまで独り勝ちしてしまったことが2019年の音楽シーンの停滞感を証明しているのは事実だが、それはポスト・マローンが悪いのではなくそれ以外が悪いのだ。それと、(これはジャスティン・ビーバーやドレイクやカリードにも言えることだが)「声の力」の前では、音楽的イノベーションだとか政治的多様性だとかが、いかに微力であるかもわかる。いつだってシーンを制してきたのは時代を味方にした「声の力」で、その力を完全に手中に収めたポスト・マローンの天下はまだ当分続くだろう。(宇野維正)
listen: Spotify

わずか3ヵ月の間にリリースされた『サチュレーション』三部作で名を上げ、メジャー契約後初のアルバム『イリデセンス』で全米1位に。飛ぶ鳥を落とす勢いだったはずのブロックハンプトンによる最新作は、こんな言葉から始まる――「どこに向かっているのか、私には分からない」。結成当初からの中心メンバーだったアミアー・ヴァンの裏切りと解雇、本人達のキャパを超えて急激に膨れ上がる期待といったトラウマに満ちた時期を乗り越えるために、彼らは6ヵ月間の活動休止と、結成以来ずっと続けてきた「ブロックハンプトン・ファクトリー」での同居生活の解消を選んだ。そんな決断から生まれた成果が、この『ジンジャー』だ。総勢13名の大所帯にも関わらず、本作はとてもパーソナルで切実なトーンで貫かれている。メンバーそれぞれが直面した混乱や失意を浄化するように、後半に進むにつれゴスペル譲りの救済の感覚が立ち上り、ブロックハンプトンの行く末にかすかな光を灯していく。えてして、コミューナルな夢と理想は成功と反比例に亀裂を生み、瓦解の末路へと向かうものだが、ブロックハンプトンはそんな苦難の時期を奇跡的に乗り越えてみせた。(青山晃大)
listen: Spotify

2019年に注目された「ビリー」は、実は二人いる! 例えば〈タイム〉誌による年間ベスト・アルバムを見ると、6位はビリー・アイリッシュの『ホエン・ウィ・オール・フォール・アスリープ、ホエア・ドゥ・ウィ・ゴー?』。そして、その上の5位にランクされたのが本作で、カニバル・オックスのヴォーダル・ヴェガに最初にフックアップされたNYのラッパー、ビリー・ウッズが、プロジェクト・ブロウドやロウ・エンド・セオリーに関わってきたLA拠点のプロデューサー、ケニー・シーゲルと組んでいるのだ。パブリック・エネミーでヒップホップに目覚めたというビリーは、リスナーに何かを強く訴えかけているようなフロウの持ち主だが、「メッセージ」を発したりはしない。「人類学者たちはニグロがヤクを売るのを見守っている」とか、「ディス・イズ・アメリカ 胃腸の弱い方はお断り、ドナルド・グローヴァーを待っている、ダコタ・ハウスの外で」などと、ハイコンテクストが常識。「時々物事がわかりやすくなりすぎていると思うけど、自分の作品は今なお『複雑化』されたままだ。自分が心がけているのはもっと明確にすること、これみよがしに示すことなく」とビリー・ウッズは発言している。各種年間ベストのどこかにはランクされている作品なのに、あの〈ジーニアス〉でもリリック解読が進んでいない理由もわかる発言だ。それでも(それだから?)本作を何度も聴いてしまうのは、シーゲルのビートがあってのこと。エレベーター・ミュージックのように慎ましやかなトラックとビリーの押しの一手のフロウのミスマッチだとか、サンプルされた断片の任意のポイントだけ微妙にピッチをかえてループさせることで、ビリーのフロウに妙な形で楔を打つような効果等々……後から出た本作のインスト・アルバムにも手が伸びてしまう。(小林雅明)
listen: Spotify

カニエのくせに、いや、カニエだから、結構慎重なのか。本作以前に発表される予定だった『ヤンディ』収録予定曲(で無断リーク済みの)“Selah”がトラックリストにあるのを見て、これをそのままゴスペル・アルバムに入れるのは無理だと思ったら、言葉を差し替えていたが、結果的に、カニエ自身の私生活や私情をリリックに織り込むことは、本作全体を通じてほぼやめている。実際、その残骸とおぼしきパートは、カニエの信仰心を疑う者が突っ込みやすい表現だと言える。と同時に、突っ込まれてこそ、カニエらしいのも確かだ。ちなみに、今現在、クリスチャン・ラッパーで名実ともにNo.1のルクレイなどは、極私的な体験から絶妙な表現を通じて聖書の一節をイメージさせるだけでなく、2年前のアルバムでは製作陣にメトロ・ブーミンやDJダーヒー等を招き、その翌年にはゼイトーベンとのコラボ作を出している。それをふまえて言うなら、カニエなら(ピエール・ボーンを起用してはいるが)サウンド的に、名曲“ファザー・ストレッチ・マイ・ハンズ”(シリーズ)の縮小版的なもの(収録曲はどれも短いし、続編的内容の曲もある)からもう少し外に踏み出せたのではないだろうか。カニエが、音作りの上で一貫して「人の声」に興味を示し、既に2作目のアルバムの4、5曲で、モチーフとしてのクワイアを意識していたことを思い返せば、なおのこと。ただ、こうして表現スタイル全般に関して、カニエのくせに、やや腰が引けたような状態にあることから、逆にはっきりするのは、現時点でのカニエ自身の信仰の篤さだ。収録曲中で、本作に最初に否定的な反応を示したのはクリスチャンだった、とも漏らす本作において、彼はリスナーに信仰を持つよう呼びかけることなく、自分自身の言葉を使って、自分が神を崇拝し、対話し、嘆願する姿を見せている。(小林雅明)
listen: Spotify

“ノット”を聞いたとき、ニール・ヤング&クレイジー・ホースだ、と思った。「It's not the room / Not beginning / Not the crowd / Not winning...」。エイドリアン・レンカーは、ぶっきらぼうにかき鳴らされるファズ・ギターと、ごつごつとしたロックンロール・ビートを背に、否定の言葉を連ねる。歌声は次第にこわばっていき、彼女は喉をふるわせる。フィオナ・アップルやPJ・ハーヴェイを思わせる発声。それは、怒りともかなしみともとれるようなエモーションが込められた、振り絞った歌へと変わっていく。まるで、血反吐をはいているかのようだ。ありあまる創作意欲から2019年に二つのアルバムを発表したブルックリンの4人組がいうには、先行した『U.F.O.F.』が「天(celestial)」であるなら、こちらの『トゥー・ハンズ』のほうは「地(mud)」なのだという。ゆえに、アコースティック・ギターやウィスパー・ボイスを繊細に重ね合わせいたアンプラグドかつ幻想的な前作とくらべ、『トゥー・ハンズ』が聞かせるのは、プラグドで、向こう見ずで、血の通ったラフなアンサンブル。それにしても、ソロの歌い手としても称賛を浴びるレンカーは、どうしてバンドにこだわり続けるのだろうか。ささくれだった“フォガットゥン・アイズ”を聞いてみよう。「忘れられた瞳は、わたしたちがうしなったもの/忘れられた手は、わたしたちが選んだもの」「その傷は、どこへも行けない/だれもが家を求めていて、守られるに値する」。ビッグ・シーフの4人はその身体でもって、「忘れられ」かねないロック・バンドのアンサンブル、その可能性しかないよろこびとなまなましい傷とを、今一度聞き手に届けようとしている。そこにこそ、彼女たちがバンドである意味が宿っているのであり、『トゥー・ハンズ』はそれを力強く証明するレコードである。(天野龍太郎)
listen: Spotify

1990年代を生きた世代が犯した間違いがあるとして、「アンダーグラウンド」や「セルアウト」といった言葉で安心しきって、動き続ける世界を仕留めたつもりになっていたこと。カルチャーは静止したままのモノではない。一方、2020年代のポップを作るドジャ・キャットや彼女の同僚たちにとって世界は動き続けていくもの――それが彼女の作品に於いても意図的に反映され展開されてきたのは、2018年のヴァイラル・ヒット“モー!”だけ見た人はともかく、その前の“ゴー・トゥ・タウン”を聞いた人は直感出来たはず。本作でもアイズレー・ブラザーズの“ビトウィーン・ザ・シーツ”をサンプリング、グッチ・メインをフィーチャーした“ライク・ザット”に、1970年代のディスコ・クラシック、シックの“グッド・タイムス”まで遡れる“セイ・ソー”など、ヴォキャブラリーは大胆に狙って選ばれていることが伝わってくる。ドジャ・キャットはその日の服を纏うように様式を変える――また技術も確かで、“ルールス”では彼女はそのことを利用し比較的ハードに迫る。南アフリカの俳優とユダヤ系の母親の子供だそうで、影響を受けたのはジャミロクワイ、ファレル、エリカ・バドゥなどなど、そういえば“ボトム・ビッチ”ではブリンク・182もサンプリングしている。つまり、このアルバムを聞いていると90年代リヴァイバルが来るような気がするけど、それは早計というものか。(荏開津広)
listen: Spotify
