
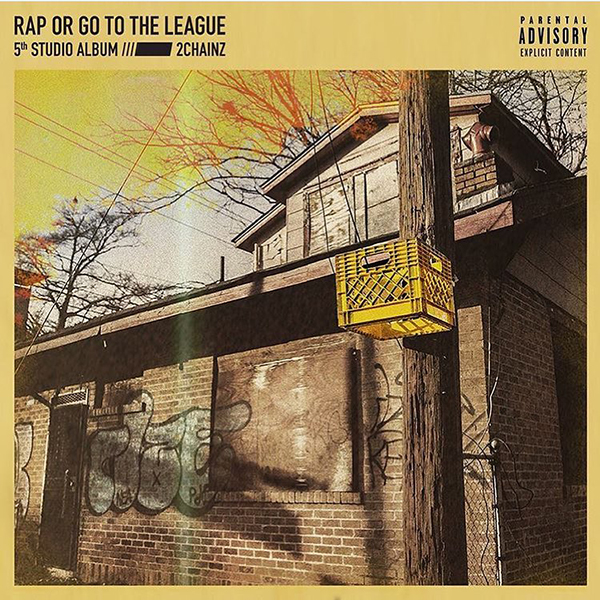
2019年屈指のヒップホップ・アルバム。つまり、緻密なストーリーテリングによる自伝性の強い作品にして、レコーディングにたっぷり時間と手間がかけられた作品。さらには、アリアナ・グランデとの一悶着を素早く回収するという時事性もあったわけだが、リリース時期が早かった(3月1日)せいか、シングル・ヒットがなかったせいか、そもそもこういうカッチリしたアルバム作品自体が時代遅れなのか、この年末に海外の主要メディアからあまり顧みられていないのが少々不憫だ。トラップ・ミュージックの象徴を長年担ってきた2・チェインズだが、本作のビートの基調を成しているのは9th・ワンダー(“スレット・2・ソサエティ”に参加)的なクラシックR&Bのサンプリング。内省的なリリックの内容とあいまって、その地に足のついた変遷はサウスのベテラン・ラッパーのキャリアの重ね方として非常にロジカルなもので、本作に参加しているヤング・サグやトラヴィス・スコットにとっても一つのロールモデルを示してみせた作品と言える。(宇野維正)
listen: Spotify

全英1位獲得作『ラヴ&ヘイト』がリリースされた2016年以降、マイケル・キワヌカの楽曲を映像作品の中で聴くことが爆発的に増えた。『ビッグ・リトル・ライズ』に『ゲット・ダウン』、『アトランタ』等々……、多くのヒット作で彼の音楽が印象的に使用されている。アメリカの映像監督たちがこぞって彼を起用する理由は、アイデンティティの模索という現代的なモチーフを、時代に左右されないタイムレスな響きへと昇華しているからに違いない。そんなキワヌカが、自己を肯定し祝福する作品を2019年に発表した事実は、重要なメルクマールと言っていいだろう。“ブラック・マン・イン・ホワイト・ワールド”に代表される寄る辺ない世界の漂流を経て、彼が見出したのは、自らの出自に対する誇りと自信。ウガンダ系イギリス人という血筋だったからこそ、彼はあらゆる歴史の中から学び、特定のシーンに縛られることのないユニヴァーサルなメッセージへと辿り着いた。今、彼のファミリー・ツリーには、古今東西の錚々たるソウル・ジャイアントが名を連ねている。(青山晃大)
listen: Spotify

80’sリヴァイヴァルを、はつらつとしたガール・ポップに落とし込んでいた『エモーション』(2015年)と比べると、『デディケイテッド』でのカーリー・レイ・ジェプセンはセクシュアルで、どこか蠱惑的な表情を浮かべている。「わたしみたいなドラッグ、試したことないでしょう/恋に落ちたって思えたら/わたしはあなたのために花開く」。ねばっこいエレクトロ・ファンクの“ノー・ドラッグ・ライク・ミー”で、彼女はそう歌う。キャプテン・カッツからプッシュ・プレイのCJ・バラン、ジョン・ヒル、ロジェ・チャヘイド、ジャック・アントノフまで、多数の売れっ子プロデューサー/ソングライターが手を貸したダンス・ポップ・レコード、といえども、BPM 100前後のビートとベースラインが腰に直撃するグルーヴは、アルバムを貫くスタイルとなっている(だからこそ、“ナウ・ザット・アイ・ファインド・ユー”は浮いてしまっているようにも感じる)。『デディケイテッド』をしめくくる“パーティ・フォー・ワン”は、おそらくこのディケイドをとおしてつよい影響力をもった、ロビンの“ダンシング・オン・マイ・オウン”へのオマージュだろう。クィアであることを肯定したと解釈されることで、結果的にLGBTQに力を与えるフロア・バンガーとなった“ダンシング・オン・マイ・オウン”と、カーリーの“パーティ・フォー・ワン”はよく似ている。「ひとりのためのパーティ/あなたがわたしのことを気にかけなくたって/わたしはただじぶんのためだけに踊る/わたしのビートで」(“パーティ・フォー・ワン”)。「孤」であることの肯定することは「個」であることの肯定であり、それは、「他」と同じでなくてはならない、という同調圧力をはねのけ、クィアでいるための力となる。“ダンシング・オン・マイ・オウン”から9年後の今、それより一歩踏み込んで、カーリーが“バック・オン・マイ・ビート(わたしのビートで)”と歌ったことには、すくなからぬ意味がある。(天野龍太郎)
listen: Spotify

R&Bを軸に様々なジャンルに自由にアプローチするライヴ感のあるサウンドで2019年注目のSAULTのメンバー(?)でもあるプロデューサーのインフローとのコラボを重ね、このアルバムの端から端までのスペースにきれいに収めることができたのは、リトル・シムズ自身の内側から涌き出た様々な思いだ。それは、音楽業界での活動継続に求められる心意気から、銃を所持したがる若者を取り巻く問題の深刻さ、自分の娘世代へのエンパワメントの積極性までいろいろだ。1曲目から堂々とセルフボースティングをかまし、それに導かれて前半の流れは、外連味溢れるというよりは、きっぷのよさが魅力だ。そして、折り返し地点にあたる6曲目以降、主題は自身が抱える傷つきやすさや脆弱性に転じてゆくとはいえ、自分自身を変に客観視するようなポーズは見せない。いろんな自分を吐き出し、その最後の最後に示される「グレイ・エリア」(表題)とは、(25歳の)彼女の中に潜む可能性や未知数な部分であると(有名音楽アーティスト27歳死亡説の影の部分も示しながら)リスナーに、しかと感じさせてくれる。アルバムとしては通算3作目にあたるが、あらためて立体的なリトル・シムズ像を立ち上がらせている。(小林雅明)
listen: Spotify
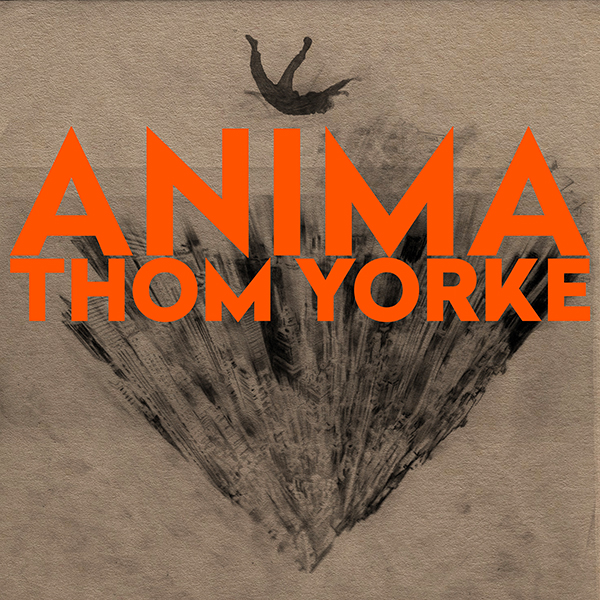
トム・ヨークは3作目のソロ・アルバムで、初の傑作を物にした。前2作のプリミティブなプログラミングや実験性からは「レディオヘッドではできないことをやる」というフロントマンのソロ作らしい気概や浮かれが感じられたものだが、同時にそれは拙さや散漫さにもつながっていた部分は否めない。しかし、本作においてはそうした「デモっぽさ」は払拭され、トムの歌声はエレクトロニック・ビートに対するカラオケ的な「浮き」を解消し、見事に一つの楽曲、一つのアルバムとして渾然一体となることに成功しているのだ。では、何が本作をこれまでと違う作品としているのか? あえて一点だけにその理由を絞るなら、それは「レディオヘッドに限りなく接近したアルバム」だからだ。リリース前に「過去の膨大なアーカイヴ音源を素材としながらプロデューサーのナイジェル・ゴドリッチと共同作業した」という旨が宣言されていたが、本作には明確に『キッドA』以降のレディオヘッドの特定楽曲を想起させる、あるいは同じセッションから取られたと考えられるサウンドが散見されている。「夢を再び見ることができるドリーム・カメラを開発した」というティーザー広告、本作に合わせて製作されたポール・トーマス・アンダーソン監督による短編映画『ANIMA』からも、アルバム・タイトル通りにユング的な無意識へのアプローチが本作の大きなテーマとなっていることは間違いない。そうした「集合的無意識」は、従来のレディオヘッド作品にも見られたトム・ヨークらしい主題だが、よりファンタジックな「夢」という形をとったことが、本作の象徴と言えるだろう。夢を「既視感の連続が見せる新たな景色」とするならば、本作のテーマとアプローチは見事に一貫している。ブリアルが自らの愛するゲーム『メタルギア・ソリッド』のサウンドを用いて闇にかすかに瞬く光のごときダブステップを描いたように、トム・ヨークはレディオヘッドと自らを素材にUKクラブ・サウンドという憧憬を形にし、「トム・ヨークの中にあるレディオヘッド」と「レディオヘッドの中にあるトム・ヨーク」というアニマたちをここに描いてみせた。それはロック・バンドという価値観が急速に解体されつつある時代において、一つの必然であり、大きなヒントともなることだろう。(照沼健太)
listen: Spotify

「ピンク」から「パンク」へ。1st『PINK』において、CHAIの4人は所謂「カワイイ」の価値観からはみ出す個性を「NEOカワイイ」と再定義してみせたが、彼らは続く本作『PUNK』で、そのメッセージのユニバーサルな同時代性を全世界に証明した。コンプレックスを逆に長所と捉え、ありのままの自分を肯定することは、CHAIにとって結成当初から変わらないコンセプトであり、そこにフェミニズムやルッキズムを巡る議論が盛んな現代に対する目配せはない。むしろ、世界の潮流がCHAIに追いついたという方が正しいのだろう。同様に、音楽的な面に関しても意識的に「洋楽的なるもの」へと接近する心づもりは全く感じられない。彼らの奔放なエクレクティシズムは、2000年代以降のインディ・ロックの多彩さを最大の参照点としつつも、多分に日本人的なポップ・センスでコーティングされている。世界言語となった「カワイイ」カルチャーが内包する欺瞞に世界が気付き、批判の声も高まった2019年。それでも旧態依然としたまま変わらない日本の価値観を揺るがすのは、声高な正論や頑なな否定ではなく、こんな風にユーモアたっぷりの言葉選びと、気の置けないダンスへのお誘いに違いない。(青山晃大)
listen: Spotify

2010年代後半は「抗不安の時代」だった。ザナックスとオピオイド系鎮痛薬が数々の才能にあふれた若いアーティストの命を奪った。先日もジュース・ワールドの訃報が届いたばかりだ。ラッパーだけじゃない。深刻化するメンタルヘルスの問題は社会全体の基調トーンとなった。そんな2019年に、その当事者として、最も美しくドラマティックに、それと対峙する過程を作品に昇華したのがデイヴのデビュー作『サイコドラマ』だ。現在21歳、南ロンドン生まれのラッパーであるデイヴ。彼の存在の前提には、2010年代のUKにおけるラップ・ミュージックの革新がある。ストームジーやJ・ハスが成し遂げたグライムやアフロバッシュメントの功績がある。それはたとえばマッシヴ・アタックが90年代に成し遂げたことの背後にポストパンクとソウルとダブの所産があったのと同じ。文化や音楽は川の流れと同じだ。ただ、そういう文脈を全部差し置いても、強いパワーが作品自体に宿っている。アルバムはコンセプト作で、セラピストとのセッションを模した構成。そこで彼自身の人生が語られていく。レイシズムについて、虐待と暴力について、殺人で終身刑に処された実兄について。鬱と疎外について。“ブラック”や“レスリー”を最初に聴いたとき、胸の深いところを握り潰されたような感覚があった。歌詞もちゃんと調べず、誰が歌ってるかすら知らない段階で、ピンときた。これは「生き延びるための音楽」だ。その勘は間違っていなかった。アルバムは今年のマーキュリー賞を受賞。UKにおける今年の最も優れた作品という評価を受けた。ただ、評価うんぬんよりも、きっとこの作品を本気で「必要としている」人は日本にも多くいるはずで、そこに届いていない現状はとても歯痒く悔しい。(柴那典)
listen: Spotify

収録時間は、全15曲約25分だった前作『サム・ラップ・ソングス』から全7曲で16分以下へ。本作の内容について「断末魔の叫び声をあげ崩壊しつつある帝国に取り囲まれた状態での理想」と彼は説明している。そこには、ある種の諦めや(平行世界への)現実逃避?も含まれているのか、アールが1曲手がけたデビュー作『レット・ザ・サン・トーク』も聴き逃せないマヴィが1stヴァースをバッチリ担当した“エル・トロ・コンボ・ミール”(制作はイースト・オークランドの新鋭プロデューサー/ラッパーのオーヴァーキャスト)では「箱にしまう自分の恐怖心、それはまるで読まれることのない願い事/まるごとすべてを『千と千尋の神隠し』」と出てくる。こうして若手をフックアップしてはいるが、前作にあった共同作業のケミストリー云々はなく、その時に得た感覚を活かし、ほとんどが一筆書きのようなリリックよりも、サンプル素材をチョップしまくったり、楽曲の構造を通じて「混沌」を伝えている。1曲で本作全体の3分の1近くの長さを占め、ラップよりもベース(ライン)の逆回転再生ループを長く聴くことになるマクホミー客演曲では、銃の話を持ち出し、アールとしては久々に暴力の匂いを漂わせている。喪失感を取り上げている曲の表題が“イースト”なのと、アルケミスト作のビートがアコーディオンとアラブ(中近“東”)ポップスのストリングスのサンプルを噛み合わせたものであるのは何か関係があるのだろうか。(小林雅明)
listen: Spotify

(本作全体の基調でもある)哀しげなピアノの音色で始まり、日曜から土曜までストリートに立つ売人(=自分自身)の心の動きを素直にリリックに託した“ファイナー・シングス”が、2018年夏にラップ・リスナーの耳目を集めた、シカゴはノースサイドのプロジェクト育ちの20歳のメジャーからのデビュー作。シカゴのストリートからの視点或いはストリートに対する見方は、特にドリル・ムーヴメント以降様々な角度から表現されてきた。ポロ・Gは、同じシカゴではG・ハーボほどはストーリーテリングに傾いてはいないものの、彼からさらに派生したラッパーのようにも聴こえる。例えば、ポロ・Gと同じように服役経験があったりすると、ツッパった態度を見せてくる者も少なくない(実際、本作収録曲のなかでは、ツッパった部類に入る“ポップ・アウト”が全米最高11位のポップ・ヒットを記録)。だが、ストリートに愛でられたがゆえにいつまでも拭い去ることのできない魂の不安を歌った“ディープ・ワウンズ”や、「保釈された時、俺を迎えに来てくれたのは母親ただ一人だった」という“ラスト・ストライク”などを聴いていると、軽めの声だし力んだところもないので容易に結びつかないかもしれないが、「ブルーズ」に通じる部分が彼の音楽の大きな特徴なのではないだろうか。(小林雅明)
listen: Spotify

ソウル、インディ・ロック、ジャズ等のジャンルをシームレスに横断するソングライティングと、エレクトリック・ギター弾き語りを主軸にしたミニマルかつアンニュイなサウンド。西ロンドンという出自も手伝って、これまでThe xxやキング・クルールの後を追う存在とも目されていたニルファー・ヤンヤ。彼女のデビュー・アルバムは、ロンドンっ子らしい印象の強かった以前の姿から大きく発展を遂げた作品となった。冒頭、健康を自動管理する架空のプログラム「WWAY HEALTH=We Worry About Your Health」のヴォイス・メッセージから続く“イン・ユア・ヘッド”で、分厚く鳴り響くギター・リフ。本作の前半に顕著となっているロック然としたアグレッシヴさは、これまでの内省的なイメージを覆すには十分で、海の向こうのシンガーソングライター=セイント・ヴィンセントやミツキの面影もちらつく。ただ、アルバム全体を通した「WWAY HEALTH」のインタールードが演出するディストピアンな物語性には、風刺的なブリティッシュ・ユーモアのセンスもしっかりと感じられる。そう考えると『ミス・ユニヴァース』というタイトルだって、彼女の志したポジションを象徴しつつ、ピリっとした皮肉が効いている。(青山晃大)
listen: Spotify
▼
▼
2019年 年間ベスト・アルバム
21位~30位
2019年 年間ベスト・アルバム
41位~50位
2019年 年間ベスト・アルバム
扉ページ
