

愛されキャラのダベイビー。正直に言って、一発屋で終わると思っていた。しかし、そんな予想は外れて、ダベイビーは2020年の最大のスターの一人になった。ロディ・リッチとの“ロックスター”。この『ブレイム・イット・オン・ベイビー』からの、2020年の大ヒット・ソングである。「新品のランボルギーニ、パトカーはファック/ピストルをぶら提げて警察官みたいだろ/リアルなロックスターに会ったことがあるか?/これはギターじゃないぜ、グロックだ」。威勢はいいものの、ダベイビーは“ロックスター”のヴァースの後半で、娘の眼前で正当防衛のために19歳の若者を射殺したことによるPTSDを告白する。彼はその後、この曲の「ブラック・ライヴズ・マター・リミックス」を発表した。「俺は家に帰るための道を探している、壊れたハートを持った男だ」と歌う“ファインド・マ・ウェイ”にも表れているように、『ブレイム・イット・オン・ベイビー』には暗い影が落ちている。金太郎飴のようにマンネリなフロウを揶揄されがちなダベイビーだが、ラッパーとして成熟していく姿がここにはあるように思える。11月には自死によってこの世を去った兄グレン・ジョンソンに捧げた『マイ・ブラザーズ・キーパー(ロング・リヴ・G)』をリリース。「俺たちは悪魔と闘っている、みんな乗り越えようとしているんだ」(“ブラザーズ・キーパー”)。そうラップするダベイビーは、これまでになくシリアスな面差しだ。(天野龍太郎)
listen: Spotify

ポロ・Gが育ったマーシャル・フィールド・ガーデン・アパートメンツというプロジェクト(公営団地)は、シカゴ北部のオールド・タウンにあるそうだ。ドリルが生まれて育まれたのは南側なので、ポロがハードなサウンドとスタイルを捨て去ってメロディアスなフロウでラップするようになったのには、北部出身ということもあるかもしれない(とはいえ、ポロは当然ギャングのメンバーでもある)。2019年、リル・ティージェイとの“ポップ・アウト”とアルバム『ダイ・ア・レジェンド』でシカゴのシーンからのし上がったポロ・Gは、この2ndアルバム『ザ・ゴート』でさらなる成功を勝ち得た。ビルボード200では2位を獲得。いよいよ名声を確立した、と言えるだろう。ポロ自身もこうラップする。「前のテープはクラシックだってやつらは言う / けど、もっとホットなアルバムをつくった」(“ゴー・ステューピッド”)。ちなみに、「GOAT」とは「Greatest Of All Time」の頭文字であり、また彼の星座である山羊座への言及でもある。「山羊座には偉大な人間が多い。レブロン・ジェイムズ、キング牧師、デンゼル・ワシントン、タイガー・ウッズ……」と彼は同じ星座の黒人たちを数え上げる。テイ・キースとマイク・ウィル・メイド・イットによるヘヴィなビートで、スタナ・4・ヴェガス、NLE・チョッパーとラップした“ゴー・ステューピッド”は、どこまでもハードだ。いっぽう“21”では若くして得た富を誇示しながら、ジュース・ワールドとの思い出を歌い、メランコリーに耽溺する。“ビューティフル・ペイン”のような感傷的で甘いラヴ・ソングがあり、他方に無慈悲なストリート・ライフと不安定な精神状態がある。それらのあいだの揺れ動きはマスタードとの“ハートレス”によく表れており、それこそがポロらしさと言えるだろう。(天野龍太郎)
listen: Spotify

切ない。胸が痛い。こんなはずじゃない。BLACKPINKのドキュメンタリー・フィルム『BLACKPINK ~ライトアップ・ザ・スカイ~』を観たときの感想だ。研究生として毎日数十時間のレッスンを何年も重ねて、戦友がリタイアしていく中を耐え続け、ようやく手にしたスターダムのチケット。そして、2016年以降の圧倒的な成功。そのスーパー・サクセスは、彼女たちに自由ではなく、さらなる不自由との闘いを強いる。大きすぎる変化、過酷なスケジュール、転落への不安。飽き飽きするほど繰り返される、ポップ・スターの悲劇。BLACKPINKも例外ではないことに、重苦しさを覚えて胸が痛む。それもまた一つの演出だけれど、4人の疲れ切った表情は割り切って考えられない。憧れにたどりついても、何もみつからない。“ラヴシック・ガールズ”のメランコリックなリリックを思い出す。「私たちは生まれて死ぬまでずっとひとり / だけどなんで愛を探しているの?」。手に入らないものだけを欲しがって引き裂かれる、永遠の愚かさ。それでも、“ハウ・ユー・ライク・ザット”の、トラップ・ビートに絡みつく妖しい半音階と、2分39秒以降、「BLACKPINK!」のかけ声から「ドゥンドゥンドゥンドゥドゥドゥン!!」と迫り来る張り手のようなフロウには、否定しがたいエナジーとユーモアと高揚感が宿っている。リサが自らの名前と「モナリザ」で韻を踏む“アイス・クリーム”の楽天的な歯切れの良さも、重たいキックがコーラス・パートで消える“クレイジー・オーヴァー・ユー”のたまらない浮遊感も、訓練された美と必要に迫られたサービス精神だけでは成り立っていない。芸能の悲惨で美しい伝統よりも、人類普遍の物語構造よりも、「愛らしい野蛮さ(Pretty Savage)」を信じること。BLACKPINKという選ばれた存在だから指し示せた、24分30秒の未来と今。(伏見瞬)
listen: Spotify
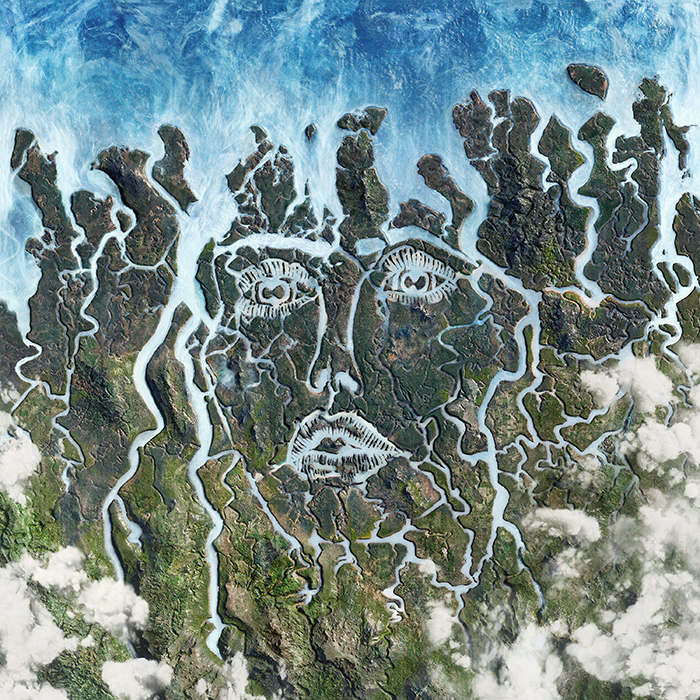
デビュー・アルバム以降ここ数年のディスクロージャーには、アンビヴァレントな気持ちを抱かずにはいられなかった。彼らが常にハイクオリティな楽曲をリリースし続けていたことに疑いはないが、「踊れないダンス・ミュージック」である彼らのデビュー・シングル“オフライン・デクスタリティ”に心を奪われた身としては、デビュー・アルバム以降ほとんどの楽曲があまりにウェルメイドで健康的すぎて、まるでレジャー体験のように感じられる違和感を否定できなかったからだ。しかし、2020年という未知の一年間と本作を通過したことで、それらの印象は一変してしまった。世界中が踊れない時代に、『エナジー』を謳うダンス・ミュージック・アルバムをリリースすることに対し、葛藤や恐怖がなかったというようなことはないだろう。『テネット』の公開をコロナ禍で強行して興行的に爆死したクリストファー・ノーランの気骨を重ねるのはローコンテクストすぎる? しかし、やはりこれも誰かがやらなくてはいけなかったことであるのは間違いない。「世界中をツアーできないならば」とYouTubeやTwitchなどの動画プラットフォームを駆使してDJプレイやビート・メイキング・チュートリアルを配信するその姿からは、彼らの「グッド・ガイ」感がいかにリアルなのかを思い知ることになったし、本作の特徴であるアフリカ音楽からの影響への返礼をアフリカの農業に貢献する慈善団体〈Just Digg It〉とのパートナーシップ締結で果たそうとするその筋の通し方には感服させられた。無数の若き才能が自殺やドラッグ、強盗などで命を落とし続ける昨今、そしてこの2020年において、彼らのような健全なマインドを腐すのは野暮でしかないだろう。タイトル・トラックにして先行シングルである“エナジー”に並ぶ驚きは残念ながら”マイ・ハイ”くらいしかアルバム中には無かったが、それは些細なことだ。(照沼健太)
listen: Spotify

音楽から一旦離れて精神分析を学んだことも影響したのか、ローラ・マーリングの7作目には一曲一曲、短編小説のような鋭さと余韻がある。大きくモチーフとなるのは苦しむ人へかける言葉とエンパシー。その人とはもちろん、彼女自身でもある。マヤ・アンジェロウの『娘への手紙』をヒントに、「想像上の娘に語りかける」というコンセプトが中心となって、娘(若い世代/若い頃の自分)と自分、母親という女たちの連なりが意識され、歌の中に時間の流れがあるのだ。「恋は時間で癒える病気」と、アビューシブな恋愛を歌う“オンリー・ザ・ストロング”。“ブロウ・バイ・ブロウ”では、「一番難しいのは、失ったものから何かを得ること」と率直に吐露する。タイトル・トラックの歌詞は「服を脱がせようとする連中が敷いた路線/退屈で禿げた年寄りのアドバイス」と、16歳で飛びこんだ音楽業界を振り返るようだ。グレアム・グリーンの『情事の終わり』を主人公ではなくサラの視点から語る“ジ・エンド・オブ・アフェア”も、彼女が失ったものを明らかにする。そんな物語が乗るピアノやギターのアコースティックなサウンドは素朴に聞こえるが、ボン・イヴェールのロブ・ムースらによってきめ細やかで、モダンなアレンジが施されている。シンプルかつ精緻。30歳になる前からオールド・ソウルと呼ばれ、ジョニ・ミッチェルやレナード・コーエンとも比べられるマーリングが、女性たちの苦しみ、悲しみの昇華にフォーカスした一作。(萩原麻理)
listen: Spotify

2019年、もっとも重要なラップ・ソングのひとつだった“フリー・ウージー”には、リル・ウージー・ヴァートがアルバムをリリースできない原因として指弾するDJドラマやジェネレーション・ナウとの対立が滲んでいた。実情はわからないが、ともあれ前作『ラヴ・イズ・レイジ2』から3年もかかって、『エターナル・アテイク』はようやくリリースされた。とはいえ、このアルバムはそんな事情を感じさせないほどにいきいきとしている。ビートの空隙に差し挟まれるアド・リブは確信に満ちているし、プロのスケーターやサーファーのような身のこなしで律動を乗りこなすさまは、一番調子がいい時のリル・ウェインを思わせる。『エターナル・アテイク』は3部構成になっている……らしい。それぞれ「Baby Pluto」、「Renji」、「Lil Uzi Vert」と、ウージーの3つのペルソナに対応している。投票を募ったカヴァー・アートの候補は3つ。正式に決まったアートワークでは、3つの人影(宇宙人?)が地球に向かうUFOを見送っている。3、3、3。三体問題が予測不可能であるように、ウージーが取りつかれている数字は混沌をもたらす。だからこそ、なのだろうか。アポカリプスと救済を説くヘヴンズ・ゲートへのオブセッションは、ネタなのかマジなのかわからない。ウージーはただひたすら、ひとりでライムしつづける。マネー、ビッチ、ドラッグ、パテック・フィリップ、コム・デ・ギャルソン、アレキサンダー・ワン、ヴェトモン、遊戯王、バレット・プルーフの車……。いっぽう「俺を崖っぷちに追いやってくれ」と歌った“XO・ツアー・ライフ”の続編である“P2”では、メランコリーに溺れている。「安らかに眠れ、死んだ仲間たちよ」。アルバムが憂鬱と混乱のままで終わらず、ボーナス・トラックに“フットサル・シャッフル・2000”と“ザット・ウェイ”が置かれているのは、せめてもの救いだ。(天野龍太郎)
listen: Spotify

2016年の『サヴェージ・モード』の続編となる本作だが、全9曲約32分に極めてヘヴィでダークな世界観を凝縮させた前作とは意匠的つながりはあまり見られない。その代わり本作を特徴づけているのは、モーガン・フリーマンが務めるナレーションや、シームレスな曲間、雄弁なピアノが織りなす「映画的」という印象だ。ここで綴られるのは、21サヴェージの近年の静動。アルバム序盤こそ「Pussy」の連呼とボースティングの嵐だが、次第にその心情が吐露され始める。2019年に米移民税関捜査局に拘束され(アトランタ出身ではなく)イギリス国籍であると暴かれたことについての言及もそのひとつ。そして終盤には自身の失恋についてと思われる内容のセンチメンタルかつ静かな怒りを湛えた楽曲が続く。その迫力は、序盤の「Pussy」連呼すらそこへの伏線かと思ってしまうほどだ。もしそれをSNSへの投稿で終わらせてしまえば、単なる釈明や恨み節で終わってしまったはずだが、21サヴェージとメトロ・ブーミンはこうしてそれらをハイクオリティなアルバムに仕立て上げた(ドレイクが客演しSZAとのゴシップを自ら振りまく“ミスター・ライト・ナウ”も象徴的だ)。そしてそれは、怒りや悲しみ、復讐心などの狂おしいほどの感情に取り憑かれながらも、より良い自分であろうとする態度の表明でもある。「その時々にできることは/宇宙の中で良いことを決意するくらい」とは小沢健二の復帰シングル“流動体について”の一節だが、本作で21サヴェージとメトロ・ブーミンが見せているのは「自分一人では無理でも、仲間の力を借りてでも、より良くあろうとしたい」という気骨。それこそが「サヴェージ・モード」なのだろう。(照沼健太)
listen: Spotify

『孔雀』のインタールードはほんとうにおもしろい。「一番大事なのは、粗チンでも、最悪インポでもいい、それでもイクことができる、感受性豊かなpussy」(“Interlude 1 (Island Girls)”)。「どうせ笑ってんだろ、そうやって私が怒ったり泣いたりしてるのを見て。自分の本性は誰にも見せずに安全な場所に隠しておいて。男ってマジそれ。しに(すごく)弱虫」(“Interlude 2 (Good Man)”)。ここには、Awichのアティテュードが表れている。歌とラップを、日本語と(米軍基地からもたらされた)英語を行き来しながら、Awichはここで自身の女性性に向き合っている。主題はそれだけではない。根を下ろす生活の土地――沖縄という、この国がマージナルな場所に押しやっている土地の物語を、そこに生きるひとりの女性(Island Girl)として、Awichは歌う。時にダーティに。時に抱擁感のある愛をもって。時に怒りをあらわにして。まちがいなくAwichのキャリアにおける最高傑作である『孔雀』は、べたついた感傷で溺れそうになった2020年のこの国に差し出された救命ボートのようなレコードだ(その点ではMoment Joonの『Passport & Garson』にも似ている、とも言える)。Awichは“DEIGO”で「愛しい島」に向けてラップする。「顔面すれすれ泳ぐ F-15」とともに育ったこと。「僕ら」は「プレコ」で「ごみを食べて育った」こと。そんなウチナーの歌に、ナイチャーはどのようにして向き合うべきか。(天野龍太郎)
listen: Spotify

フレディ・ギブスがプロデューサーのアルケミストとコラボ作を出すのは、これで二度目。ただし、前回は基本的にカレンシーも交えた三人による作品だったのと、ひたすらミックステープを出し続けているカレンシーのサウンドの基本型が、ここでアルケミストが聴かせるスタイル同様、サンプル主体のメロウなものであるため、規定路線の彼の曲にギブスが色を添えているように聴こえるきらいがあった。それが今回は完全に主役。アルケミストがまろやかな音色で全体に統一感を持たせた上で、ギブスはラップの主題とスタイルのヴァリエーションで聴かせる。ダブルタイムに忠実なフロウで押しまくる“ゴッド・イズ・パーフェクト”を2曲目に置き、そのアウトロでギル・スコットヘロンのしゃべりをサンプルした流れのまま、「革命とは大量虐殺か、ほら、おまえらによる処刑がテレビ中継されてゆく」とギルの名曲のタイトルをひねったフックを通じてBLMに合流する“スコッティ・ビーム”へと続く。その曲でリック・ロスを招ぶ一方、タイラー・ザ・クリエーターが登場する“サムシング・トゥ・ラップ・アバウトではデイヴィッド・T・ウォーカーの温もりのあるギターがループする。その中で「神が俺にクラックを売らせた、おかげで俺にはラップのネタがある」と過去と現在を繋げる「ギャングスタ・ギブス」としての健在ぶりも示し、同様の過去を共有するグリゼルダから二人が参加。(小林雅明)
listen: Spotify

以前からハードな幻覚剤の使用を公にし“トリガー・プロテクション・マントラ”という7分の瞑想のための音楽をリリースする一方で、直截な性器への言及をリリックに持ち込み「スローソン(クリップスで有名)からのビッチ」と自称する彼女の活動は、ストリートとカウンターカルチャー由来の精神世界をR&Bのサウンド文脈で結びつけようとするもの。このアルバムではアブ・ソウル、フューチャー、ナズ、またタイ・ダラー・サイン、ウィズ・カリファといったゲストを迎える一方で、彼女自身が経験したビッグ・ショーンとの別離というパーソナルかつ誰もが経験したであろう感情生活のドラマをサブジェクトに選び、前進的なR&Bアルバムとしてだけでなく幅広い層にアプローチしようとする。悲嘆の乗り越えは、曰く「We ain’t the same, I am moving different now I am in the midst of an ascension now」、魂の上昇だ。幾つかの米ポップ音楽ジャーナリズム評では「チルなだけ」などと云われているが、彼女自身のアイデンティティによる人種のステレオタイプをも利用しながら、商業主義の真ん中でそれまでバラバラに分かれていた人々を結びつけようとするパースペクティヴは興味深く、また個人的なプレイしっ放しのリスニング感想として単調さ(?)も気にならないとは記しておく。(荏開津広)
listen: Spotify
▼
▼
2020年 年間ベスト・アルバム
31位~40位
2020年 年間ベスト・アルバム
扉ページ
