

2020年の日本語ラップ最重要作。テーマとモチーフの当事者性もさることながら、構成の巧みさが、このアルバムの最大の凄みだと思う。関西国際空港の入国審査の場面から始まる“Kix / Limo”。自分の住所をフックにし「文句あんなら会いに来い」とラップする“IGUCHIDOU”と、その曲の最後に仕掛けられたスキット。韓国出身で大阪在住の移民ラッパーとして活動するモーメント・ジューンの出自がテーマやモチーフと不可分に結びついていて、A&R・マネージャーのシバさんや恋人のナターシャのような実名も登場する。ラッパーとして、リリシストとしての表現のリアルさへの覚悟がある。だからこそ、日本にも当然存在する人種差別の当事者としての問題提起の鋭さを受け取る人も多いと思う。それも何より本作の魅力なのだが、それを「メッセージ」ではなく一人称視点の「疑似体験」として構築するアルバムだ。特に白眉なのは“Losing My Love”以降の後半の展開。他者の手を払い、現実から目を背け、自分の中にいる「Garcon(=子供)」を引きずり出し、インナー・チャイルドとの対話を繰り広げる。ラストの“TENOHIRA”が決意表明としての響きとして意味を持つ。この先のシーンに2020年に撒かれた「種」としての意味合いを持つ一枚。(柴那典)
listen: Spotify

2020年に、質、量ともに充実した作品を出したアーティストとして真っ先に名前が浮かぶのが(複数の演奏者と制作に数年を費やし、結果的に今年発表された秀作)『メンジャー・オン・マックニコルス』を含め、実に4作ものアルバムを出したデトロイトの10年選手ボルディ・ジェイムスであり、ソロ2作に加え3名のラッパーと個別にコラボした3作をリリースしたビートメーカーのアルケミストである。こうした快進撃を予告するかのように2月に投下されたのが、この二人のコラボとなる本作だ。ハードボイルドな表情をしたボルディのラップは、ドラッグ・ディールにまつわるあれこれを淡々と物語り、どこから探してきたネタなのか、それを美麗すぎず、劇的になりすぎない絶妙な調合でサンプル&ループしたビートと合体し、警句のような表現や結構な皮肉で突き刺してくる。例えば、出産間近の妻の計画殺人を企てたNFL選手の姓を表題にした1曲目では、その事件を経て生き延びた息子と、18年後に出所した父親との関係を、人生の難局に重ねてみている。また、“サーフ&ターフ”で「誰も俺を撃たないが、俺はンンンを撃った、三回は」と、お惚けモードで新たな傑作ヴァースを生んだヴィンス・ステイプルズ、容疑者逃走の模様を伝える生中継音声でその曲と繋がる“スクレープ・ザ・ボウル”でかけあいに挑むベニー・ザ・ブッチャー等、客演者の起用も適材適所としか言いようがない。(小林雅明)
listen: Spotify

突き詰めると、これは家族とアイデンティティについてのアルバムなのだと、サワヤマは本作について語っている。新潟県で生まれたサワヤマは、5歳でロンドンに移住。白人社会のなかで日頃から無自覚な偏見に晒される一方、故郷の日本にも居場所を持たず、親との確執にも苛まれていた彼女は、そんなやり場のなさを音楽にぶつけたのだ。幼少期は日本人学校に通いながら宇多田ヒカルや椎名林檎を聴き、ティンバランドとネプチューンズが欧米のチャートを席巻していた頃に青春を過ごした彼女は、00年代のR&Bを主なバックボーンとしながら、そこにハウスやニューメタルの要素も配合。当時のメインストリーム・ロックが孕んでいたミソジニーも炙り出した本作は、サウンドだけでなく、その倫理観においても00年代ポップ/ロックを再定義してみせた。各主要メディアは『SAWAYAMA』を2020年イギリスの最重要作として評価。一方、〈マーキュリー・プライズ〉と〈ブリット・アワード〉はこのアルバムをノミネート対象外とした。25年をイギリスで過ごしてきたサワヤマは、ブリティッシュ・アーティストではないのか。ここではイギリスだけでなく、二重国籍が認められない日本の現状も問われている。(渡辺裕也)
listen: Spotify

ベニー・ザ・ブッチャーは、ニューヨーク州でも犯罪発生率が極めて高いバッファローのラッパーで、ウエストサイド・ガン率いるクルー、グリゼルダの一員。15年以上のキャリアがあり、作品数も多いが、これは通算2作目となるアルバム。1曲目から、ジェイ・Zの最初の2作同様、アル・パチーノ声のペイン・イン・ジ・アスに「OK! I'm reloaded」(映画『カリートの道』からの引用)の名文句を言わせ、ベニーはヤクの調達人に金額を提示される前に札束を積む、とラップ。本作の表題は「立証責任」(Burden of Proof)なので、ジェイ・Zの「合理的な疑い」(Reasonable Doubt)を想起してもおかしくないし、全収録曲の制作に携わったヒットボーイの手がけるサンプル主体のビートの趣味も、中盤以降の90年代の東海岸のコーク・ラップを知る人たちをも満足させるようなものだ。だが、ベニーのラップに関しては、型通りのセルフボーストよりも誠実さを素直に吐き出してゆくのが特徴的で、“フェイマス”では、ラッパーとして成功した今と比べても、初めて大口のコカインを取引した時ほど名声を勝ち得たと実感したことはないと、売人上がりのラッパーの紋切り型には全くとらわれていない。また、“トレード・イット・オール”で、亡き兄を取り戻せるなら全てを差し出すと訴えているのも、エモ・ラップを知る時代には耳に入りやすいのでは。(小林雅明)
listen: Spotify

激しい怒りに貫かれているレコードだ。ピンク・シーフは、この一枚でまちがいなくフィラデルフィアのムーア・マザーに並ぶアンダーグラウンドの顔になった。Bandcampのキャプションにはこう綴られている。「ブラックは神だ。(中略)混沌はあってしかるべき。あなたは怒っていい」。バーミンガムのピンク・シーフことリヴィングストン・マシューズはアンダーグラウンドにおける通例どおり、いくつかの名前を持っている。「iiye」、「ronee sage」、それにB・クール・エイドとクリプトナイトのメンバーでもある。ビリー・ウッズやアデ・ハキムと共演しており、ブルックリンのリヴ(Liv.e)の紹介者であり、またスラムズ([sLUms]。詳しくは2019年のベスト・アルバムのマイクについてのテキストを参照してほしい)ともつながっている。彼は2018年にも『エンスリー』という優れたヒップホップ・アルバムをリリースしているが、この『ネグロ』は、それとはまったく性格が異なる。ここにはハードコア・パンクがあり、むきだしのジャズがあり、黒人たちの声がある。それらはめちゃくちゃにつぎはぎされ、ぐしゃぐしゃに汚され、びりびりと歪んだ音で刻まれている。まずは“FK”を聞いてほしい。ピンク・シーフは3分のあいだ、ただただ「ファック!!!!!」と叫びつづける。なぜ、ピンク・シーフは「ファック」と言わなければいけないのか。それがわからないなら、針を上げてもらってかまわない。なお、このアルバムは4月8日に――ジョージ・フロイドが、あの横柄なデレク・ショーヴィンに無残なやりかたで殺される前に――リリースされている。そのことの重要性を、2020年も終わろうとする今、もう一度噛みしめる必要がある。(天野龍太郎)
listen: Spotify

明治時代のリリシスト兼批評家、Siki Masaokaは我が身に近づく死期を予感しながら、当時崇拝されていた紀貫之を指して「下手な歌詠み」と言い切ったが、Dos Monosの三人も下手な歌詠みに対する悪意を隠さない。だがしかし、ありきたりなDisrespectにもなびかない。彼らは「崇拝」の仕組みを見据え、そこからさらりと身をかわし、ラップ・ミュージックの仕切り直しを体現する。あらゆるしきたりを無視して、あらゆる知の蓄積を駆使して、今ここにある血なまぐさい景色を凝視する。その仕草が、彼らの悪意と覚悟の表明となる。『Dos Siki』の四曲において、キック以外のパーカッションは甲高い響きへ寄せられた。低音より高音を強調する音の配置はアール・スウェットシャツやジェイペグマフィアの近作を想起させるが、サンプリング・ループが次々押し寄せるDos Monosのサウンドはもっと情報過多でやかましい。この騒々しい春の祭典の中で、図太い神経を通過した骨太いフロウを、三匹の猿は盤に刻みつける。「ナシ・アスター」の一語で『ミッドサマー』の監督をコケにする荘氏itのアクセント強い低音、本とIQを捨てて音に酔えと誘惑するTai Tanの粘っこく伸びる母音、ブリジット・フォンテーヌの微笑みを待ち望むBotsuの壊れかけたラジオDJのようなハイトーン。三つの声はそれぞれのやり方で、訳もなく訪れては去る四季を季語なし野暮抜きで表現してみせる。そこに、「柿食えば鐘が鳴くなり」と詠った一二〇年前の若き俳人の残響を聞き取ることは、あながち誤りでもないだろう。(伏見瞬)
listen: Spotify

2018年のEP『ブラック・イン・ディープ・レッド』で音楽的に大きな飛躍を遂げたモーゼズ・サムニーは、続くこの『グレイ』でさらに広く、深い探求をおこなっている。というよりも、もともとの性向をより全面的に展開している。想像力のおもむくままに絵を描いているような、どこまでも広がっていく音の風景をまとめあげようともせずに、『グレイ』にはあらゆる音楽がそのままに、ごろりところがっている。抽象と具体とのあいだを行き来し、始点も終点もない不定形の音楽の広がり。それが『グレイ』の像である。パーソネルを見ると、数えきれないほどの音楽家たちが関わっている。『アロマンティシズム』(2017年)から引き続き参加している者も多いが、それはまるで、現代の音楽シーンの一角がそのまま現れているかのようだ。しかし、どれほどミュージシャンが参加しようと、サムニーの音楽の中心にあるのは彼の歌声である。自身で録り、幾重にも重ねたヴォーカルには、これまでどおり、いや、それ以上に深く、パーソナルな手触りがある。開け放たれた扉や窓を吹き抜ける風と人々の交通、それに対して、心理的な壁で守られ貫き通される頑なな個の表現。その二律は、『グレイ』においてシームレスに縫い合わされている。稀有な、まごうことなき傑作だと思う。(天野龍太郎)
listen: Spotify

2010年前後にシカゴで勃興したヒップホップの一形態であるドリルは、インターネットを経由してロンドンへと飛び火し、更にそこからアメリカに逆輸入される形でブルックリンでも火がついた。ブルックリン・ドリルをメインストリームへと押し上げる存在として期待されていたのは故ポップ・スモークだったわけだが、UKドリルの顔役は1stアルバム『エドナ』で全英1位を獲得したヘッディ・ワンだ。『エドナ』の僅か半年前にリリースされたこのミックステープは、ヘッディがUKドリルの代表格であると同時に、その限界を拡張する存在であることも証明している。如何にもUKドリルらしい“シャレイドス”のような曲がある一方で、“トールド”、“スモーク”、“ノウ・ミー”に感じれられるのはテクノやUKガラージが大音量で鳴り響くダンスフロアの息吹。プロデューサーのフレッド・アゲインがベルリンでベルクハイン(言わずと知れたテクノのメッカ)に通い詰め、帰国後に制作が始まったことの影響も大きいのだろう。だが、ここで何より強く想起されるのは、UKドリルの源流のひとつであるグライムがUKガラージの影響とは切っても切り離せないこと――つまり、イギリスならではのラップ・ミュージックとクラブ・カルチャーの強い結びつきだ。『エドナ』ではドレイクやフューチャーといった北米メインストリームの大物もゲストに迎えてグローバルなラップ・ゲームでの存在感を誇示しているのに対し、本作ではジェイミーxx、FKAツイッグス、サンファ、オクタヴィアン、スロウタイなど、ジャンルを問わずイギリス勢でゲストを固めているのも意識的だろう。本作はUKドリルの可能性を押し広げつつ、シカゴともブルックリンとも違うUKドリルのシグネチャーを強く刻んでもいるのだ。(小林祥晴)
listen: Spotify
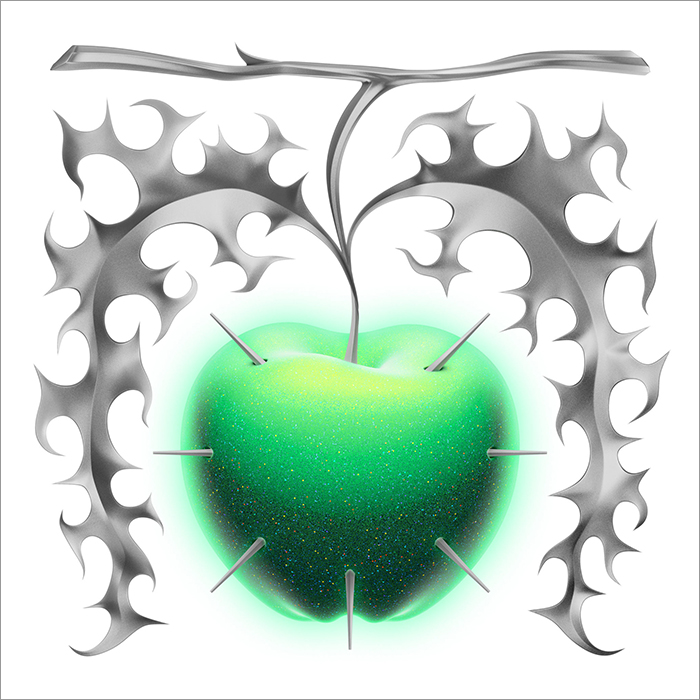
輝くシンセと、加工された声と、優しいギターと、凶悪なノイズと、キラキラと切ない旋律。それだけを摂取していたい、この強い至福の中にとにかく浸っていたいと感じさせる今年最高の「変性意識」アルバム。本当はそれで充分なのだけれど、いろいろ説明すると、まずA.G.クックは2020年のエレクトロニック・ミュージックの最重要人物の一人。彼が共同プロデュースを手掛けたチャーリー・XCX『ハウ・アイム・フィーリング・ナウ』はポップ・スターによるロックダウンに対しての誰よりも早い応答の一つだったし、2013年にレーベル〈PC・ミュージック〉を創立した彼は近年に勃興している「ハイパーポップ」のムーヴメントの生みの親でもあるわけだし、加えてシガー・ロスのヨンシーを10年ぶりの2ndアルバム『Shiver』で覚醒させたのも彼だ。こうして裏方として獅子奮迅の活躍をしてきた彼によるソロ名義でシンガーソングライターとしての表現に初めて取り組んだ作品が『7G』とこの『アップル』。リリースは『7G』が先だが、これは7部構成49曲収録という構成で自らの音楽性を7つの要素からリバースエンジニアリングした特殊なアルバムで、その1ヶ月後にリリースされた10曲入りの『アップル』がいわば「本命」という位置づけだ。かのように周辺情報と文脈が山ほどあるのだけど、そういうのは一度全部忘れて、10曲、10通りの「アトラクションとしてのサウンド・デザイン」の愉悦にひたるのが正解だと思う。(柴那典)
listen: Spotify

「僕らは“インディ・バンド”と呼ばれることに違和感がある。イギリス出身の4人の白人男性が集まったバンドだから、そう思われるのもわかるけど」。デビューから間もない2014年、バンドにインタヴューした際にマットがそう言っていたことを今も思い出す。当時この発言は「The 1975はインディではなく80年代ポップのようなサウンドを鳴らしている」ということ、そして「ジャンルを意識せずに音楽を聴く世代の一員として、同様に音楽を作っている」ことの表明でしかなかったはずだ。しかし、今となっては本作の予見めいた発言だったように思えてならない。本作は、オープニングを飾るグレタ・トゥーンベリのスピーチや、90年代インディ風、エモ、UKガラージ風ポップからアンビエントまで、無数のジャンルにまたがる22曲が収録されていることなどから、非常にハイコンテクストな作品として、その意図の推測や解釈について議論が盛んに行われているようだ。しかし、バンド最初のヒット曲“チョコレート”が収録された2013年作『ミュージック・フォー・カーズ EP』にあらためて耳を傾けてみてほしい。ポップ、アンビエント、ノイズ、ポスト・ダブステップなどそのサウンドは多岐に渡り、1曲ごとに歌モノとインストを行き来する本作と似ていることに気づくだろう。そもそも1作目となるアルバム『The 1975』だってそう遠くはない。むしろ2作目『I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It』こそがバンドにとっては異色作なのだ。この支離滅裂さ(あえてこう言おう)で一貫したバンドが「ポストU2」の座に足をかけている事実が何よりもエキサイティングであり、同時に、多くの人が見たいものしか見ていない、聴きたいものしか聴いていない現実を突きつけられる。本作が唐突な異色作であるかのような風潮や、Spotifyにおけるアルバム内楽曲再生回数の極端な格差がその象徴だ。(照沼健太)
listen: Spotify
▼
▼
2020年 年間ベスト・アルバム
21位~30位
2020年 年間ベスト・アルバム
41位~50位
2020年 年間ベスト・アルバム
扉ページ
