
先日ついにアナウンスされたスリーター・キニーの再結成と、新作のリリース。とうとう彼女たちのライヴを見ることが叶わなかった自分としては、それがようやく実現するかもしれないという喜びの反面、彼女たちがこれほどまで熱狂的に支持されていた本当の理由もわからなかったりするのだが、人気TV番組『ポートランディア』のホストとしてすっかりお茶の間の人気者となったキャリー・ブラウンスタインを筆頭に、クアージやスティーヴン・マルクマス&ザ・ジックスのドラマーとしてもおなじみのジャネット・ワイス、ソロとして来日も果たしたコリン・タッカーと、それぞれが活動の場を広げている今だからこそ、彼女たちを語るときに必ず付いて回ったフェミニズムやクィアコアといったタームを離れて、フラットにその音楽に向かい合うことができるのかもしれない。
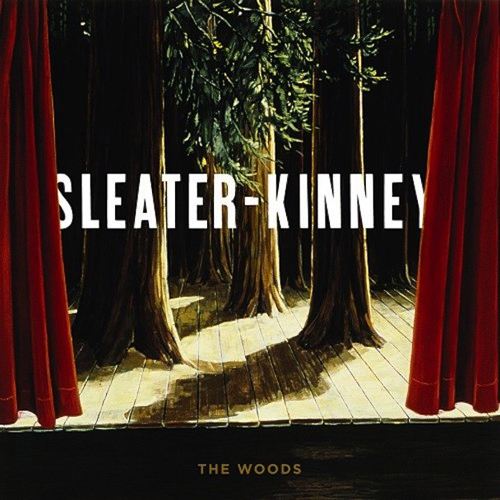
そんな自分が唯一リアルタイムで聴くことのできたスリーター・キニーのアルバムが、サブ・ポップ移籍第1弾にして、活動休止前のラスト・アルバムとなってしまった『ザ・ウッズ』だ。フレイミング・リップスやマーキュリー・レヴ、日本のナンバーガールなどを手掛け、当時超売れっ子だったプロデューサー、デイヴ・フリッドマンが携わっているのが興味を持ったきっかけだったのだが、往年のストーナー・ロックを思わせるようなヘヴィなサウンドに、メンバーの演奏、アルバムの構成、どれをとっても一級品で、本作をベストに挙げる人たちが多いのもうなずける。ヘヴィなだけではなく、キャリーがリードを取ったブルース/カントリー・タッチの愛らしい“モダン・ガール”のような曲があるのも、本作の魅力のひとつだろう。
しかし、この機会に改めて彼女たちのカタログを聴き返してみると、この作品はどうも異質というか、明らかに完成度が高過ぎるのだ。この作品を聴いた女の子たちが勇気づけられて、バンドを始めてみようという気持ちになるには、少々ハードルが高過ぎるというか、もしかしたら怖じ気づいてしまうのではないだろうか。
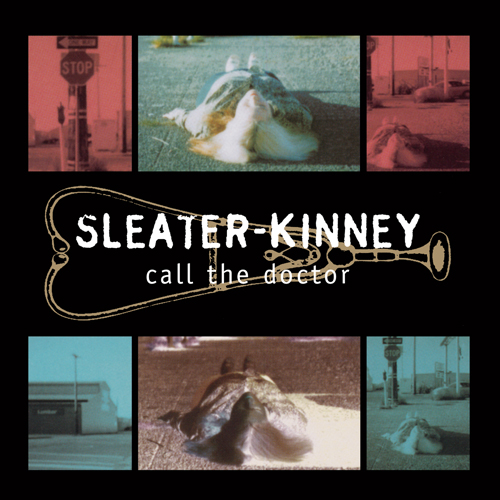
というわけで、スリーター・キニーにもこんな時代があった、という意味でオススメしたいのが、1996年にリリースされた2ndアルバム『コール・ザ・ドクター』だ。
スリーター・キニーのドラマーといえば3rdアルバムの『ディグ・ミー・アウト』から加入したジャネット・ワイスであり、それ以前にリリースされた本作を選ぶことは、もしかしたら邪道なのかもしれない。しかしこのアルバムにはそれを補って余りあるほどのテンションとヒリヒリとした緊張感が漂っていて、「あなたのジョーイ・ラモーンになりたい/わたしの写真をあなたのベッドルームのドアに貼るのよ」と歌うライオット・ガール賛歌“アイ・ワナ・ビー・ユア・ジョーイ・ラモーン”が収録されるなど、一般的なスリーター・キニーのイメージにもっとも近いのも、実はこの作品なのではないだろうか。
1stアルバム『スリーター・キニー』はコリンとキャリーのオーストラリア旅行の最後の夜にレコーディングされたそうだが、本作はオーストラリア出身の初代ドラマー、ローラ・マクファーレンが参加した最後の作品で、その後彼女たちの作品を数多く手掛けているプロデューサー、ジョン・グッドマンソンが携わった最初の作品という意味でも重要だ。個人的なお気に入りを挙げるとすれば、キャリーが歌うラストの“ハート・アタック”だろうか。ここではコリンがドラムを叩いてローラがギターを弾いているが、当時流行していたエモコアにも通じるサウンドで、張り裂けるようなスクリームが強烈だ。
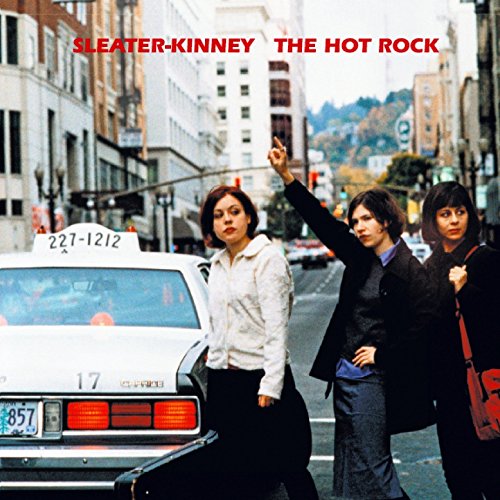
そんな自分がスリーター・キニーのベストに挙げたいのが、1999年にリリースされた『ザ・ホット・ロック』、正確に言えばそこに収録された“ゲット・アップ”という曲だ。オーストラリアのインディ・ポップ・バンド、ゴー・ビトウィーンズに触発されたという本作は、ジョン・グッドマンソンではなくヨ・ラ・テンゴの作品で知られるロジャー・マテノをプロデューサーに迎えた意欲作で、ヴァイオリンを配したスロー・テンポな“ザ・サイズ・オブ・アワ・ラヴ”からは、その影響が感じられるかもしれない。
このアルバムのリリース後に彼女たちは初のジャパン・ツアーを敢行(クラブ・スヌーザーにも出演)、本作収録曲を中心に演奏したそうなので、そういう意味で感慨深い人も多いことだろう。聞くところによれば、ジャパン・ツアーから帰ったその足でゴー・ビトウィーンズのサンフランシスコ公演に出掛けた彼女たちは、終演後に感極まってメンバーの楽屋に押し掛けたそうで、そのまま翌年リリースされたゴー・ビトウィーンズのアルバムにゲスト参加することになったという、なんとも乙女なエピソードも残されている。
そんな『ザ・ホット・ロック』からの1stシングルとなった“ゲット・アップ”のヴィデオは、彼女たちの友人でもあるミランダ・ジュライが撮影しているのだが、お互いを奮い立たせるようなコリンとキャリーの掛け合いヴォーカルをバックに、何もない草原に倒れ込んだメンバーたちが立ち上がり、何人もの女性たちと手を繋いで歩いていく……ただそれだけの映像に、こんなにも胸が熱くなるのはなぜなのだろう。ライオット・ガールの正統な後継者であるスリーター・キニーと、ガーリー・カルチャーの担い手となったミランダ・ジュライ。本作はその緩衝地帯で生まれた“Grrrly”な作品で、アルバムの1曲目を飾る“スタート・トゥギャザー”が先日リリースされたボックス・セットのタイトルになっていることからも、彼女たちにとって重要な作品だということが伺える。これからスリーター・キニーを聴くという人にも、迷わず薦めたい1枚だ。
「90年代半ば、最初のUSインディ全盛期の
落とし子、スリーター・キニー復活か?
今だからこそ聴きたい傑作アルバム3選。
その③:キュレーション by 坂本麻里子」
はこちら。
