
『東京』から20年。再結成から8年。時代が
一巡し、来たるべき新作に期待が高まる、
サニーデイ・サービス全作を振り返る 前編

明け方から昼間、そして夜からまた静かな朝へと曲中の情景描写が移り変わっていく本作は、いわば「目的のない気ままな列車の旅」をモチーフとした、ロード・ムーヴィのようなアルバムだ。そこで描かれるのは都会の街並みではなく、むしろそのはるか遠くにあるような、長閑で曇りがかった風景。ピンク・フロイドの『原始心母』を連想させるアートワークもさることながら、楽曲名に見られるニック・ドレイクやビートルズからの引用にも表れているように、その音楽的なリファレンスにおいても、本作はここまでの3作品とあきらかに一線を画している。田中貴の弾くメロトロンが印象的な3拍子のブリティッシュ・フォーク“枯れ葉”、サニーデイ屈指のハードな演奏がアルバムのクライマックスを見事に演出する“そして風は吹く”などを経て、全12曲の気ままな旅はいよいよ終着点へ。しかしそのエンディングは、結局どこにも行き着くことなく、再びアルバムの冒頭に戻っていくというものであった。少しずつだが着実に不穏なムードが漂いはじめていた当時の社会を前にして、サニーデイ・サービスは永遠に終わることのないまどろみの空間をここに作り上げたのだ。(渡辺裕也)
>>>『サニーデイ・サービス』収録曲
前作からわずか9ヶ月でリリースされ、勢いそのままにラフで荒々しい演奏を聴かせる、セルフ・タイトルの4thアルバム。前年に交流が芽生えたグラスゴーのギター・ポップ・バンド、トラッシュ・キャン・シナトラズからの影響もあったのだろうか、ピンク・フロイド『原子心母』の内ジャケそっくりなジャケット写真もイギリスで撮影されたもので、ローリング・ストーンズの“バック・ストリート・ガール”を思わせる“枯れ葉”、UKのインディ・バンド、シー・アーチンズにも同名曲が存在する“ワイルド・グラス・ピクチャー”など、アルバム前半にはブリティッシュ・フォーク風の冬枯れた楽曲が並んでいる。終盤に向けて盛り上がるのも本作の特徴で、夜の帳が下りるように始まる“PINK MOON”(タイトルはニック・ドレイクから)と“星を見たかい?”の2曲は、ライヴでも続けて演奏されることの多いサニーデイ屈指のメドレー。オープニングの“Baby Blue”とラストの“Bye Bye Blackbird”は対になっていて、“そして風が吹く”に登場する「黒い鳥が飛んで/蒼白い時になる」という歌詞でも、そのことが暗示されている。オリコン初登場7位を記録するなど、商業的にも音楽的にもひとつのピークを迎えた作品だが、今思えばそれはサニーデイの「始まりの終り」であり、「終りの始まり」でもあったのだ。(清水祐也)

最初の到達点となった『サニーデイ・サービス』の後に零れ落ちた、サニーデイ史上もっとも「壊れた」アルバム。CDの限界に近い72分に及ぶ本編に加え、10分超の8cmボーナス・ディスクをわざわざ追加したトータル82分は、様々な曲調が溢れ返ったかなりサイケデリックなものであり、例えば、森は生きているの『グッド・ナイト』にも通じるような、ギリギリの状態だからこそ生まれた高い熱量が感じられる。そんな本作の混沌は執拗なスタジオ・ワークから生まれたものであり、バンドのチャレンジを失敗も含めてスタジオごと真空パックしたような作風は、ビートルズのホワイト・アルバムやクラッシュの『サンディニスタ!』といった作品の系譜に位置すると言える。ただ、1998年という年はトータスが『TNT』を発表した「プロツールス元年」であり、これ以降は編集作業が画面上で簡単に行われるようになっていくことを考えると、本作は「スタジオ・ワークからDTMへ」という時代の節目を、『TNT』とは対になる形で示した作品だったと言うことも出来るかもしれない。曲単位で見てみると、ドラム・ループを組んだ“今日を生きよう”、強烈なファズ・サウンドの中で菊地成孔がテナー・サックスのソロを決める“ぼくは死ぬのさ”を筆頭に、アルバム全編で実験的な試みが繰り返されているが、特に秀逸なのが終盤の流れ。テープ・エコーを用いたり、逆回転のレコーディングを行ったりと、ダビーかつ長尺の曲が並び、フィッシュマンズに対するサニーデイなりの回答のようにも思えるし、Windows 98の年に「いろんな場所でみんな星に祈り/いろんな場所でみんな愛し合う」と歌った“24時のブルース”は、一足早いインターネット賛歌のようだ。ともかく、アルバムとしては混乱を極めながらも、聴き進めるに連れて心地の良いインナー・トリップへと導かれる本作は、僕にとって寝苦しい真夏の蒸し暑い夜にどうしても欠かせない一枚になっている。(金子厚武)
>>>『24時』収録曲
>>>『24時』収録曲
それでも東京での暮らし、活動は続いていく。そこに抗わずに受け入れていくことの空しさと諦念と、まあ、いいか、というようなセ・ラヴィな心理。曽我部恵一の持って行き場のない重く複雑な思いが本作を支配している。初回盤についている「『24時』レコーディング日記」が痛々しい。このアルバムが発表されたのは98年7月。その年の2月16日からマスタリング終了となった5月6日までの約3ヶ月間のスタジオの記録が綴られているが、あちこちに「うまくいかなかった」なる記述が散見される。とにかく試行錯誤だらけ。糸がもつれにもつれてどうしようもなくなりながら、なんとか完成までこぎ着けた様子には今読んでも胸が痛む。どんな作業にも苦悩はつきものだが、しかしながら、この日記には苦心の末に得られるだろう喜びが全く記されていない。その痛みが実際に全15曲80分超というヴォリュームの本作をとにかく重く重くしている。だが、酷い内容かと言えば決してそうではない。ギリギリになってドラムを丸々録り直したというラストの“24時のブルース”などは、最後の最後になって導き出した「今この場所で輝くためには?」へのこの時点での噓偽りない回答のような曲になっているし、菊地成孔がテナー・サックスで参加した“ぼくは死ぬのさ”のジョン・レノンさながらのヘヴィ・ブルーズは、音圧を高くでもしないと乗り切れないとでもいうように追いつめられた曽我部自身の赤裸々な告白に揺さぶられる。さらに、8cmボーナス・ディスクに収録されたラフなデモさながらのフィールド・ノイズに始まる“ベイビー・カム・ヒア組曲”の、もつれにもつれた作業から滲み出た寝汗をかき集めたようなドロリとした臭気には、本編のどれにもない本音を感じないではいられない。ビートルズのホワイト・アルバムのような分裂し切った作品ではないし、そのバラバラなのが面白いというような解釈も適さないだろう。ただただ、東京で暮らしていくこと、そこで音楽を鳴らすこと、それを誰かに届けることの困難と迷いが落とされている、それゆえに聴くのがつらい、そんなアルバムだ。ブックレットに彼らをずっと支えてきた育ての親のようなディレクター、渡辺文武の名はない(次作『MUGEN』ではアドヴァイスという形で復活)。でも、だからこそ彼らは音楽家として一回り大きくなることが出来たのだろうと思う。この作品を境に曽我部の表情が変わったことに恐らく多くの人が気付いたはずだ。(岡村詩野)
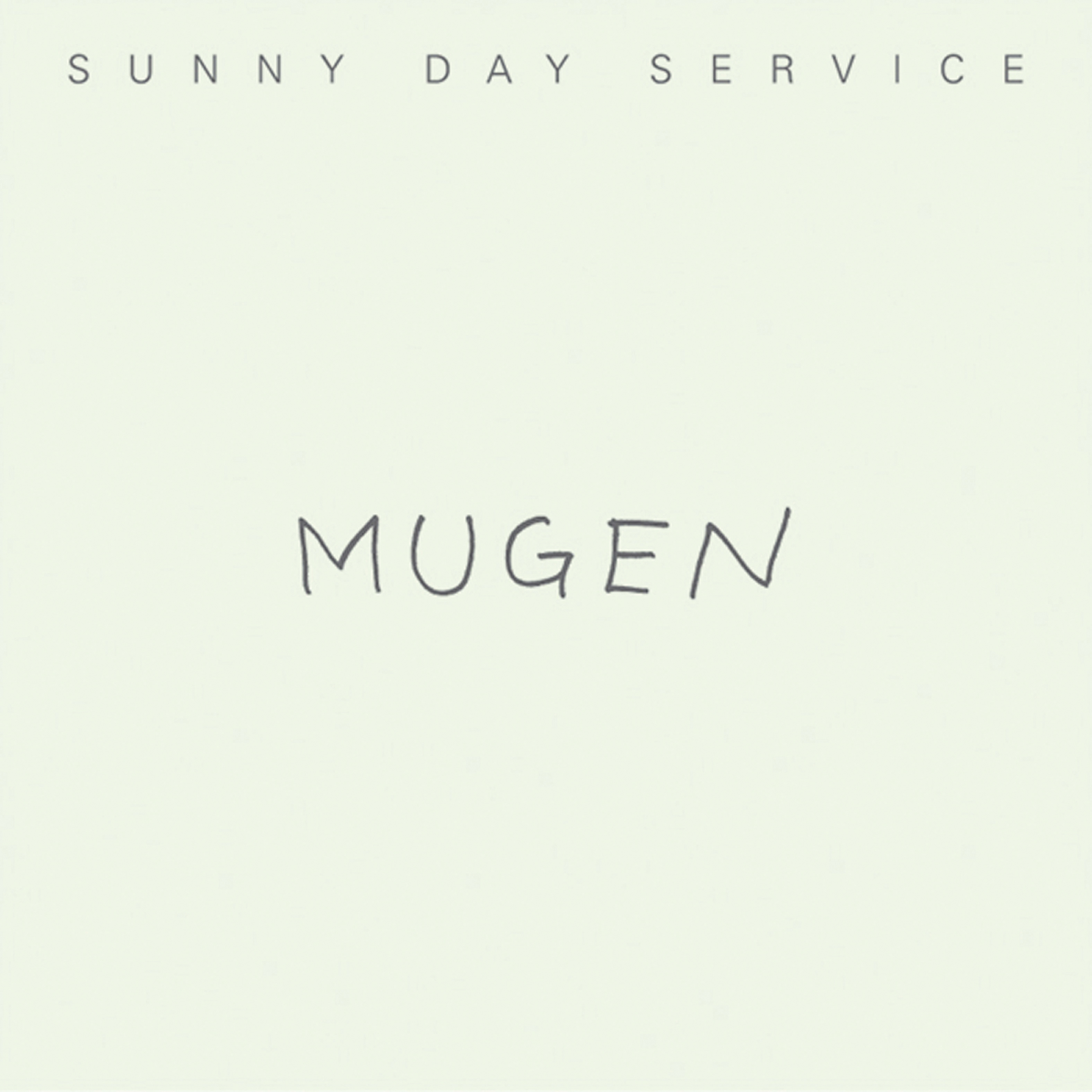
解散前の7作のなかでは、もっともえぐみのないアルバムかもしれない。レコーディングは、非常に険悪なムードで進んでいたようだが、ウェルメイドなポップ・ソングを揃えた今作から、そうしたバッド・ヴァイブスを認識するのは難しい。また、“スロウライダー”のようなグルーヴィな楽曲でさえ意図的に色味が抑えられたサウンドが敷かれており、平熱のエモーションがつねに保たれている。数曲では、ボンゴやコンガが使われつつも、ダンサブルになり過ぎず、アンサンブルの魅力を光らせる。いま聴くとこのあたりは、5人編成のスカートと近しさを感じるが、そうした点でもやはり、今作は上質のポップス・アルバムだ。そして、よしもとよしともの『ライディーン』がインスピレーションになったという“江の島”は、柔らかなリズムボックスと流麗なギター・フレーズに乗って、車窓から見える海沿いの景色を鮮やかに綴っており、音楽好きな高校生の苦い失恋を描いた参照元の作品とともに、おそらくバンドの意図を超えたレヴェルで、ある世代特有の一曲になっているような印象さえある。「いつもそうさわれないよ/感じるだけ/昼の荒野」。恋い焦がれ、夢中で手を伸ばしても、決して掴むことのできない夢幻。それがゆえに欲望は枯れることのない無限。1999年、18歳だった僕には、このアルバムの持つ甘美な絶望がとても心地よかった。(田中亮太)
>>>『MUGEN』収録曲
「東京の街には太陽と雨が降って/流れるメロディがぼくを旅へと誘う/花が咲いては枯れ/枯れてはまた咲いて/笑う女の子が恋のふもとで手を振る」。冒頭から歌われる、サニーデイ・サービスの魅力を見事に凝縮したような言葉とメロディ・ライン。本作『MUGEN』は、時を経て少しずつ関係性に変化と軋轢が生じ始めたサニーデイ・サービスが、もう一度原点を見つめ直そうとしたアルバムだ。超大作の前作『24時』から一転して全10曲45分強、手書きのバンド名とアルバム・タイトルだけを載せたアートワークも至極シンプルなものとなり、出来る限り余計なものを削ぎ落とした、まとまりのある作品が志向されている。アルバムとしては『東京』や『サニーデイ・サービス』に連なるサニーデイ・サービスの正統な系譜を継ぐ一枚と言えるだろう。とは言え、スタジオ・ワークの丹念な練りはかつての作品とは一線を画している。薄っすらとサイケデリックなコーラスや、バンジョーやマンドリン、コンガ等々多様な楽器が使用された多層的なレイヤー処理からは、例えば60年代後半のビーチ・ボーイズにも通じる、音響的野心とポップ志向のバランス感覚が感じられる。本作のラストは、ファンの女性が自作したという“東京”のオルゴールの音色で幕を閉じる。そこに込められているのは、メンバー3人の関係性と分かち難く結びついたサニーデイ・サービスの音楽が、ファンの思い出と共有されることで「無限」になったというポジティブな思いなのか、それとも、もはやそれも「夢幻」になりつつあるという諦念めいた思いなのか。どちらにせよ、本作はどこか儚く脆く、それ故にとても普遍的で美しい魅力を、今も変わらず湛え続けている。(青山晃大)
『東京』から20年。再結成から8年。時代が
一巡し、来たるべき新作に期待が高まる、
サニーデイ・サービス全作を振り返る 後編
はっぴいえんどを再定義した『東京』という
紋切り型に異論あり。サニーデイ・サービス
の真価をジャズ評論家、柳樂光隆が紐解く
