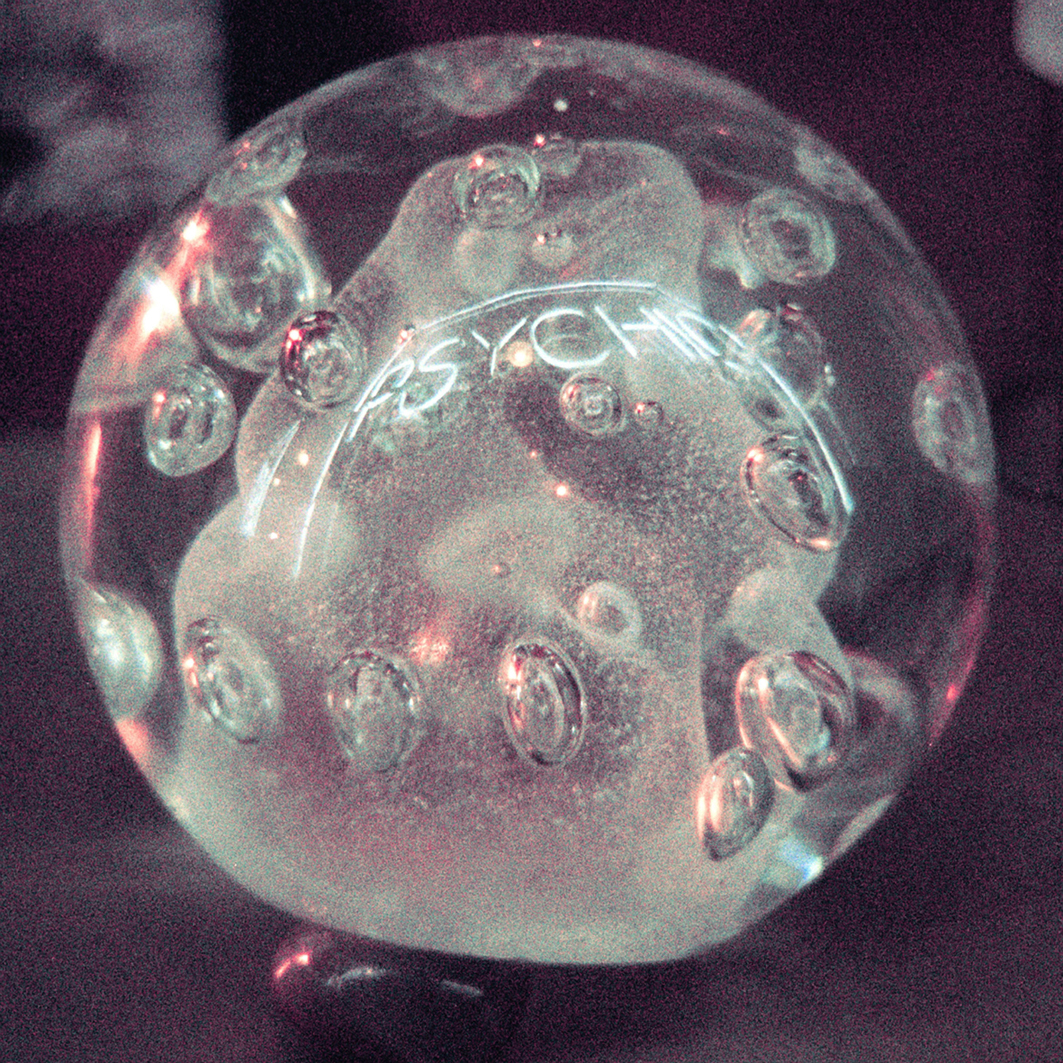
2011年当時、まだNY在住の大学生だったニコラス・ジャーという21歳の青年が作り上げたデビュー作『スペース・イズ・オンリー・ノイズ』は、まさにセンセーショナルだった。それはbpm100あたりまで大胆にピッチダウンしたミニマル・テクノに乗せ、レナード・コーエンが歌い、エリック・サティのピアノが寄り添っているようなアルバムで、驚くほど多くの人々を驚嘆させることに成功している。いかにも自己陶酔的でスノッブなアート気取りといった雰囲気は鼻につくが、彼が敬愛するリカルド・ヴィラロボスから何よりその音楽的な冒険心を受け継いで作られた刺激的なダウンテンポは、確かに未知の領域を開拓していたと言っていい。同年末には『レジデント・アドヴァイザー』や『ミックスマグ』といったクラブ系メディアで年間ベスト1位に選出されただけではなく、ホームグラウンドのメディアとは言えない『ピッチフォーク』でも20位に選ばれる快挙を成し遂げたという事実は、彼を取り巻く熱狂の大きさを雄弁に物語っているだろう。ジェイムス・ブレイクに並ぶ2011年におけるエレクトロニック・ミュージック界の寵児、それは間違いなくニコラス・ジャーだった。
同作以降、新レーベルの立ち上げやコンピの発表というニュースも届いていたが、『スペース~』に続くニコラスの大きな動きとして最も大々的に注目を集めているのが、自身のツアー・バンドでギタリストを務めるデイヴ・ハリントンと結成した「新しいバンド」、ダークサイドである。おそらく、今年6月に彼らがネットで公開したダフト・パンク『ランダム・アクセス・メモリーズ』を丸ごとリミックスしたアルバムを耳にした人も多いだろう。今思い返してみれば、あの作品は、その直後にリリースが発表された1stアルバム『サイキック』の豪華なアペタイザーだったというわけだ。
ただ、ダフト・パンクのリミックス・アルバムは、戦略としては非の打ちどころがないほど巧妙だったが、音楽的には目を見張るようなものではなかった。そして、手厳しい言い方をしてしまえば、それは『サイキック』にも同じことが言えるかもしれない。
闇を切り裂くように鋭く甲高い歌声が響き渡る11分強の電子組曲“ゴールデン・アロウ”は、アルバム冒頭で早くも訪れる本作のハイライトだ。そして、その後もダウンテンポ気味のハウスやクラウト・ロック、さらにはファンクやブルース、アンビエントの語彙を散りばめたトラックが続き、十二分に耳を楽しませてくれる。ただ、ダークサイドの根幹にある、「ニコラスがアナログ機材を使って生み出す沈み込むようなエレクトロニック・サウンドと、デイヴのブルージーなギターの接合」という音楽的なアイデアは、驚くほどの化学反応を生み出しているとは言い難い。
本作のプレスリリースには、ニコラスが「自分はロックを作っていると思った」と語り、デイヴが「自分はダンス・ミュージックを作っていると思った」と語っている様子が紹介されている。しかしながら、そのようなジャンル越境的な感覚自体は、今や決して目新しいものではないだろう。むしろ、そういった状況下でもまだこんなやり方が残されていたのか、という驚きを与えた点に、『スペース・イズ・オンリー・ノイズ』の素晴らしさはあった。
実際、本作に較べるとニコラスのソロは音楽的にミニマムで空間の余白が大きく、ある意味ではシンプルなのだが、次にどのような展開になってしまうか分からないスリルが常にあった。しかし、『サイキック』には全般的に妙な安心感を覚えてしまう。もちろん、決して悪いアルバムではない。だが、『スペース~』と肩を並べるほどの目の覚めるような傑作でもない。
ニコラスは来年にもソロの2ndをリリースする予定だと聞く。やはり彼は一人ベッドルームで奇想天外な発想をトラックに落とし込む時にこそ力を発揮するプロデューサー気質であることが明白になった今、ダークサイドでの来日が実現することよりも、ソロでの次の一手が待ち遠しい。きっと彼はそこで、また新たな光景を見せてくれるはずだ。
このプロジェクトの発端が、ニコラス・ジャーのソロ・ツアー用に組まれたバンド・セットだった経緯を考えれば、なるほど、本作の始まりがロックンロールのレコードを作ることだったというジャーの動機も何となく察しがつく。第一、そもそもがいわゆるクラブ・ミュージックやコンシャスなテクノ・サウンドに対して違和感を抱いた男である。2011年の『スペース・イズ・オンリー・ノイズ』を機に知名度を広げたジャーのプロフィールには、リカルド・ヴィラロボスの名前が常套句のようについて回ったが、実際に触れたサウンドはミニマルとかテクノとかいうより、たとえばマッドリブとキース・ジャレット、さらにはケアテイカーが同居したようなダウンテンポでラウンジーなコラージュに耳を奪われたことが自分には印象深い。そして、何よりその男は魅力的な美声のシンガーだった。
そんなジャーが、自身のエレクトロニックなスタイルとギターや生ドラムといったロックのインストゥルメンタルを組み合わせるという、発想自体は凡百なアプローチにどんな活路を見出したのか。あいにく、2年前のEPを聴いたかぎりではマップ・オブ・アフリカらバレアリックの遅れたフォロワー程度の感想しか残らず、本作に対しても正直たいした期待を持ち合わせてはなかった。
結論からいえば、EPの印象を大きく超えるようなサプライズは本作にない。しかし、はるかにプログレッシヴな輪郭を帯びたそのロック・サウンドは、まさにEPを習作としながら、ジャーが自身のアイデアを成熟させることで形にした成果にほかならないだろう。EPの時点ではまだ不定形なセッションといった様子が強かったが、本作においては、コンポーズにより意識が置かれた楽曲固有のストラクチャーのようなものを感じることができる。
その背景には、もちろん、ジャズのベーシストとして知られるが、インディ・ロックからメタルまで幅広いジャンルで演奏してきたマルチ・インストゥルメンタリスト、相棒のデイヴ・ハリントンの功績が大きいことはいうまでもない。ブルージーなギター・リフとハンドクラップが刻むドアーズ・ライクな“ペーパー・トレイルズ”、呪術的なパーカッションが鮮烈なアンビエント・ファンク“ジ・オンリー・シュライン・アイヴ・シーン”が並ぶ中盤は本作の白眉だが、とりわけジャーの熱心なリスナーにとっては、“メタトロン”の濡れ落ちるようなバラッドの方が刺激的かもしれない。逆に、“フリーク、ゴー・ホーム”や“グリーク・ライト”のアブストラクトやエディット/コラージュは、それが『スペース・イズ・オンリー・ノイズ』と同じ作り手によるものであることを確かに伝える。そして、“ハート”を筆頭に本作のほぼ全編で聴けるジャーのヴォーカルはとても情熱的で、テノールとファルセットを使い分け、レナード・コーエンやジム・モリソンの面影も彷彿させるその豊かな感情表現は聴き手を魅了してやまない。
広義のサイケデリック・ロック、それこそ(デヴィッド・ギルモア加入後の)ピンク・フロイドやカンのようなバンドが、このプロジェクトにおける音楽的な指標のひとつに位置づけられることはおそらく間違いない。ただ、たとえば2000年代後半のクラウト・ロック・リヴァイヴァル、そこから流れたコズミックやディスコ・ダブのようなダンス・カルチャーとの隣接/緊張感は、本作から受ける印象では希薄に思える。ジャー本人の先鋭的なアーティスト・イメージとは裏腹にダークサイドにはどこか古色蒼然とした趣があり、それは個人的に、トリップホップ直前夜のブリストルに現れたムーンフラワーズの孤雲野鶴なサイケデリックも思い起こさせて面白い。あるいは、ダークサイドが『スペース・イズ・オンリー・ノイズ』へのリアクションであるといえるように、ジャーの来るべきセカンド・アルバムが本作へのアンサーとなり得るシナリオは十分に考えられる。ともあれ、興味深い作品であることは確かだ。
