

これは2010年代という変革のディケイドの墓標だ。“マグノリア”や“wokeuplikethis*”の時点では誰もが100%ピエール・ボーンのシグネチャーだと思っていたざらついた音色の耳障りなアナログ・シンセ・リフは、前作『ダイ・リット』、本作を経て、もはや完全にカーティ本人のシグネチャーとなった。韻も踏まず、時にはタイトルを連呼するだけの、リリシズムの片鱗もなく、ウォーク後の価値観さえもどこにも見当たらないリリックをひたすらライムする(いや、叫ぶだけの)フロウとさえ呼べない耳障りな声の連なりと耳障りなシンセ・リフ、唯一の規範であるハットとキックがバランスを欠いたミックスによって渾然一体と鳴っているだけの、ひたすら冗長な全24曲63分。前述のような身振りによって、つい数年前まではヒップホップという文化と伝統と規律の破壊者として脚光を集めたカーティは、2年の間ひたすら期待を募らせた挙句、70年のパンク・ジン〈スラッシュ〉の表紙を飾ったエモとゴスの開祖でもあるダムドのデイヴ・ヴァニアンを模し、ドレッドにする以前の自らの若き肖像を使った青「白い」顔をした吸血鬼という新たなペルソナを纏う以外は、ほぼ何ら進化を見せないという形で世界中からの期待に応え、リリース後ほんの数時間の間に、多くのラッパーたちがアートへの献身と起業家崇拝の二つに枝分かれしていく2020年的な磁場の狭間に置き去りにされた。「私」というエゴを愛するがあまり、自分の周りに孤独という壁を築き上げることがすべての元凶であることを歌ったボン・イヴェールの“iMi”をサンプルしたアルバム最終曲のタイトルは、“F33l Lik3 Dyin”。ほとばしるほどの赤(=血)を貪り尽くすことでしか生を謳歌することの出来ないヴァンパイア。それは奪うことでしか延命を望めない我々が暮らす社会のアナロジーでもある。予め失敗作であることを運命づけられたこのアルバムが放つ蠱惑的な魅力の正体はノスタルジアなのだろうか。この墓標の下には、変革の時代だった2010年代が眠っている。ひたすら騒々しいまま。(田中宗一郎)
listen: Spotify

J・ハスは2018年1月に公共の場でナイフを所持していた咎で逮捕された。前年に『コモン・センス』で成功を掴んだ直後だったたけに、そのニュースは大きな衝撃をもたらした。キャリアの重要な期間を獄中で過ごさざるをえなかったハスは、2019年4月、ようやくカム・バックする。そうして彼が立ったのは、02アリーナでのドレイクのステージだった。パーフェクトな帰還だ。それだけに、“マスト・ビー”での本格的な復帰は待望のものだったと言える。太いベースライン、トラップ風のハイハット、かなしげなストリングスとサックス……。相棒のジェイ5によるビートをバックに、J・ハスは口を開く。「俺はめちゃくちゃになった男を見た、閉じ込められた男を見た」。悲嘆に暮れているのかと思いきや、それに続くのはストリートの描写である。O2アリーナで大観衆を沸かせながらも、路上で起きていることをライムする――どこまでもハスらしいスタイルだ。『ビッグ・コンスピラシー』は、あくまでもJ・ハスらしいアフロスウィング、アフロバッシュメントを中心にしている。アルバムはダークなストイシズムに満ちており、華美なきらいもあった前作とは対照的に、ハードな態度を貫く。とはいえ、そこには音楽的な野心が見え隠れしている。“ノー・ディナイイング”はドリルだし、レゲエの注目株であるコーフィーとの“リピート”はダンスホールで、前作に続いて参加したナイジェリアのバーナ・ボーイ(今年の最重要人物の一人だ)との“プレイ・プレイ”はレゲエ色が強調されたアフロビーツだ。ヒップホップ・ソウル調の“ワン・アンド・オンリー”ではエラ・メイが堂々たる歌を聞かせていて、このあたりの人選も見事というほかない。J・ハスが立役者になったアフロスウィング、アフロバッシュメントは、今年さらに広がりを見せた。コベントリーのパ・サリューによるヘヴィな『センド・ゼム・トゥ・コベントリー』は、その最良の成果のひとつだろう。そういったタイミングに『ビッグ・コンスピラシー』でハスがストリートに戻ってきたことは、2020年の重要な出来事だった。(天野龍太郎)
listen: Spotify

1995年2月15日テキサス州ヒューストン生まれ。現在25歳のミーガン・ザ・スタリオンは、ビヨンセをゲストに迎えた“サヴェージ・リミックス”とカーディ・Bとのコラボレーション“WAP”の二枚のシングルをビルボード・チャートのナンバー・ワンにたたき込み、2020年の顔になった。しかし、光あるところには常に影あり。7月15日に交際中のラッパー、トーリー・レーンズに足を撃たれるスキャンダルが起きる。『グッド・ニュース』はその事件についてのラップ・ソング“ショット・ファイアード”から始まる。銃殺されたノトーリアスBIGの“フー・ショット・ヤ?”を引用し、今年3月に警官に誤って撃ち殺された救急救命士ブリオナ・テイラーに言及しつつ、銃撃による心身の痛みを表現する。二曲目、ジャズミン・サリヴァンの出口なしの混乱の歌をサンプリングした“サークル”でも、「私の頭の中のバグダッド」との対峙を曝け出す。『グッド・ニュース』はちっとも「GOOD」じゃない、「BAD」な近況(=NEWS)を伝える反語的タイトルだ。「BAD」なのは状況だけではない。ミーガンはMVやライヴでデカい尻を激しく揺らし、あからさまに性的なリリックを綴り、自らを「BITCH」と呼称する。セクシュアルに「BAD」とされる女性をレペゼンする。彼女の前では『NARUTO』も下ネタと化すだろう。曰く「佐助を探す九尾の狐のようなプッシー」(“ガールズ・イン・ザ・フッド”)。ハイハットとキックを時に32分の三連で刻むトラップ・ビート、80年代のマシン・ビートを思わせる16分のハイハット、そして90年代クラシックの引用(前述のビギー、または“フリーキー・ガールズ”におけるアディーナ・ハワード)。ヒップホップの変遷をまとめたような音像の正統性の中に、ある種の集合的意志が息づいている。それは「BAD」を「GOOD」に変えて明日の糧としてきた、ラップ・カルチャーの精神の在り方だ。ミーガンは痛みと混沌とセックスの終わりなき呪縛を、重く速いフロウで今日も快活に笑い飛ばす。(伏見瞬)
listen: Spotify

ウェイ、ウェイ、ウェイ、ウェイ、エーイ、エーイ、フウーッ、ハッ! 最初は2019年7月のミックステープ『ミート・ザ・ウー』、続いて2020年2月の『ミート・ザ・ウー・2』、さらには死後の『シュート・フォー・ザ・スターズ、エイム・フォー・ザ・ムーン』と、都合3作すべてのLPに収録されることとなった“ディオール”。あの必殺アンセムがパンデミック前のストリートやクラブに浸透した時点で、ポップ・スモークはラップ・シーンに久々に現れた真のゲーム・チェンジャーだった。アトランタ・トラップからUKドリルを経由してのブルックリン・ドリルというジャンル&地政学上の転換。ミュージック・ビデオ撮影のために借りたロールスロイス・ファントムをそのまま自分のものにしてしまう、そのリアル・ギャングとして強烈な実像がマンガのようにそのまま刻印された唯一無二の声とフロウ。そのどちらかが欠けていたらここまでの現象化はあり得なかったわけだが、その両方が作品に結実していたのは本作『ミート・ザ・ウー・2』まで。記録破りのファーストアルバムとなることが約束されていた『シュート・フォー・ザ・スターズ、エイム・フォー・ザ・ムーン』は、約束通り2020年を代表する大ヒットアルバムとなったわけだが、それは後者の「声とフロウ」をアトランタ勢を含む先輩スターたちが飾り立てたゴージャスな葬礼に他ならなかった(それも全然悪くないのだが)。2020年に入ってようやく弾が切れたXXXテンタシオン。「弾はまだ残っとるがよ」なジュース・ワールド。ポップ・スモークだけでなく、まだまだ全然底が見えなかったそんな特別な才能たちを20〜21歳という極端な若さで奪っていった、繰り返される悲劇。それを生み出す社会構造。そんな潰えた可能性たちの死骸が転がっているシーンを指差して、「停滞」と呼びたければ呼べばいい。(宇野維正)
listen: Spotify

ポップ・ミュージックの世界には、ミュージシャンの死後も制作が続いて完成するアルバムというジャンルが存在する。ここ日本ではhide『Ja,Zoo』が代表的だが、本人が模索したアルバム・コンセプトや意志、楽曲を、遺された近しい人物たちが継承して完成させるという点で、未発表曲集とははっきりと区別されるべきだろう。だが、もちろんミュージシャン本人の意図通りの作品が出来上がるかは疑わしい。マック・ミラーによる本作『サークルズ』は、2018年9月の急逝のわずか1ヶ月前にリリースされたアルバム『スウィミング』と対になる作品として制作されていたそうだが、やはり制作をリードした遺族やプロデュースを手がけるジョン・ブライオンの感傷による影響は拭いきれない印象だ。ベッドルームでマック・ミラーが宅録したかのような親密なプロダクションは、近年のビート・トレンドと程遠いばかりか、ラッパーではなくシンガーソングライターの作品のようですらある。しかし、それが結果として本作をアクチュアルな作品に仕立てることに繋がっていることは無視できない。全世界が喪に服すようだった2020年春、自室に籠った多くのリスナーの気持ちに、この悲しきアルバムは優しく寄り添った。マック・ミラーの不安定な心情の吐露は、ヒリヒリした痛みを伴いながらも結果的には不安を緩和させた。誰かの悲しみや苦しみや不幸が、他の誰かを癒すこともある。それはポップ・ミュージックのひとつの呪いであり祝福だ。(照沼健太)
listen: Spotify

昨年の『アフリカン・ジャイアント』が候補に選ばれながら、グラミー受賞を逃したことに対する世間の反応を背に、受賞経験者ユッスー・ンドゥールを招き、1曲目から、目標は高く(“レベル・アップ”)と始まる本作の表題は『トゥワイス・アズ・トール』。そんなバーナに加え、アフリカとの接点を求めていたディディもエグゼクティヴ・プロデューサーに(しゃべりで何度か登場)。アルバム全体のサウンドの基調は、過去作からのプロデューサーたちがもたらしてくれる「アフロフュージョン」。そこに、曲によってはティンバランドやマイク・ ディーン等のUS勢が、やり過ぎない程度に音色や質感や鳴りに手を加えている(ようだ)。そうした絶妙な新趣向で始まるアルバムの前半では、よりデカい存在になるため精進してゆくとのバーナの意気込みが歌われることで、聴く者は鼓舞される。それが、ケニアのポップ・グループ、ソウティ・ソルを招いた“タイム・フライズ”から、バーナの歌は具体的にアフリカに、そこからアフリカン・ディアスポラに向けられたものとなり、“モンスター・ユー・メイド”では独立以前から続く地元ナイジェリアの問題点を挙げる。ストームジー共演の落ち着いた“リアル・ライフ”では、生きること、ラスト曲では死生観(ポップ・スモークの名も)にも触れ、アフリカン・ディアスポラの心をひとつにまとめたいバーナの意思が、作品全体の根底から響いてくるようだ。(小林雅明)
listen: Spotify
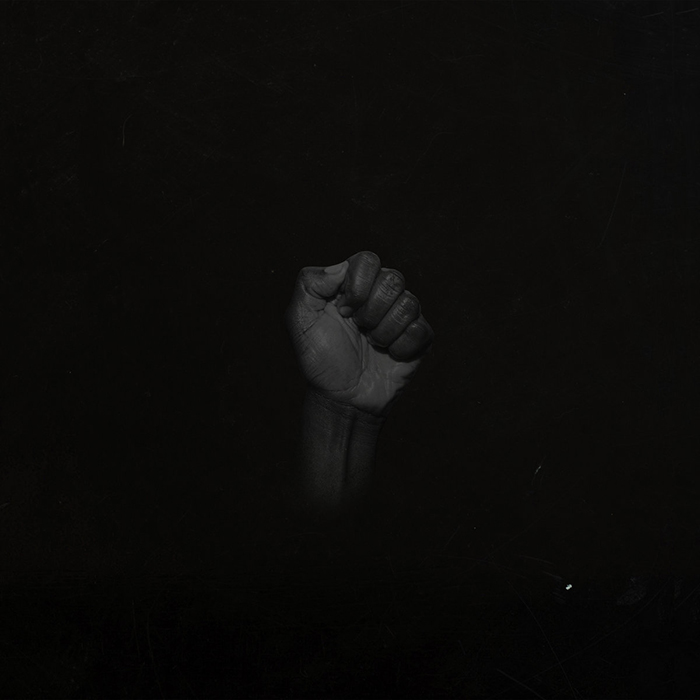
ジューンティース(6月19日。1865年のこの日、合衆国で奴隷解放が実施された)に発表された本作は、2020年の音楽を振り返り、ブラック・ライヴズ・マター(BLM)との関係について語るとき、真っ先に挙げられる(べき)作品だ。例えば、ケンドリック・ラマー自身は意図してなかったのに、BLM運動の現場で愛された“オールライト”という曲があるが、逆に、このソルトなるコレクティヴの作品は、BLM運動が拡大化する危機的状況を直接的に反映させ(その旨は公式サイトに)ながら、場合によっては“オールライト”以上に簡素かつ意義深い表現に向かっているのだ。声高なレジスタンスや、大所帯のゴスペル・クワイアやバンドによる厚みや迫力のあるサウンドで押してくるのとは違う。リズム&ブルースやアフロビートなど「ブラック」に根差した様々な音楽の骨組みの部分や、歌だけではなく、チャントやスポークンワード表現における簡潔さに耳を傾けている。その結果、ソルトの奏でる一曲一曲は、公共の場で大音量で大衆を先導するのではなく、熾火(おきび)のように炎を上げずとも燃え続け(ジャケのブラック・パワー・フィストの画像処理が象徴的)、聞き手一人一人に働きかけ、その熱を静かに、だが着実に伝播/共有してゆき、レジリエンスを引き出してゆくようだ(本作には続編がある)。これはBLMのサウンドトラックなどではなく、これもBLM運動なのだ。(小林雅明)
listen: Spotify

アメリカ東海岸のゲイ・クラブで70年代初頭に鳴っていたコミュニティ音楽としてのディスコと、その後79年のディスコ・デモリッション・ナイトの直接の引き金となった当時のチャートを賑やかせた紛い物のディスコは、文化的にはまったくの別物だった。だが、いまだ20世紀後半にはそれぞれの文化的な出自を背景に持つビートによって規定されていたダンス・ミュージックは、21世紀に入り、資本主義とグローバリゼーション、インターネットという三つの触媒によって幾多のビート・メイキングのフォーミュラと歴史を飲み込み、その出自から切り離され、より高性能なグローバル・ポップとして再定義された。その完成形がこのアルバムだ。どこまでもいかがわしい紛い物のダンス・ミュージックとしてのポップ。この見事な完成度。と同時に、思わず舌を巻かずにはいられない軽薄さ。インネクセス88年のメガ・ヒット“ニード・ユー・トゥナイト”のリフの引用から“ブレイク・マイ・ハート”が組み立てられていることを指摘するまでもなく、この傑作は前述のような歴史が溶解した結果の産物でもある。だからこそ、Mr.フィンガースやマスターズ・アット・ワークといった伝統や出自との繋がりを示したブラック・マドンナ改めザ・ブレスト・マドンナ主導のリミクス版『クラブ・フューチャー・ノスタルジア』の言い訳がましさに比べれば、この誰をも拒まない軽薄さにこそ軍杯が上がる。だが、パンデミックを経た世界では文字通りこのアルバムは、もしかするとあったかもしれない未来へのノスタルジアそのものになった。20世紀後半にシカゴ、デトロイト、ニューヨークからベルリンやロンドン、東京へと飛び火したコミュニティ音楽の歴史は一度は完全に潰えたと言っていいだろう。血の轍を乗り越えた先の、この軽薄さを取り戻すために我々はまたゼロから始めなければならない。(田中宗一郎)
listen: Spotify

ラップ、ドリル、ダンスホール、アフロビーツ、R&B……と多様なスタイルで聴かせるパ・サリューのデビュー・ミックステープ。ロンドン郊外のスラウで生まれた翌年から強制送還された両親と母国ガンビアで暮らし、このテープの表題にもあるコベントリーに10歳で戻るも、西アフリカ系で訛りが強いため、激しい差別の対象にされたという。本作を聴き始めると、ほどなくしてパが訛りむき出しでガンガンラップしているのに気づくはず。これは、彼が自分が自分であることを誇ることに徹した表れだろう。また、音楽的な幅広さも、ステレオタイプの陷穽に嵌められるのを嫌ったからに違いない。さらに、パは武装することで、そういったマインドセットを補強し、文句を言ってくる連中をなぎ倒しながら、新天地コベントリーと祖国をつなぎ、自らの足場を固めていったことが本作から見えてくる。彼は昨年10月に銃撃されるも生き延びている。そんな環境だからこそ、“ブロック・ボーイ”でド頭から威勢良く登場し、曲の後半以降、鬨の声と勇壮なストリングスが加わる“マイ・ファミリー”は「血は水よりも濃し」の世界だ。アルバム全体を通じて、サウンド・スタイルが次々に変わってゆく一方、パが一貫して放ち続ける「鉄砲玉みたいな熱さ」も、ラストのマへリア客演曲“エナジー”で少しはクール・ダウンされるかと思いきや、生存本能に触れていて、徹頭徹尾、生命力に溢れたテープとなっている。(小林雅明)
listen: Spotify

今回は自分の物語だけでなく、人々の物語として『フォークロア』を紡いだテイラー。これまでの彼女のアルバムと同様、そこでは恋や怒りや傷心が描かれるが、曲調にも歌詞にもどこかアメリカン・クラシック――文学、音楽、映画、風土――な匂いが加わっている。それは意図的というより、新たなコラボレーターとの出会いがあり、さらには脈々と連なるものをイメージしたとき、テイラーの想像の端々に浮かんできたのだろう。自然の中にテイラーが一人たたずむヴィジュアル自体、古びた趣を持ち、まるでソローの『森の生活』、もしくは17世紀ニューイングランドが舞台のホラー『ウィッチ』(2015)のようだ。女性の苦悩を歌う“マッド・ウーマン”も、ホーソーンの『緋文字』など、共同体から狂女/魔女と呼ばれてきた女性像と共鳴する。“ザ・ラスト・グレイト・アメリカン・ダイナスティ”に登場する実在のソーシャライト、レベッカ・ハークネスなど、カポーティやフィッツジェラルドの小説に出てきてもおかしくない。とんでもなく裕福で反抗的で、女友だちの一団「ビッチ・パック」とともに上流社会を騒がせた女性。その人生はもちろん、彼女の別荘を購入したテイラーの人生と重なり、曲の中で時間の流れを生み、大きなストーリーとなる。自分の人生は自分が体験したことだけじゃない、時代や性別を超えた人生の集積でもある――その気づきが創作そのものに新たな命を吹き込んでいる。おそらくだからこそ、ほんの数か月後には『キッドA』における『アムニージアック』のような『フォークロア』の姉妹作、『エヴァーモア』まで生まれてきた。その溢れ出す創作意欲。彼女の動機にはもうひとつ、最初の6枚のアルバムの原盤権が奪われた怒りがあるのでは、と勘ぐっているが、それでもやはり、この新境地は大きい。もう恋をしなくても、男と別れなくても、いくらでも新しい曲が書ける。私の中にはいくらでも物語が眠っている――テイラー・スウィフトが世代のソングストレスとなる階段を何段も駆け上がってみせた、一大転機作。(萩原麻理)
listen: Spotify
▼
▼
2020年 年間ベスト・アルバム
6位~10位
2020年 年間ベスト・アルバム
21位~30位
2020年 年間ベスト・アルバム
扉ページ
