

あらゆる意味で「2016年的」な作品だ。匿名的なアートワーク、コンパクトなトータル・タイム、ミニマルでインダストリアルなサウンドとオールドスクールなソウル曲の共存は「カニエ・ウェスト『イーザス』以降のポップ・レコード」の提示であり、2曲目でいきなりやってくるビートレスな“ジェイムズ・ジョイント”やテーム・インパラのカヴァー“セイム・オール・タイム”はフランク・オーシャン『ブロンド』の予見を感じさせる。しかし今年初頭の本作リリース以後、カニエ『ザ・ライフ・オブ・パブロ』を筆頭に、ビヨンセの最高傑作『レモネード』、前述のフランク・オーシャンといった歴史的名盤候補が立て続けに発表されたことによって、その先鋭的なイメージが瞬く間に払拭されてしまったのも事実。いや、だからだろうか、いま改めて聴く本作は、さまざまな音楽的意匠を行き交いながら、最後にはシンプルにピアノとヴォーカルで聞かせる最終曲“クロース・トゥー・ユー”という普遍へたどり着くという道程にこそ『アンチ』というアルバム・タイトルの本質と予言があったようにも感じられる。(照沼健太)
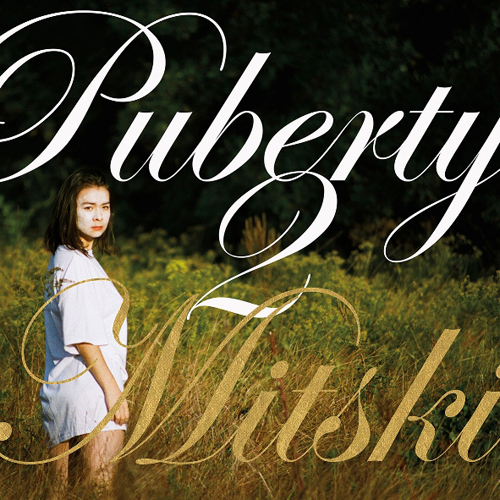
ジャパニーズ・ブレックファスト、ジェイ・ソム、そしてこのミツキ。をピックアップして「アジアン・ハーフの女性ミュージシャン」と括られることに、他でもない当の彼女たち自身がそれなりに自覚的だったことは、実際にこの夏、3組が一緒にプロモーショナル・ツアーを行ったという事実からも察することができる。ともあれ、そんなふうにして彼女たちに向けられたスポットライトは、話題に欠けた2016年のUSインディ・シーンを賑わせたささやかなトピックとして、ぜひ記憶の片隅に留めておかれたい。とりわけ、このミツキの4作目に収められた“ユア・ベスト・アメリカン・ガール”は、ピッチフォークのベスト・ニュー・トラックにも選ばれるなど大きな反響を呼ぶことに。エスニシティとアイデンティティに翻弄される悲恋を描いたそのノイズフルなバラードは、さまざまな立場の違いから度し難さを増す今という時代の意識に深く突き刺さり、聴く者を強く揺さぶった。たとえばその苦い後味は、昨今のアフロ・アメリカンの音楽家が投げかけるメッセージとも、その問題の根底において通じ合うものではなかったか。(天井潤之介)

2016年はR&B/ヒップホップにとって、インディ・ロック・リスナーでさえ羨むような記録的な名盤ラッシュの一年だった。その中で際立って目立ったとは決して言えなかったものの、これを機に昨今のブラック・ミュージックに手を伸ばした人には決して見過ごして欲しくないのがスクールボーイQの本作。現在のヒップホップ・シーンのニュー・キング、ケンドリック・ラマーとコンプトンで〈ブラック・ヒッピー〉を共に組む彼は、同じくLAのクリエイター集団でケンドリックの諸作でも貢献しているDigi+Phonicsのメンバーが中心となってプロデュースしたトラックに乗って、ストイックに2016年のコンプトンを真摯に見つめるラップを聴かせる。ケンドリックのように変幻自在にライム・フローを操れるわけでも、決定的な名フレーズを生み出しているわけでもない。その意味ではまだ発展途上ではあるのだが、時折聞かれる、ケンドリック以上にケイオティックかつサイケなサウンド展開に乗った際のフロウのオーラには、ここからひとつの新たなカリスマを生み出す兆しのようなものが伺える。地元のライバルたちとの刺激合戦で一皮剥けるとすごく楽しみな存在だ。(沢田太陽)

制作に16年間費やされた本作は、マスタリングのためにメンバーがニューヨークのスタジオに飛ぶ1時間前まで絶え間のない作業が続けられていたという。もう完全に常軌を逸している。ちなみに、本作リリース後に〈BBCレディオ1〉で2時間にわたってオンエアされた〈エッセンシャル・ミックス〉は、本作と質感をほぼ同じくする完璧なサンプリング・アート作品だった。このアルバムが生み出されるまでどれだけの時間が、どれだけの作業が、どれだけのサンプリング・ソースが費やされてきたのか、ラジオでその片鱗を伺い知って途方に暮れてしまった。そもそもアヴァランチーズは、オーストラリアのメルボルンという英米と地理的距離と時差のある場所で生まれた、00年代にハミ出してしまった90年代の尻尾のようなグループだった。彼らはあれから、世界中に散らばった現在/過去のリズム・ミュージックを巡る「80日間世界一周」ならぬ「16年間世界一周」の旅に出て、まさにジュール・ベルヌ的な時間の流れの中で新世界にたどりついた。我々が聴いたことのない、シナトラと、〈モータウン〉と、ビーチ・ボーイズと、ビートルズの音楽が鳴っている新世界に。(宇野維正)

ドレイク等が立ち上げたレーベル〈OVOサウンド〉からは、エレクトロニックなR&Bの側からラップにアプローチしていったパーティネクストドア、ヴォーカル込みのセルフ・コンテインドなポスト・ディスクロージャー系のマジード・ジョーダンといった、それこそドレイク・サウンドの元ネタ的みたいな人たちがデビューしてきたわけだが、このdvsn(と書いてディヴィジョンと読ませたいようだ)の、サウンド担当のナインティーン85は、あの“ホットライン・ブリング”を含む『ヴューズ』のメイン・プロデューサー。確かに、そこでの彼の仕事は、ドレイクのキャラを引き立てるものではあったが、それはそれ、とばかりに、ここでは、相方でファルセットが自慢のダニエル・デイリーの歌(声)の旨味を引き出すことに専念。“アンジェラ”では、エリオット・スミスの“アンジェルス”をサンプルしたり、曲によっては、女性ヴォーカリスト複数を配して、ゴスペル感を高めたりと、覆面ユニットぽい打ち出し方を含め、キャラやイメージ抜きで成立させたいという自信が感じられる。(小林雅明)

このソロ・プロジェクトの主、ナタリー・メーリングがジャッキー・オー・マザーファッカーのメンバーだったことを知ると、たいていの人は相当に驚く。けれど、日本ではフリー・インプロ系、もしくはサイケ、フリー・フォーク系のバンドという認識が強い彼らも、少なくとも彼女が在籍していた00年代後半頃までは、ゴスペル、ソウル色を意識的に打ち出す側面も持っていた。ジャッキー・オーのそうしたブラック・ミュージック・テイストを静謐な歌に寄せたのがこのワイズ・ブラッド。中でもこの3作目は、フォーキーで神秘的な色彩よりも、例えばかつてのジョニ・ミッチェルがそうだったように、ジャッキー・オー時代から様々なアングルでチャレンジしてきたブルー・アイド・ソウル・ミュージシャンとしての凜としたプライドが静かに漂ってくる。ただ、その表現は決して外に向けられたものではない。あくまで自身の内側で焙煎、熟成させていこうとする試み。だから、同タイプと見られることも少なくないが、最新作で飛躍的に感情表現の幅を広げてみせたエンジェル・オルセンとは対照的と言える。でも、私はこの人のそうしたストイシズムに魅力を感じるのだ。(岡村詩野)

地元コンプトンを真っ赤に染め上げるYGのメジャー2作目。これまで一緒に数々のアンセムを作ってきたDJマスタードとは距離を置き、The HBK GangのP・ローやテラス・マーティンらとともによりダイナミックなサウンドを創り上げた。危険な香りを漂わせる“ドント・カム・トゥ・LA”や“フー・ショット・ミー?”は冒頭から張りつめた雰囲気を与えるし、テラス・マーティンがファンカデリックやザップをサンプリングしたウェッサイ賛歌“ツイスト・マイ・フィンガーズ”を聴けばYGの提示するスタイルが瞬時に分かる。ベイエリアの逸材であるカマイヤー、そして泣く子も黙るドレイクを迎えたシングル“ホワイ・ユー・オールウェイズ・ヘイティン?”や、ニプシー・ハッスルとともにアンチ・トランプを高らかに唱える“FDP”は高い話題性も伴い、YGのキャリアにおいても最重要楽曲となったに違いない。ケンドリック・ラマーらの語り口とは異なる、コンプトンのストリート描写を味わってほしい。(渡辺志保)
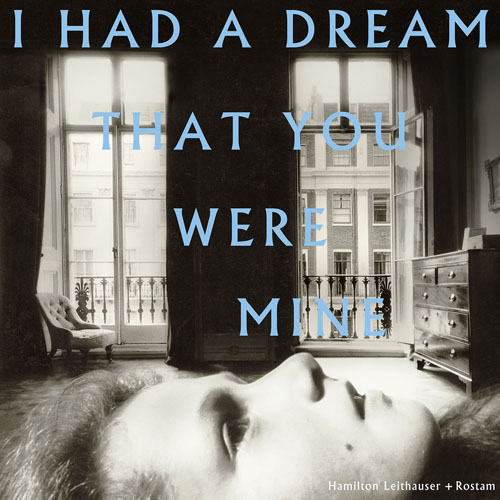
「バカげているのは勿論わかってるんだけど、僕はいつもレナードのことをものすごく近くに感じていたんだ」ーーレナード・コーエンの訃報をうけて、ハミルトン・リーサウザーはこんなコメントを残している。実際、彼がレナードから大きな影響を受けていることは本作を聞けば明らかだし、00年代以降、ザ・ウォークメンのフロントマンとしてニューヨーク・インディのダンディズムを体現してきた男は今、どうやら自らのルーツと改めて向き合っているようだ。簡潔にいうと、それは50~60年代にかけてのポピュラー音楽。それは前述したレナードの初期作を思わせるガット・ギターのフィンガリング奏法に限らず、ドゥーワップの楽しげなハーモニーや、管弦楽を用いた優雅なバロック・ポップにも及んでおり、そこにコラボレーターである元ヴァンパイア・ウィークエンドのロスタムがシンセサイザーなどを加え、現代的なミキシングを施すことによって、過去と今が交錯したアメリカの風景をここに浮かび上がらせているのだ。20世紀のポピュラー音楽史における生き証人たちが次々とこの世を去っていくなかで、彼らは確実にそのバトンを受け継ごうとしている。(渡辺裕也)

1992年、オークランドに生まれたカマイヤーは、まるでレンガみたいに巨大な携帯電話を持っている理由を「iPhoneよりも個性的で、私に合うから」と説明する。彼女曰く、TLCやアリーヤ、ミッシー・エリオットといった、影響を受けた90年代アーティストの象徴なのだそうだ。ただ、実際にはそのガジェットは80年代のモデルだろうし、ファースト・ミックステープにあたる本作も、再生した瞬間にバーナード・ライト“フー・ドゥー・ユー・ラヴ”(1985年)のイントロのループが聴こえてくる。確かにそれはLL・クール・J“ラウンジン(リミックス)”(1996年)やシェイド“テル・ミー”(1996年)でもサンプリングされているわけだが、全体的にはメイン・プロデューサーのCT・ビーツの仕事を始め、やはり80年代のテイストが効いているように思う。勿論、彼女のコンセプトに厳密な時代考証を求める必要などなくて、むしろそのサウンドと清々しいボースティングが、現在のポップ・ミュージックにおける女性像のステレオタイプに対するカウンターとなっていることに注目するべきだろう。なにしろ、カマイヤーは同世代の女性たちに向けてこう語っているのである。「レコードを売ったり、愛を手に入れるためにセックス・シンボルになる必要はない」と。(磯部涼)

2010年にドレイク“カラオケ”でそのメロディメイカーとしての才が世界中に知られることとなったフランシス・フェアウェル・スターライトは、その6年後、今度はプリズマイザーと呼ばれるハーモニー生成ソフトウェアの伝道師としてカニエ・ウェスト、チャンス・ザ・ラッパー、フランク・オーシャン、カシミア・キャットらの作品でフィーチャーされた。つまり、彼は2016年のポップ・ミュージックを瞬く間に席巻した良性ウィルスの発生源となったわけだが、その渦中にシェアしたのが、よく見ればセルフタイトルが冠せられたこの作品。全10曲30分強に様々な音楽的アイデアが凝縮された本作では、当然のようにプリズマイザーが駆使されているが、ヒップホップ系ミュージシャンの即物的な使い方(そもそもPファンクやザップの時代から黒人はボイス・エフェクトが大好きなのだ)と違って、とてもスピリチュアル。ソングライティングの作法や歌声に共通点を感じさせるかつてのピーター・ガブリエルやフィル・コリンズがソウル・ミュージックをロジカルに咀嚼していったように、フランシスはゴスペルのフィーリングを人工的に生み出すことで黒人音楽に接近してみせる。プリズマイザーは目的ではなく、そのための道具なのだ。(宇野維正)
2016年 年間ベスト・アルバム
21位~30位
2016年 年間ベスト・アルバム
扉ページ
