

かつてティペロの双子(エルヴィス・プレスリーと死別した双子の兄)について歌ったニック・ケイヴは自らの双子の息子のひとりを事故で失った。その事実をこの作品に必要以上に接続してはならない。だが、歌がどうしようなく生まれ、歌がどうしようもなく必要とされる場所は何処か。人がどんな知恵と努力を持ってしても打ち勝つことの出来ない万物流転の法則に打ちのめされた瞬間だろう。だからこそニック・ケイヴという作家はそんな瞬間にこの世に姿を現した信仰と神、愛と憎悪、罪と疫病、支配について歌ってきた。エレクトロニクス音楽とモダン・クラシックの手法を借りた、静謐かつ狂おしいバラッドが8曲。そこには荒涼とした無言の地平が拡がっている。社会の動乱を受け、いくつもの社会的なアングルを持った傑作が産み落とされた2016年。だがこのレコードは、この平和な街であろうと地球の裏側のアレッポの街であろうと、誰もが必ず向き合わねばならない薄暗い深淵から鳴っている。その深淵の奥底にある悲しみと苦悩の前でのみ、我々は初めて等しくなる。これを福音と呼ぶべきか。そして今年、世界はニック・ケイヴ最大のロールモデルであるレナード・コーエンを失った。道は続く。どれだけ呼んでも神は答えない。(田中宗一郎)
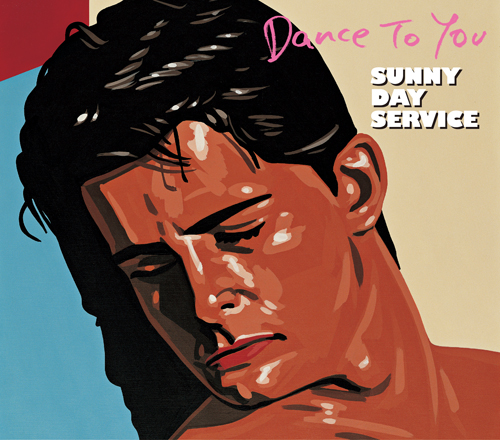
もし仮に今が「政治」の季節だとしても、「表現」がそんな下らないものに巻き込まれる必要はない。時代の動乱とファナティックな衝突がひたすら激化する中、社会的なテーマを持った傑作がいくつも産み落とされた2016年。サニーデイ・サービスだけはそんなものには興味はない、という振りをしてみせる。リリックの行間には傷跡に浮かぶ血のように幼児殺人事件や国会前デモ、いくつもの社会の歪みが滲み出しているものの、サウンドはあくまで涼しげなサマー・ブリーズを感じさせるダンス・フィールを持った2016年型AOR。社会について語りたいという誘惑からも、社会について語らねばならないという抑圧からも優雅に身をかわしてみせた。製作期間が延びに延び、予算が底をついたせいで決して録音状態はベストではない。メンバー3人は揃っていない。だが、それさえも表現の中に取り込んでみせた。わざわざ社会的なイシューを言葉にしなくても現実程度のものは描けてしまうんだとばかりに。社会など人が作り出した制度に過ぎない。政治など茶番だ。それ以前に人は時間や距離、重力といった物理に捕らわれている。弱くて、はかなくて、醜くて、かけがいのない、そのすべてを「2016年の今」というモチーフを使って描くことは出来はしないか。このレコードをレナード・コーエンやニック・ケイヴの作品の隣に並べよう。ポップ音楽とは歴史であり、社会の囚われものであり、だからこそ音楽は瞬間の刹那にしかない。我々の生もまた然り。春に咲き、夏に舞い散る。朝に起き、夜に咲く。命が芽吹き、命が舞い散る、永遠に終わりのない季節。そこでは生の官能だけが鳴っている。『DANCE TO YOU』はそんな実相を見事に切り取ってみせた。君は今もそこにいる。夢と過去に囚われ、またどうしようもないブルーな恋に落ちる。だらしない欠伸をしながら。どうやら終わりは来ない。生まれた場所、海に戻るにはまだ早い。(田中宗一郎)

肉声とデジタル加工された声、アコースティックとエレクトロニック、ルーツとモダン、生演奏とサンプリング、ヒップホップとドローン/アンビエントとロックとジャズとフォークとゴスペルと……そうしたありとあらゆる相反するものや断片化したものが、ここでは大量に現れてはただ共存しながら、ときにノイズを上げ、ときにハーモニーを奏でようとしている。これはとても真摯なコラージュ・アートだ。バラバラになったものや人がどうにかひとつの場所に集まって、それぞれの孤独と痛みを少しずつ分かち合いながら、味わったことのない音と感情を引き起こすこと。他者と共有出来る祈りを探り当てること。神の存在を信じてはいないが、一方でゴスペルの敬虔な響きに感銘を受けてきたジャスティン・ヴァーノンが自らの矛盾に向き合ったのがボン・イヴェールであり、本作はそのひとつのピークである。いま、無理解で隔離された者同士が、あるいは信仰によっても分断された人間たちが、それでもスピリチュアルな領域で共鳴し合えるのか。かつて山奥で歌っていた無名の青年のあまりに理想主義的な問いと実践が、ここでは苛烈なまでにいびつで美しい歌になっている。(木津毅)

リアーナがテーム・インパラの楽曲をカヴァーし、ビヨンセがジェイムス・ブレイクを自身の楽曲にフィーチャーする現在のUSシーンでは、メジャーとインディの垣根を越えたユニークな繋がりが音楽の進化を加速させている。ソランジュもまた、その越境性に可能性を見出だしている音楽家だといえる。そういった観点から本作を切り取ってみると、注目すべきはサウンドにおける「間」の有り方であり、そこからインディ・ロック的なものへのシンパシーが感じられる。本作にも参加しているデイヴ・ロングストレス(ダーティ・プロジェクターズ)や、ロスタム・バトマングリ(元ヴァンパイア―・ウィークエンド)のバンドに象徴されるように、ある種の「間」を意識したサウンド・デザインが一部のインディ・ロックに見られるが、本作からもそういった要素が聴こえてくる。USメインストリームのヒップホップにおけるオブセッシヴですらあるミニマリズムや、ネオ・ソウル的な粘り気のあるグルーヴとは異なる、どこか緩やかで乾いた「間」がそこにはあるのだ。この独特の音響感をソランジュは意識的に操っており、それは本作のオリジナリティの基盤であるような気がしてならない。(八木晧平)
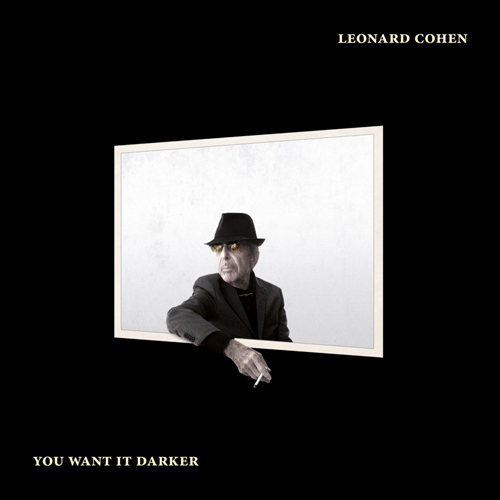
タイトル曲である一曲目で何度も繰り返される「Hineni」。ヘブライ語で「私はここにいる」という意味で、旧約聖書において聖徒たちが神からの呼びかけに答える時の言葉だという。そしてそれを聞いた神は人類に祝福を与えるのだ。それはまるで神への賛美である「ハレルヤ」という言葉と対になっているかのよう。だが、彼は決して神に服従してばかりではない。むしろ裏切り続けてきた人生でもあった。この曲では、まるで神に背いてきた闇だらけの日々が終わりに近づいていることを、まるで罰を受け懺悔するかのように綴っている。「覚悟はできている」と。女、酒、ドラッグにまみれた時代……ただ詩人として優れているというだけでは決して語れない、人として堕落した側面があったからこそ、このカナダ出身の82歳は最期まで魅力的だった。「なり代わってもかまわない人物が三人いる。ロイ・アキューフ、ウォルター・マッソー、そしてレナード・コーエンだ」。69年に知り合って以来何かと影響し合ってきた友、ボブ・ディランがかつて語ったあまりにも有名なこの台詞こそ、レナードへの最大の賛辞、謝辞であり、自分自身と友への最大の嘲笑なのだ。(岡村詩野)
2016年 年間ベスト・アルバム
1位~5位
2016年 年間ベスト・アルバム
扉ページ
