
>>>2016年のベスト・アルバム5枚(順不同)

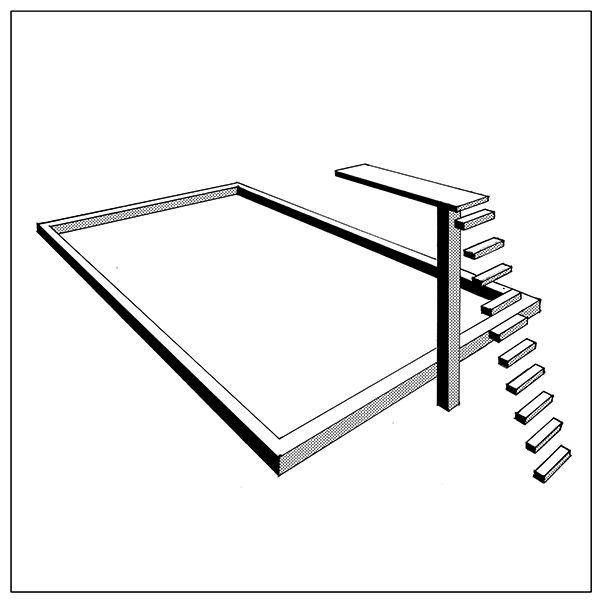

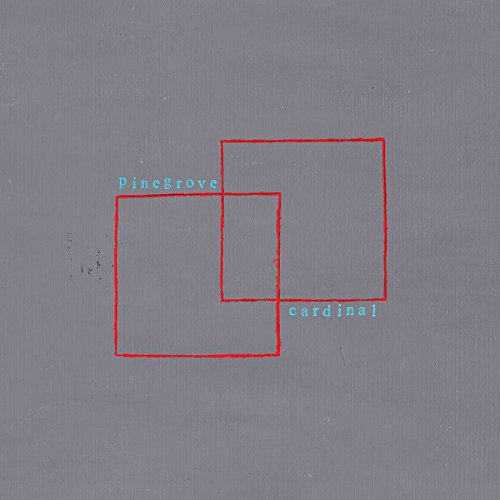

>>>2016年のベスト・ソング曲(順不同)
数年前の、あの熱気に満ちていた東京のインディ音楽シーンについて、その面白さとは第一にかれらの不定形で流動的な演奏のスタイルにあった、ことを思い出す。かれらは主にライヴの現場において、演奏のたびに人数やメンバーの顔ぶれを変え、楽器の構成や個々の持ち場を入れ替えたりして異なるアンサンブルを組み、結果サウンドの趣向さえもその都度さまざまに転じてみせる。アルフレッド・ビーチ・サンダル、王舟、oono yuuki、片想い、あるいは『My Lost City』の頃のcero……その背景にあったであろう個別の事情についてはさて置き、そうして演奏を重ねるなかでやり取りされる自由闊達なミュージシャンシップというものが、やれ海外の動向と安易に紐付されたり、やれ同時代性みたいなところに回収されたりしない、あの東京のインディ音楽シーンならではの豊かさを担保していた――というのが、当時観客のひとりだった自分には実感としてある。
たとえばボン・イヴェールやホイットニーのように、メインのソングライターがいて、アルバムや楽曲ごとにサポートのプレイヤーや楽器をフレキシブルに配置するかたちで行われるレコーディング・プロセス。あるいは、ノーネームやジェシー・ボイキンス三世といったヒップホップやR&B系のミュージシャンによるライヴ・パフォーマンスの映像から窺える、フリースタイルでオープンマインドな空気に溢れた生演奏。そうしたかれらが繰り広げる光景とは、かつての東京のインディ音楽シーンの担い手たちが見せていたそれと自分の中では重なるところがある――と言ったら、個人的な体験に引き寄せすぎだろうか。
こと欧米の音楽シーンにおいては、いわゆる「ロック・バンド」的な、すなわち固定されたメンバーによる「バンド音楽」のプレゼンスが低下して云々といった物言いがされてかまびすしいこの頃。対照的に、昨年2016年に支持を広げた件のアーティストらがとるスタイルとは、もっと縛りの緩い、フットワークが軽くて人の出入りが自由なコレクティヴとかのイメージに近いものなのだろう。はたまた、LAFMSのジョー・ポッツが言うようにそれは、単純に「友達の輪」なのかもしれない。
ただし――こじつけを承知で言えば、それがコレクティヴであれ友達の輪であれ、その場面場面で行われているのはまぎれもなく、ひとつの「バンド演奏」であり、「バンド音楽」でもある、という事実。そして、であるならばその一点において、かれらと「ロック・バンド」は本質的なところにおいて何ら変わるものではないのではないか、とも。いや、ソングライターや演奏者の探究心やフレッシュなアイデアというものがそこに注がれ続けるかぎり、「ロック・バンド」という形式はそうやすやすと汲み尽くされるものではない、と考える。
むしろ伸び代しか感じなかったオウガやミツメのニュー・アルバム。まだ何者でもないクラン・アイリーン。高橋翔は新バンドのELMERで、昆虫キッズが締め括った青年期の終わりの、その先を描こうとしている。東京のインディ音楽シーンのキーマンズにして最大のクエスチョンマークだったホライズン山下宅配便の解散をへて伴瀬朝彦が新たに関わるcooking songsは、あの「豊かさ」――かれの言葉を借りれば「引き出しの引き出し合い」――を今も体現し続けているようだ。そして、ディグローは今もっともアルバムが待ち遠しくてたまらない「ロック・バンド」のひとつである。
海外では、パーケイ・コーツ、パイングローヴ、ホテリアー、ウィーヴスが印象に残った。なかでもパーケイ・コーツのアンドリュー・サヴェージは、レーベル運営やプロデュース業を通じて地元の〈セイクリッド・ボーンズ〉や〈メキシカン・サマー〉周辺の若手とも繋がる、ブルックリンの次の顔役となりえる人物。かの地に新たな波を起こしてくれるのではないか、と期待している。
〈サインマグ〉のライター陣が選ぶ、
2016年の私的ベスト・アルバム5枚
&ベスト・ソング5曲 by 渡辺志保
2016年
年間ベスト・アルバム 75
