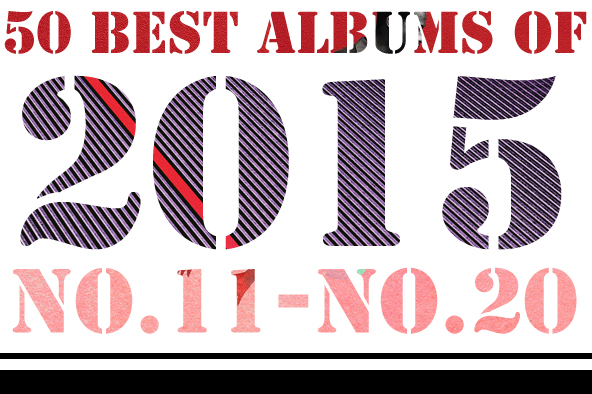

この男、60年代からタイムスリップでもしてきたのか? そんなあり得ない疑問も頭に浮かぶほど、レオン・ブリッジズのデビュー作は50~60年代ソウルへのオマージュですべてが彩られている。アナログな音色への徹底したこだわりは、とても現代に生きる26歳の青年とは思えないほどだ。だが、ネット・ラジオや動画サイトを通してサム・クックを発見したという彼にとって、これは決して安直なノスタルジーでもコスプレでもない。例えば、“リサ・ソーヤー”では1963年生まれの彼の母親を主人公に、当時の黒人たちの慎ましい暮らしを歌い、“ツイスティン・アンド・グルーヴィン”ではさらに時代をさかのぼって、祖父と祖母のナイトクラブでの運命的な出会いがモチーフに。最終曲は、アメリカ南部のカルチャーにとって象徴的な意味を持つ「河」をタイトルに冠した、慈愛と救済のゴスペル・ソングだ。数多の支流が流れ込むミシシッピ川のように、レオン・ブリッジズは自身のルーツを辿るパーソナルな探訪の旅を、偉大なるソウル・ミュージックの大河へと注ぎ込み溶け合わせることで、この思慮深くソウルフルなレコードを作り上げた。(青山晃大)

「あんた、自分が間違ってるのわかってるでしょ。いい加減にして、ゆうべの居場所お見通しよ」と、1曲目から「バカね」(それが、そのままタイトルに!)と浮気男をなじる曲で始まるので、表題通り「リアリティ・ショウ」感覚満載で「スーパー行く時もマスカラ付けなきゃいけなくて大変」と歌う次の曲も?と思いきや、特定の一人の女性による「同性の共感を呼ぶ熱い」一人称語りではなく、様々な女性の主観/視点が交錯していて、複眼的な視点で歌われていることが、アルバム全体の特徴の一つになっている。ジャズミン・サリヴァンの歌そのものは、90年代後半過ぎのR&B風(と書いたら「正統派」と受け取ってもらえるだろうか?)なのに、トラックは、明らかに打ち込み主体。ただし、曲ごとにその音色に細心の注意が払われているため、歌力では彼女に負けないビヨンセが、2年前にアルバムの大半でやっていたような強引さを微塵も感じさせないあたりも、何度聴いても飽きさせない魅力につながっている。R&Bリスナー以外の音楽ファンをも引き込んだ上で、2015年における「オーセンティックなR&B」とは何か?と、自信に満ちた問題提起を行なっているかのようだ。(小林雅明)
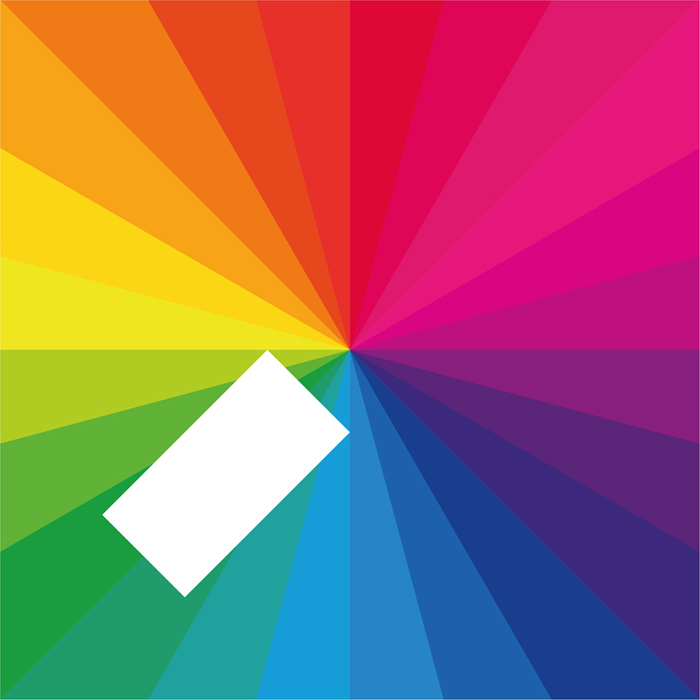
クラブやパーティに日常的に行かない音楽ファンにとって、これほど理想的な「ダンス・ミュージックのレコード」は他にないのではないか。70年代のソウル・ジャズから90年代のレイヴ・サウンドまでが走馬灯のように揺らめいている今作には、「時代」もなければ「現場」もない。ダフト・パンクが『ランダム・アクセス・メモリーズ』で提示してみせたような、ディスコ・ミュージックを軸とした「歴史」に対する視座もない。ひたすらアゲまくるだけのEDMの時代に突然現れた、ダウナーでメランコリアに包まれた桃源郷としてのダンス・ミュージック。重要なのは、それがジェイミー・スミスの幻想や妄想から生まれたものではなく、ニーズが加速し続けるバンド活動の傍ら、それでもDJとして各国のフロアを精力的に回ってきた彼の体験とそこで見てきた風景から生まれたものであることだ。根っこの部分では引きこもり志向を持つ音楽家が、世界中で激動の日々を過ごした後に、またスタジオにこもって丹念に作り上げた作品。音楽的にはどこも新しくないのに、2015年最高のサウンドトラックに成りえている理由はそこにある。(宇野維正)

アルバムのオープニング・トラック“レット・イット・ハプン”に、あなたは何を思うだろう。聞き様によっては開き直りとも受け取られそうな、この「起こるがままに任せてみよう」というタイトルから、テーム・インパラ(=ケヴィン・パーカー)が示そうとしたのは、恐らく「変化は起こるべくして起こる」ということなのではないか。つまり、エレクトロニクスを大々的に導入したことも、クラブ・ミュージック的なフォーマットが加わったことも、すべては必然なのだ、と。一方で、本作の最後を締めくくる“ニュー・パーソン、セイム・オールド・ミステイクス”のタイトルとリリックで示されているように、ひとは過ちを繰り返す生き物でもあるし、その判断が周囲から受け入れられないことも、時にはあるだろう。それでいて、我々は現状にとどまり続けることができないのも、また事実。だからこそケヴィンはみずからの創作意欲に従い、それまでのサイケデリック・ロック的なアプローチから離れることを決意。以前から関心を示してきたモダンR&Bへと接近し、ついにはあの素晴らしき『ローナイズム』さえもしのぐ傑作を手にしたのだ。(渡辺裕也)

2010年代に入り大挙した女性のエレクトロニック・アーティストのひとり。と、十把一絡げに扱われた数年前までの評価からは隔世の感さえ覚えるほど。いや、その名前が取り沙汰され始めた頃にはすでに他と一線を画する多彩な素養と豊かな作家性を披露していたことは『エクスタシス』(2012年)以降の近作が物語るとおり。4作目の本作は、そうして積み上げられてきたキャリアの頂に置かれてふさわしい。ギリシャ悲劇やミュージカルを下敷きとしたコンセプチュアルな仕様も伴った前作『ラウド・シティ・ソング』に対して、アメリカーナ~スタンダードなシンガー像も再発見させる堂々の歌いぶり含めてこれまでのディスコグラフィからすれば「ポップ・アルバム」と躊躇いなく呼べてしまうだろう本作。しかし勿論それだけではない。クラシック音楽の才媛らしい管弦楽器の微に入った構成。そしてUSアンダーグラウンド仕込みの(控えめながら)趣向を凝らした音の造形。あるいは“ヴァスケス”の――〈ストーンズ・スロウ〉周辺やLAビート人脈との交流を裏づける熟れたグルーヴ。つまり、ここにはホルターの音楽的な美点が凝縮され、かつ、さりげなくも周到に尽くされている。(天井潤之介)

「ファック・ギャングスタ・ラップ!」。2015年を代表するラップ曲の一つ“ノーフ・ノーフ”の一節で、LAはロングビーチのラッパー、ヴィンス・ステイプルズは、自らの立ち位置をこう表明している。親も、近所の連中も皆ギャングだったから、自分も正式にギャングに入ったものの、2006年の夏(=表題)に、ギャング間の抗争で多くの仲間を失い、終りの始まりを迎えた、という生い立ちからなのか、ここには、景気よく銃をぶっ放すような紋切り型は皆無。だからといって、反ギャングを唱えるわけでもない。ツッパってるのではなく、妙に醒めているのだ。それでいて、大文字の「ブラック・ライヴス・マター」ではなく、「ラヴ・ウィル・テア・アス・アパート」の過去形を大きな教訓に、彼自身が体験した何通りかの「愛」についての検証も行なっている。そんな一癖ある彼の態度に、(『イーザス』にも参加した)ノーI.D.を中心に、クラムス・カシーノ、(ケンドリック作品でお馴染の)DJダーヒー等によるビートも十全に応え、その結果、全く一筋縄ではいかない楽曲ばかりが並び、聴く者に「アンノウン・プレジャーズ」をもたらすという意味でも、ジャケに偽りなし。(小林雅明)

『イリノイ』に収録された痛切なフォーク・ソング“ジョン・ウェイン・ゲイシーJr”でスフィアン・スティーヴンスは実在した殺人鬼の心情にじわじわと同化していたが、ちょうど逆のことがここでは起こっている。「昔むかし」……両親の名前を刻んだタイトル・トラックをそんな風に「お話」として始めてしまうことは、彼の危うい生き様か作家性か。実母の死を契機とした幼い日の記憶にまつわるこの極めて個人的なレコードは、同時にアメリカの片隅で埋もれそうになっているすべての小さな生を、繊細な震えとして浮かび上がらせる。なぜ彼が大地に埋もれていた伝承としてのフォーク・ソングを掘り起こし続けてきたか、その答えがここにはある――スフィアン少年、彼自身が誰も見向きもしない悲しみをあらかじめ負っていたからだ。それは豊かでも勇ましくもない貧しくか弱いアメリカの、しかし想像力に満ちた悲しみだ。「僕の安らぎになって、僕のファンタジーになって」……彼がそう囁くとき、この歌たちはふとあなただけの「お話」として寄り添ってくるだろう。微かな音で演奏されるフォークとエレクトロニカに耳を澄ませば、そこでは消え入りそうな愛が息づいている。(木津毅)

『ゲーム・オブ・スローンズ』に『フォースの覚醒』他モダンなファンタジー巨編が大人気を博す今の時代にふさわしい、LAのコンテンポラリー・ジャズ界から放たれたCD3枚組~計3時間弱の大作。本人が話していたコンセプチュアルな「物語」の筋はやや曖昧ながら(本作はいずれグラフィック・ノヴェル化されるらしいのでそちらで補強できるか?)、アコースティックからフリーに至るジャズの太い幹にソウル/ファンク/ヒップホップ/エレクトロニック……とブラック・ミュージックの諸相が豊かに厚く編み込まれていく様そのもの=音楽による勇壮なオデッセイが本作のステイトメントなのではないかと思う。結果としてサン・ラやフェラ・クティ、マグマらに通じるスピリチュアルで深遠な小宇宙を形成しつつ、どの楽曲もメロディックでリズミックな快に満ちたアクセスしやすさを維持しているのは見事。彼もゲスト参加したフライロー『ユー・アー・デッド』やケンドリック・ラマー『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』は勿論、アフリカン・アメリカンの歴史を12作を通じて辿る意欲的なプロジェクト『Coin Coin』を押し進めているマターナ・ロバーツとも根底で共鳴する、ポジティヴな光を2015年に送り込む1枚だ。(坂本麻里子)

日本で本作を語る際になぜか必ず語られる、“ボアド・イン・ザ・USA”の「アメリカが僕にくれたのは/無駄な教育とサブプライム・ローン」という一節。ブルース・スプリングスティーンの“ボーン・イン・ザ・USA”をもじったタイトルも含めて、それ自体は決して上手いとは言えないし、むしろ稚拙だとすら思えるが、それ以上に本作が素晴らしいのは、その強烈なキャラクターやステージ・パフォーマンスにやや遅れを取っていた感もあるファーザー・ジョン・ミスティ=ジョシュ・ティルマンのソングライティング・センスが、見事なまでに狂い咲いていることだ。“シャトー・ロビー #4”や“ストレンジ・エンカウンター”といった曲のメロディは、2012年の来日公演を最後に彼が脱退したフリート・フォクシーズを即座に連想させるものだし、ここにはバンドの2ndアルバム以上に、フックのある曲が収められている。ジャケットのアートワークよろしく、中世の絵画の世界に、急に現代的なモチーフや、歌っているティルマン本人がヌッと顔を出す奇妙な感覚。映画の書き割りが倒れて目の前に現実の世界が広がる、そんな鮮烈な瞬間が何度も訪れる傑作だ。(清水祐也)

ヴェト・コンと並び、感情を害しやすいネット族(面の皮が薄いのか?)から字面だけで「女性蔑視」と赤旗を上げられそうなバンド名を名乗るダブリン発のノイズ・フリーク4人組。勿論、女性メンバーはいないし、ポップ・バンドでもないスクリームぶり=おバカな冗談であることは、このご機嫌にフリーキーで不穏にささくれたアンチ・ミュージックを聴けばすぐに分かるはずなんだけども。結成は4年前で、既にEP/シングルは多数発表済み&ライヴの評価で足がかりを掴んできた実直派。だが、ある意味国内で自足しているアイルランド・シーンに身を置いてきたおかげで、インディ青田刈りのレーダーに引っかかることなく彼らが自由に音世界を伸ばすことができたのは本デビュー・フル・アルバムに吉と出ている。サウンドの類似性という意味ではノーウェイヴや80年代USハードコア~マス・ロックを指摘できるとはいえ、一見やりたい放題なカコフォニーの中にテクノやダンス音楽のミニマルな反復およびビートからの影響を混ぜ込む手際によって、他にない個性=踊れるノイズ・ロックを造成。ダークなユーモアも含め、ザ・フォールの正しい末裔がやっと登場した感。頼もしい。(坂本麻里子)
「2015年 年間ベスト・アルバム 6位~10位」
はこちら
「2015年 年間ベスト・アルバム 50」
はこちら
