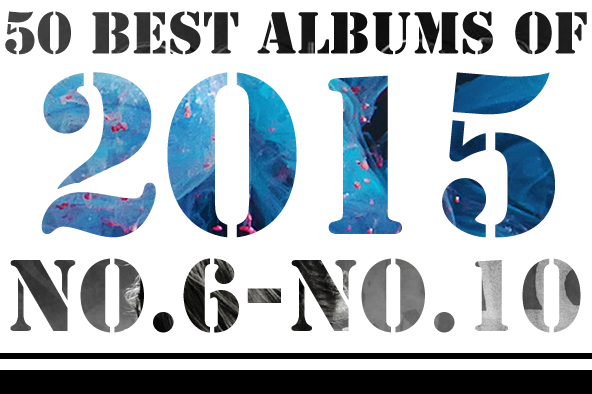
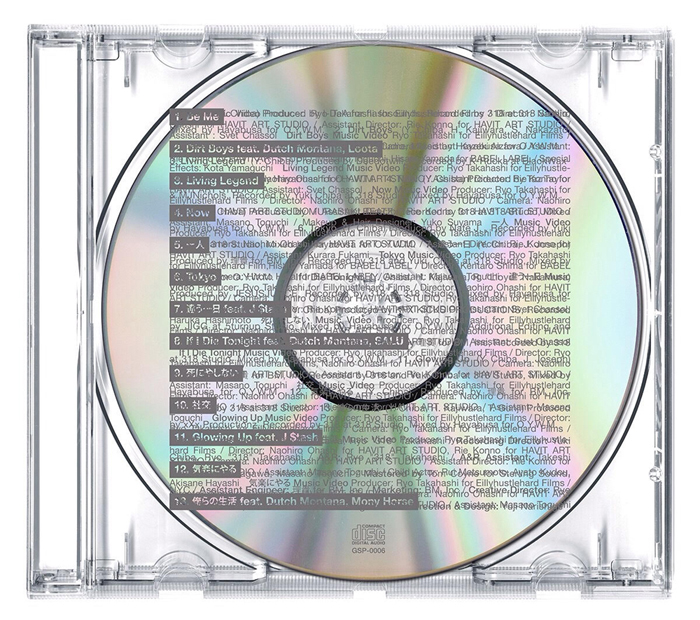
KOHHは飾り気のない言葉を通して様々な顔を見せる――ナイトクラビングを楽しむチャラいプレイボーイ、マリファナでリラックスする姿、ファッション・ラヴァー、額に汗を浮かべた日雇いの労働者、王子のストリートに生きる者、兄や息子としての自分、そしてピュアなアーティスト。ボースティングをキメながらも迷いや葛藤、アンチノミーを包み隠さず曝け出す。その危ういまでのストレートフォワードなアティチュードの言葉こそが彼そのものである。ヤング・サグの“ユー・ワナ・ビー・ミー”か、あるいはチャンス・ザ・ラッパーとソーシャル・エクスペリメントの“ワナ・ビー・クール”へのアンサー? とにかく冒頭の“Be Me”に持っていかれる。いきなりシリアスだ。「マジ、誰のことも信用しないって思ったことは何回もある/自分で壊す/勝手にもがく/他人のせいにしちゃったら全部が終わる/全部が終わる前に楽しみたいだろみんな」。『DIRT』は「生と死」を巡るアルバムだ。「死んだら意味ない」「明日なんていらない」とKOHHは言い切る。でもそこにはやっぱり逡巡が含まれている。だからこそKOHHのラップは多くの人を魅了し続けるのだろう。(天野龍太郎)

何度しくじり、無様な姿を見せたとしても、再び立ち上がればいい。決して遅すぎることなんてないのだから――このアルバムから受け取れるメッセージがあるとすれば、つまりはそういうことだ。若干15歳でトップ・スターの座に上り詰め、その急激な成功の反動から身も心もズタボロになってしまった若きプリンス。しかし、ここにいるのは、もう「哀れなアイドル」ではない。音楽で自分自身を証明することを静かに決意した、一人の立派なアーティストである。復活の烽火を上げたジャックUとのコラボ曲“ホウェア・アー・ユー・ナウ”や、キャリア初の英米1位を獲得した“ホワット・ドゥ・ユー・ミーン”を筆頭に、トロピカル・ハウスなどの最新トレンドをいち早く取り込んだポップ・ソングの完成度は高く、これを機に人々の見る目は否応なしに変わるだろう。リリックは赤裸々な心情の吐露が多いが、本作に賭ける彼の想いは、(表面的には恋愛の歌である)アルバム屈指の名曲“ソーリー”からも伝わってくる。「今夜/僕に償いをさせて/2度目のチャンスに賭けてみたいんだ」。そう、諦めない限り、チャンスは何度でも巡ってくる。そしてジャスティンは、そのキャリア史上もっとも大きな賭けに勝ったのだ。(小林祥晴)

表題の『DS2』とは“ダーティ・スプライト2”の略で、フューチャーの成功への足がかりとなった2011年のミックステープ『ダーティ・スプライト(=コデインのスプライト割り)』にあやかったのだろう。この通算三作目のアルバム発表以前に、わずか半年の間に、アルバム水準の質の維持を主題に、厳選した楽曲のみで構成されたミックステープを三作発表し、そこで充実した仕事を残したビートメイカー(である以前にミュージシャン的資質を持ち、ありがちなアトランタ・トラップには仕上げない)メトロ・ブーミンに、本作収録曲のほとんどを任せたという念の入れよう。と同時に、シアラとの別離後初のアルバムでもあり、2013年の前作『オネスト』での、あのエモすぎるオートチューンに結晶していた「愛は盲目」な感じが、ドラッグ(各種タイプの使用は勿論、精製、取引、それに絡む銃や暴力)、カネ、セックスに入れ替わり、古き佳き? フューチャーが蘇えった。『ダーティ・スプライト』から4年の間に、彼らが曲で煽るあまり、常用者が増え、流通が制限され、今では入手困難になってしまったコデインのように、魅力的かつ希少価値なものがここにあると言いたげだ。(小林雅明)

ずっと昔からロックンロールがそうだったように、コートニー・バーネットは、「他人と一緒でなくてもいい」ということを教えてくれる。左利きでフェンダー・ジャガーを弾いているのに「コートニー」という名前でも構わないし、エレキ・ギターをピックで弾かなくたっていい。女の子が女の子を好きになったって構わないし、健康を気にして有機野菜を食べなくたっていい。時には考えてみるのもいいし、そこに座っているだけだっていい。そもそも彼女の住んでいるオーストラリアでは、アロハ・シャツを着たサンタクロースが、真夏にサーフィンしながらやってくるのだ。どこにも行けない人たちをエレベーターになぞらえた“エレベーター・オペレーター”や、車に轢かれた動物たちを描いてキャピタリズムを批判した“デッド・フォックス”。銃に怯えて銃を取る代わりに、彼女は言葉の散弾銃を放つのだ。その行間から零れ落ちるのは、ちょっぴり歪んだシンキング・ウーマンズ・サイケデリア。ボブ・ディランが、ロビン・ヒッチコックが、そしてボビー・ギレスピーが着ていたあの黒と白のポルカ・ドット・シャツに、今はコートニー・バーネットが袖を通している。(清水祐也)

2015年に発表されたレコードのなかで、これほど自分の耳を楽しませてくれた作品は他にない。解像度が高い各パートの録り音。余白を存分に活かしたエフェクト処理。『サウンド&カラー』から聞こえてくる音は、とにかくそのひとつひとつが圧倒的にクリアなのだ。通常、ブルーズやサザン・ソウルの録音といえば、そのルーツに倣ってヴィンテージな質感を捉えたものが正解とされがちだが、本作の洗練されたサウンド・プロダクションは、そうした常識をいとも簡単に覆してしまったのだから、これを驚異的といわずしてなんと言おう。それでいて、彼女たちは伝統的なブルーズと距離をおいたわけではなく、むしろソングライティングそのものは非常にオーセンティック。そう、ここには過去への憧憬と理解があるだけでなく、それを自分たちの手で更新させようという強い意志がある。ホワイト・ストライプスの『エレファント』が世に出てからちょうど一回りした時期に、ブルーズがまたしても時代性を取り戻した。『サウンド&カラー』を聴いていると、そんな実感がこみ上げてくる。(渡辺裕也)
「2015年 年間ベスト・アルバム 1位~5位」
はこちら
「2015年 年間ベスト・アルバム 50」
はこちら
