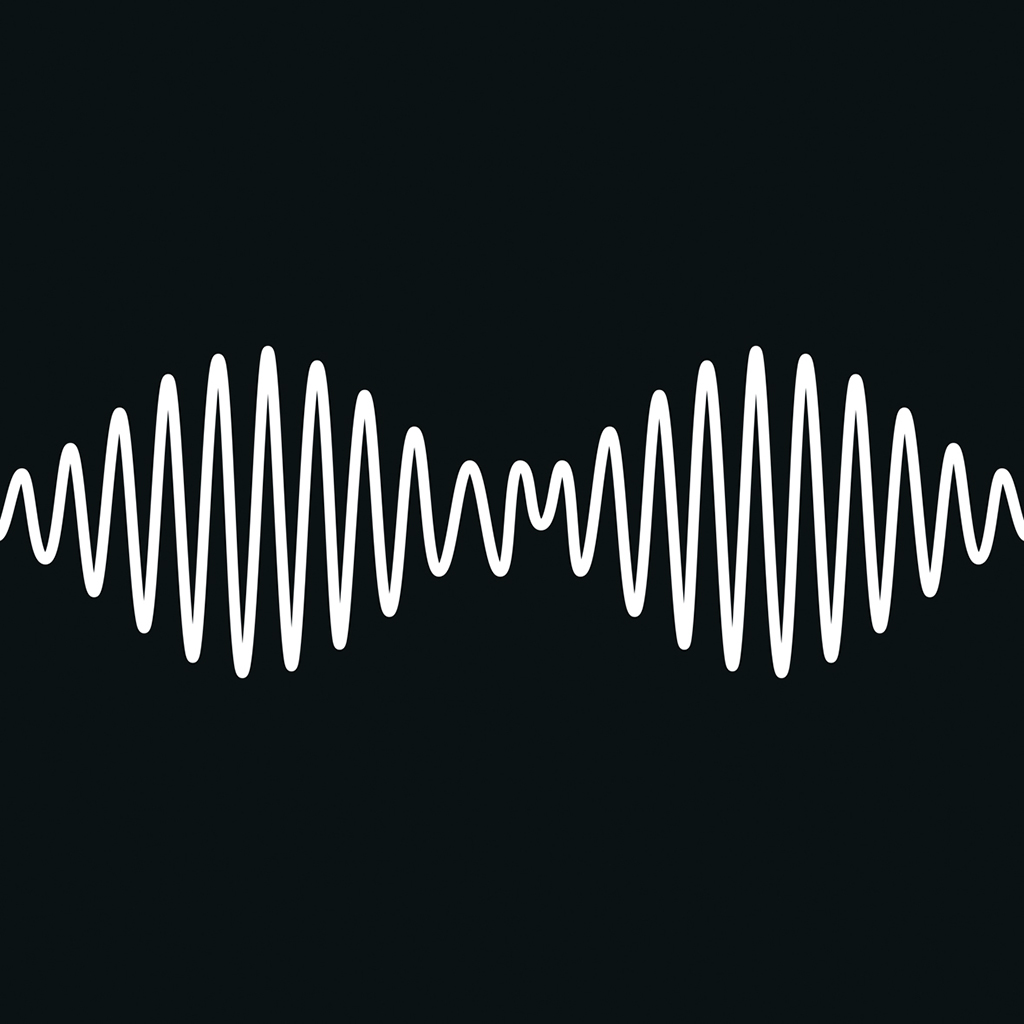
床を踏みならしたり、膝を叩いた音を混ぜ合わせて作り出したファットな響きのキックとスネアに、不穏な旋律の単音リフとベースがぎこちなく絡みついてくる。bpm84。美しい青空を見上げることなど一度も思いついたこともない盲目の蛇が、床をずるずるとうねりながら進んでくるようなヘヴィなビート。ハットとベースで裏拍を刻むだけですぐさまビートは跳ね出すことなど知りつくしているにもかかわらず、そんなつもりは毛頭ない。これから先、心が弾むことなど二度とないだろうと意固地に決めつけたかのような、バウンスを拒んだファンクネス。そして、悪い酒にすっかり飲まれてしまった男の独白が始まる。「俺が這いずりまわるようにして帰る場所はお前なんだ」。リリックが描き出すのは、世界でもっとも惨めで、もっとも勘違いした存在であるオトコという生き物のカリカチュアだ。その後ろを固めるのは、おそらくは昨今のR&Bのヴォーカリゼーションや、カニエ・ウェストの『808s & ハートブレイク』以降のオートチューン・ヴォイスを彼らなりに変奏したつもりのファルセット・コーラス。それはまるでメフィスト博士の愚行を嘲笑う天使たちのいたずらな笑い声を思わせる。このアルバムは、自嘲と自己保身、プライドと自己嫌悪が同じ意味を持っているような不思議な場所から幕を切って落とされる。この完璧なオープナーから一度たりとも弛緩することなく、最後まで一気に聴き入らせてしまう完璧な42分38秒。遂にこのバンドは、偉大すぎる1stアルバムの呪縛からも解き放たれることに成功した。いや、勿論、もしあなたがこのアルバムに少しもピンとこなくても別に悪いことじゃない。背伸びする必要などない。このレコードを棚にしまって、もう少しだけ無邪気で幸福な子供時代を楽しめばいい。
至極乱暴に言うなら、この『AM』というアルバムの音楽的な軸になっているのは、ヘッドフォン作りで巨大な富を生み出す遥か以前のドクター・ドレが得意とした重低音ファンクをギター・コンボによって再構築し、あろうことかブラック・サバスの重低音リフをそこに乗せるという、米国ウエストコーストと英国ミッドランドそれぞれが誇るヘヴィネスをぶつけ合わせた、ありえないハイブリッド・サウンドだ。それゆえ、徹頭徹尾ヘヴィ。ブラック・サバス不朽の傑作“ウォー・ピッグス”のリフを大胆に拝借した“アラベラ”には、ご丁寧にもトニー・マイオミの音色で、イーグルスの“ホテル・カリフォルニア”とドアーズの“ファイヴ・トゥ・ワン”それぞれのフレーズを引用した、ちょっとした悪ふざけさえある。そう、このバンドが笑いを忘れたことは一度もない。いずれにせよ、このアルバム全体を覆っているのは、米国ウエストコーストを思わせる渇いた虚無と、英国ミッドランド特有のよどんだ退廃だと言っていい。
マイク・スキナーが少しばかり足踏みをしている間に、その愛弟子的存在だったはずのアレックス・ターナーは、英国人特有のライムを代表するリリシスト/ヴォーカリストへと成長した。このアルバムにおける彼は、米国のヒップホップMCに対抗出来る数少ない英国人のひとりになった。そして、リリックで綴られているのは、「失われた週末」期のジョン・レノンを思わせる、愛する女性に見限られ、消えない後悔と執着心に苛まれる、惨めで自堕落ですっかり荒んだ孤独の風景だ。だが、リリックのトーン&マナーは、映画やポップ・ソング――さまざまなポップ・カルチャーからの引用によってユーモラスに語られるものあり、『ブロンド・オン・ブロンド』期のボブ・ディランやビートルズ後期のジョン・レノンにも似たシュールリアリスティックなもの――すっかりトリップして、ストーンした歌詞とも言える――あり。いずれにせよ、キャラクター自らの愚行を嘲笑うようなメタフィジカルな視点を持ったもの。それゆえ、湿った自己憐憫はここにはない。あるのは、むしろ笑いだ。
例をひとつ挙げよう。歌詞が手元にないなら、まずはアルバムからの先行カット――アルバムの基調に準じたヘヴィなファンク・トラック“ワイド・ユー・オンリー・コール・ミー・ホェン・ユア・ハイ?”の日本語詞付きのヴィデオを見ればいい。タイトルは「なんでクスリでぶっ飛んでる時しか電話してこないわけ?」――つまりこれは、もっともやってはいけないことを、もっともやってはいけないタイミングでやってしまうことについての曲。身に覚えのある男性諸氏も少なくないだろう。Eやアシッドをキメた後で自分がひどい飛び方をしていないか、鏡で何度もチェックしながら、よせばいのにテキーラでさらに追い討ちをかける――そんなどうにもキマらない夜。そして、そんな風に自分自身がどうにもならなくなっているのに、意中の女性にまるで相手の安否を気づかっているようなメールを送り続ける。墓穴を掘るとは、まさにこのこと。ヴィデオ・クリップの最後には、17通の着信とメールを残した相手の携帯には、「アレックス、バンドやってるガキ」としか登録されていないという最高のオチまでついている。ドラッグあるある、恋愛あるあるの見本のような見事なストーリーテリングだ。
アルバム全体に話を戻すなら、冒頭の4曲はとにかく完璧。その後、グラム・ロック風のブギー“アイ・ウォント・イット・オール”をちょっとした箸休めに、A面最後にはまた別のハイライトが待っている。ジョン・レノンが得意とするトニック・コードの5度の音を半音づつ上げていくというコード進行を使った50年代ロッカ・バラッド風の“No.1パーティ・アンセム”がそれだ。オーセンティックなソングライティングに初めて本格的に取り組んだ4thアルバム『サック・アンド・シー』スタイルの完成形とも言えるこの曲は、「自分を汚したい夜」をひたすらロマンティックに鳴らすことで、むしろすっかり自暴自棄になったキャラクターの孤独と惨めさを際立たせるというアクロバティックな仕掛けを持っている。
アルバムB面はさらにヴァラエティに飛んでいる。軽くシャッフルするビートとスキット・コーラス、甘いメロディとコードがどこかルー・リードの“サテライト・オブ・ラヴ”や“ウォーク・オン・ザ・ワイルドサイド”を彷彿させる“マッド・サウンズ”もあれば、エンニオ・モリコーネ風の“ファイアーサイド”もある。どこか最初期のドゥルッティ・コラムを思わせる“アイ・ウォナ・ビー・ユアーズ”ではデビュー時からアレックス・ターナーがその影響を公言してきたポストパンク詩人、ジョン・クーパー・クラークが歌詞を書き下ろすというサプライズもある。いずれにせよ、前述のヘヴィ・ファンクを基調にしながらも、サウンドの幅も持たせた、統一感と聴き手を飽きさせない見事なフロウを併せ持った、文字通りの傑作だ。
だが、もしかすると、この新たなヘヴィ・サウンドや彼らの最近のロッカー風のヴィジュアルのせいで、何もかもがすっかりマッチョになってしまった、と感じる者もいるだろう。だが、実際のところは、むしろ逆。そもそも男が髪を油で撫でつけ、皮を着込み、黒で武装するのは、自信のなさや不安を隠すため。「失われた週末」期の、すっかり自信をなくしたジョン・レノンがハンブルグ時代の写真をアートワークに使い、往年のロックンロールのカヴァー・アルバムを作ったことを思い出せばいい。だが、むしろここでのアレックス・ターナーは、サウンドとリリックの巧みな組み合わせによって、無益なマチズモで武装することで精一杯自分自身の弱さを隠そうとする男たちのカリカチュアを描き出し、そのことによってマチズモそのものを相対化させようとしている。まるで、レノンのようにわざわざハウス・ハズバンドにならずとも、ユーモアや皮肉さえあれば、マチズモは克服出来るのだ、と言わんばかりだ。
女やゲイに比べれば、何世紀にもわたってずっと社会的に甘やかされてきた男という生き物は、いつまで経っても成長しない場合が多々ある。でも、まあ、成長した男ほど退屈なものもないしな。と、最悪のエクスキューズを用意しているのが、男の甘えなのは言うまでもない。実際、男にとっての唯一の成長というのは、そうした自らの愚かさを対象化出来るかどうか――実際、その程度のものだろう。そして、アークティック・モンキーズは、この『AM』において、見事にそれをモノにしている。1stと2ndが無邪気な子供時代についてのアルバムだったとすれば、3rdアルバム『ハムバグ』は大人の男に憧れる子供のアルバムだった。4thアルバム『サック・アンド・シー』は成長の痛みとビターネスを真正面から扱っていた。だが、『AM』は大人の男も所詮は子供でしかないことを嫌と言うほど思い知らされた、ほんの少しだけ成長した大人のアルバムなのだ。
この『AM』は、間違いなく2013年にリリースされたすべてのアルバムの中で、もっともユーモラスで、もっとも笑えるアルバムだ。でも、聴き手に涙を流させるのは簡単だからね。誰もが抱える痛みのひだを少しばかりくすぐってやりさえすればいいだけのこと。だが、痛みの核心を一直線に射ぬいた時にしか、笑いは生まれない。
彼らのいいリスナーとは言えない自分が不思議に思うのは、今も続くジェームス・フォードの重用だ。2ndでバンドの初期衝動に次の手を示し、同時代のシーンに導線を引いたフォードの功績は大きい。が、フォードのそもそもの音楽的な出自、やはりダンス・ミュージックに軸足を置いた近年の仕事と、とくに3rd以降のサイケデリック・ロック化したバンドの音楽志向とのズレ。逆に、その3rdへの制作参加を機に交流を深めていくクイーンズのジョシュ・オムとの音楽的な共鳴とは対照的であり、しかも今ではメンバー全員がLAに移住したと聞く彼らは、もはやアメリカのバンドといっていいのかもしれない。
メタリカを唸らせ、13thフロア・エレヴェーターズも彷彿させるリズム&ブルースとガレージ・サイケの混交を見せた3rd以降の重量化の背景に、アメリカン・ロックの暗部と深淵を体現するオムの手引きがあったことは間違いない。ロックンロール固有のグルーヴを追求するように原点回帰的な装いで登場したはずの彼らは、しかし、同時期の2000年代後半に台頭した折衷主義的なギター・ロックよりも実はハイブリッドで、かつ先行世代のロックンロール・リヴァイヴァルよりもルーティという特異な現在に立っている。実際、今のイギリスでキャリアの近いバンドの中から彼らと音楽性を共有するような名前を挙げるのは難しいだろう。それこそ、最新作でアメリカン・ソングの伝統への深い洞察に満ちたソングライティングを披露したヴァンパイア・ウィークエンド、あるいは、同じような眼差しでそのルーツにまで遡るロック・ミュージックの多様なフェーズを集成したジャック・ホワイトにさえ、近作の彼らは親近感を抱かせるようだ。そして、ソング・オリエンテッドな佳曲が並んだ前作を挟み、本作ではそうした傾向をさらに深めているといっていい。
“アー・ユー・マイン?”や“アラベラ”で聴けるメタリックなギター・リフやボトムの効いたロック・アンサンブルは今や彼らの十八番といえる。加えて、やはり本作で耳を引くのは、アレックス・ターナーの懐深い歌声と、その流暢なハーモニー/コーラスだろう。エコーが美しい“ニー・ソックス”。ソフト・ロック風のレイドバックしたメロディに映える“No.1パーティ・アンセム”。ヴォーカル・ワークへの傾倒はとみに昨今のポップ・ミュージックにおけるモードのひとつだが、前述のディスコグラフィの流れを踏まえたとき、たとえばそれは彼らと同時代のアメリカのインディが「歌」を復権させた光景も連想させて興味深い。それこそ、当時ダーティ・プロジェクターズのロングストレスやグリズリー・ベアのドロステがR・ケリーやアッシャーへの共感を明かしていたエピソードを併せて思い返せば、本作で多用されたファルセットも聴こえ方が変わってくるのではないか。ターナーが本作についていう「アメリカ的」なるものの一端は、この辺りにもあるのかもしれない。
