

2012年で一番売れた曲、“コール・ミー・メイビー”。セレブにもキッズにも口パク映像させたあの勢いはよく覚えていますが、実はそれに乗っかろうと発売を遅らせまでしたアルバム『キス』のセールスはイマイチだった。まあ、そんな一大プロジェクトになるとは思わず短期間で作られたレコードだったので仕方ありません。そんなわけで、満を持して企画された次作『エモーション』。その間に一枚フォーク・レコードがボツになったとか、あらゆるソングライター/プロデューサーから200曲が集められたとか噂されていますが、その甲斐あってポップ・アルバムとしては超高性能。80sポップをコンセプトに、1stシングル“アイ・リアリー・ライク・ユー”では「女子のセックス観」がシンディ・ローパー並みに元気に歌われ、他の曲でも職人たちが彼女の気さくな魅力を引き出しています。さらにはアルバムを買う層も射程に入れ、ヴァンパイア・ウィークエンドのロスタム、シーア&グレッグ・カースティンらインディな顔ぶれも揃えている。ただ彼らの曲もいいのですが、図抜けているのはデヴ・ハインズによるシンセ・バラッド“オール・ザット”。やっぱデヴ、最高です。(萩原麻理)

ででで電気スゲで、でんでんででっで電気スゲー! 漏電しているようなギター・サウンドにまず圧倒される。レオ・フェンダーがはじめてブロードキャスター(後のテレキャス)をかき鳴らした興奮を追体験出来るかのようだ。そしてドラム・サウンドも非常にパワフルながら、デジタルで加工したような不自然さはない。まさに「エンジニアリング」を感じさせる、2015年のバンド・サウンドにおける理想的なプロダクション。10年前の前作『ザ・ウッズ』には、向井秀徳が自身のスタジオで再生してスピーカーを飛ばしたというエピソードがあるが、本作のミニマル&パワフルなサウンドはそれ以上と言えるだろう。とはいえ、何より本作で魅力的なのは、ギターと(ベースと)ドラムとヴォーカルのアンサンブルが、まだ一切行き詰まっていないということを証明するソングライティングと演奏だと、強調したい。ロックンロール誕生からすでに60年の月日が過ぎた。しかし、一周しようが何周しようが、まだここには新しいバンド・アンサンブルが存在している。それには変拍子もエレクトロニクスも必要なかったらしい。「人間をナメるな。あきらめるな」と容赦なく聴き手をぶん殴る爽快で新鮮な8thアルバムだ。(照沼健太)

白銀に染まるディストピアでの子供たちの蜂起を描いた『ロットバルトバロンの氷河期』は、なんと的確に2015年のこの国を予見していたのだろうか。優れたポップ・アーティストはつねに時代の空気を鋭敏に吸い込み、誰よりも空想的な方法で世界を創り出す。社会へのステイトメントを落とし込むことが当たり前となった国内インディ・シーンにおいても、やはり彼らはトップ・ランナーだろう。今作で光を当てたのは、革命の真ん中で声を上げる者ではなく、漫然と違和感を抱えて過ごす傍観者たちや、燃えゆく都市に時代の終焉を見るビッグ・ブラザー側の権力者。つまり『~氷河期』では書き割りに終わった人々をあらためて主役として描いているのだ。前作と比較して、特にリズム面で幅を増した楽曲が、様々な立場からの視点を反映している。そして、録音地である〈ホテル2タンゴ〉周辺のカナダ人脈が力添えした、サイファイな触感の音作りが、舞台をファンタジックに染め上げる。どうしようもなく動いていく時代のただ中で、ひたすらに生きるしかない名もなき人々を記録したリアル・フィクション。『ATOM』はあなたのいかなる選択も否定しない。(田中亮太)

根っからのポップ・カルチャー好き。メインストリーム音楽への素直な憧れ。むしろファンシー趣味なルック。等々といったそもそものクレア・バウチャーの属性をあらためて踏まえて前作『ヴィジョンズ』を聴き返せば、本作において彼女が何ものに対する気兼ねや一切のエクスキューズなど無用であることは瞭然。飛躍こそあれ転向や宗旨替えの類はあらず。出自である北米アンダーグラウンド・シーンに倣いDIYな流儀を築き上げてきた彼女の音楽は、今回その「見せ方」を変えただけ――ということなのだろう要は。ただ、大胆かつ確信犯的に。そのことは、本作が引き続きセルフ・プロデュースである一方、マスタリング等にはアデルやチャーリーXCXを手がける制作陣が起用されているところにも窺える。彼女はここでも果敢にクロスオーヴァーを試みている。と同時に、いわば本作で彼女は「何をやるか」と「どうやるか」との間にようやく折り合いをつけることができたのかもしれない。そしてこの周到なバブルガム・ポップは勿論、自身を育んでくれたローカルへの微笑み返しも忘れていない。これは正真正銘のブレイクスルー作。だが、彼女のキャリアハイはここよりもっと先にあるはずだ。(天井潤之介)
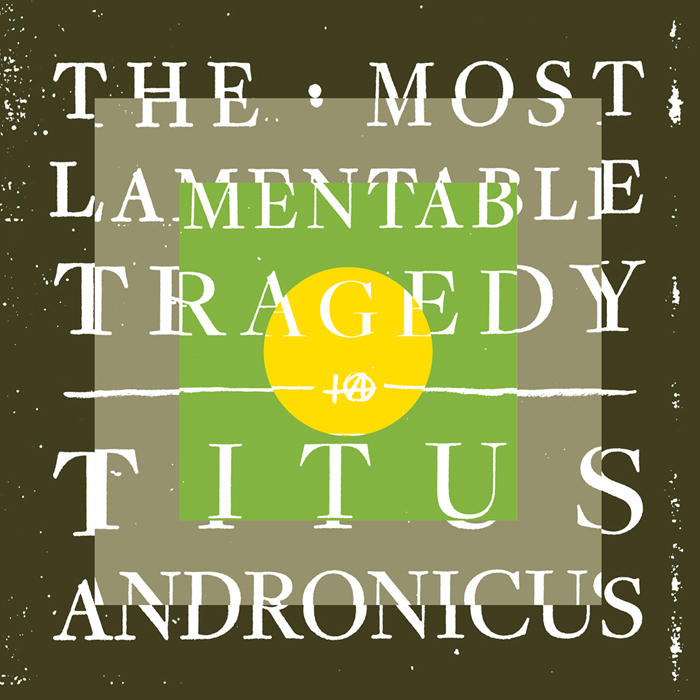
大家シェイクスピアが書いたもっとも残酷で血まみれな、ゆえに比較的知名度の低い古典悲劇をバンド名に掲げる、「おや?」と思わせるひねくれぶりに気概を感じさせるモダン・パンクス。傑作2nd『ザ・モニター』でもパンクらしからぬ「南北戦争をモチーフにしたコンセプト・アルバム」なる野心が光っていたが、4枚目の本作はなんとCD2枚組の大作ロック・オペラに挑んでいる。ザ•フーの『四重人格』、ハスカー•ドゥ『ゼン•アーケード』、近いところでは盟友ファックト•アップの『デイヴィッド・カムス・トゥ・ライフ』と同様、人生の変わる体験を経て主人公がメタモルフォーゼし再生するという映画的なナラティヴをなぞっているものの、リーダー:パトリック・スティックルズ本人の躁鬱病との闘いをベースにした半自伝的なストーリーだけにそのシャウトは遮二無二に熾烈、塩辛いポエジーと歓喜に満ちている。ギター•ロックはもはや若者カルチャーの主役ではないと言われて久しいが、スプロールしながらスコープを次々変える93分の大絵巻にクラシック/ハード/パンク/グランジと70~90年代のロックの諸相を圧縮した本作の確かなエネルギーに触れると、そんな外野の意見なんてどうでもいいことに気づく。(坂本麻里子)

北米インディが牽引したこの10年のサイケデリックな冒険主義への反動か。それとも、2000年代初頭のポスト・パンク・リヴァイヴァルと同根異相のモードに過ぎないのか。ガール・バンド然り。イヴェットやその他諸々。そしてこのカルガリーの4人組。コールドでノイジー。モノクロームでロウ・キー。彼らに著しい傾向をあえて位置づけようとすればどちらとも言えそうだし、「2015年の気分」と諸手を挙げるには既視感を拭えないのも本音。ただどうあれ、2010年代も折り返しを過ぎて潮目の変化を促す兆候が表れ始めていることは確か。とりわけ、前身のウィメン時代をへてディケイドを跨いだこのヴェト・コンの面々はそのあたり十分に自覚的なのでは。ディアハンターの後を追うヴェルヴェット・フォロワーなアート・ロックだった以前の面影はほぼ皆無。まるでディス・ヒートがハード・ミニマルをやっているような“マーチ・オブ・プログレス”は本デビュー・アルバムの白眉だが、そのメタリックな快楽性は一方でニュー・インダストリアルやロウ・ハウス周辺の現行のアンダーグラウンドなエレクトロニック・ミュージックとも潮流を共有する。(天井潤之介)

アデルの最新作に共作者として参加したことでも名を上げた、バンクーバー出身のシンガー・ソングライターによるデビュー作は、パトリック・カーニー(ブラック・キーズ)、JR・ホワイト(元ガールズ)、アリエル・ラヒトシェイドといった気鋭の才人たちによるプロダクションの下で製作された。だが、その誰もが過度の自己主張をせず、むしろ丁寧に紡がれるこの旋律にうっとりと酔いしれるように最小限のバックアップに務めている。それは、ひとえに彼の楽曲が持つタイムレスな魅力ゆえだろう。そう、本作の魅力を味わうためには、何の予備知識も必要ない。ただ、繊細で美しいピアノや歌声と、その中に込められた狂おしい感情に耳を傾ければいい。そうすれば、周囲を取り囲むノイズは一切遮断され、ただ純粋な「僕」と「あなた」の繋がりの愛しさに胸を締め付けられるに違いない。これだけ目まぐるしく情報が飛び交う時代に生きていると、流行りや最新を追い続けるのにふと疲れや徒労感を感じる瞬間が、誰にだってあるだろう。そんな時にも、このレコードはきっと古い友人や家族のように温かくあなたのことを迎えてくれるはずだ。(青山晃大)

2010年代前半にリリースされたシングルや一連のライヴ活動からして、再結成ブラーは古き良き時代を懐かしむ同窓会的なものだと誰もが感じていたに違いない。だからこそ、約13年ぶりに届けられた新作には、まったくもって予想外の、嬉しい驚きがあった。ゴリラズでのヒップホップ/ファンク/エレクトロニック音楽への挑戦、あるいはDRCミュージックでのアフリカ音楽の探求など、デーモン・アルバーンがここ10数年で積み上げてきた音楽的含蓄が、「この4人」によってブラーというフォーミュラの中にしっかりと落とし込まれている。“ゴー・アウト”などでは手数を抑えてヘヴィなファンクネスを抽出することに尽力したリズム隊、そして時にはエフェクトを駆使してノイズをまき散らし、時にはソロでのトラッド・フォーク研究の成果である繊細な演奏を聴かせるグレアムの多彩なギター・ワークも素晴らしい。90年代のブラーを思わせる曲も時折顔を覗かせるが、それは本作の音楽的達成に自信を持っているからこそ出来る、余裕のファン・サービスだろう。過去を引き受け、未来に目を向けた、「2015年のブラー」としてあるべき姿がここにはある。(小林祥晴)

ホワイトハウスがレインボーカラーでライトアップされた2015年において、言い換えれば西洋社会で性の多様性が前向きに称揚される現在において、アメリカから北国に逃れたこのゲイ中年はひとり、食料品店で何を買っていいのかわからずボーッと突っ立っている。『007』の新作をトム・フォード、ベン・ウィショー、そしてサム・スミスという現代のパワー・ゲイが華々しく彩るいっぽうで、このおじさんは元彼への醜い恨みや孤独、HIVポジティヴであることの混乱をバリトン・ヴォイスで朗々と歌い上げるばかりだ。オーケストラル・ポップとしても、あるいは80sニューウェーヴ色が濃厚なシンセ・ポップとしても、アダルトであること……というかもう若くないことが強調されていて、しかし逆説的に開き直りにも似た清々しさもここには漂っている。白眉はシングル“ディサポインティング”。そこでトレイシー・ソーンの声が聞こえれば4、50代のおじさんたちは泣くだろうが、若いリスナーはそんなことを気にしなくてもいい。ただ、ドゥワップ・コーラスと太いシンセ音を引き連れたこの皮肉屋の中年が、ボロボロになりつつそれでも愛を謳いあげる姿を見てほしい。(木津毅)

人種問題を扱ったケンドリック・ラマーとディアンジェロをこの一年の象徴とするなら、そうした黒人音楽史の誇るべきゆたかさを誰よりも鮮やかに示してみせたのは、間違いなくソーシャル・エクスペリメントだった。ゴスペルとジャズの要素をふんだんに盛り込みつつ、そこにハウスやシカゴ・バップのリズムをなめらかに接合。ヒップホップを媒介とさせることで、彼らは過去と現在を一直線につなぎ、ソウル・ミュージックのあらたなスタンダードをここに提示している。なかでもハイライトは、やはりミュージカル仕立てのMVも最高だった“サンデイ・キャンディ”だろう。そう、ここには賑やかなダンスと重層的なハーモニー、そして語るべきストーリーがあるのだ。ちなみに、『サーフ』はあくまでもドニー・トランペットことニコ・セガールが取り仕切った作品なので、チャンス・ザ・ラッパーの活躍に期待しすぎると、すこしだけ物足りなさもあったかもしれない。しかし、まあ、そこは焦らずにいこう。つい最近も、チャンスはソーシャル・エクスペリメントとの共作曲を立て続けにふたつ発表したばかり。お楽しみはまだまだこれからだ。(渡辺裕也)
「2015年 年間ベスト・アルバム 11位~20位」
はこちら
「2015年 年間ベスト・アルバム 50」
はこちら
