

あまりにもそつなくできすぎていて、どうリアクションしたらいいのかよくわからなかった『ソー・マッチ・ファン』(2019年)をリリースした頃からすでに予告されていた、一応は「2ndアルバム」という位置づけになっているこの『パンク』は、天然のトリック・スターらしく挑発的なタイトルでリスナーに期待をさせておいて、それを鮮やかに裏切る。「俺は嘘なんてつかない」(“デイ・ビフォア”)とヤング・サグはラップする。けれども、彼が字義どおりの意味で言葉をあつかうような約束事に従ったためしなんてないし、それこそが逆説的にこのアルバムを彼のピュアな「リアル・ライフ・ストーリー」たらしめている……のかもしれない(その意味で、サガーはリル・ウェイン以上にラップ・ミュージック・シーンで重要なアイコンなのだ)。『パンク』に横溢しているのは、アコースティック・ギターおよびエレクトリック・ギターの響きとドラム・ビートに依らないプロダクションだ(主にチャーリ・ハンサムがプロデュースを担い、4曲でドラムが用いられていない)。それがソフトで、アトモスフェリックで、どこかメランコリックで、ディープで、ヴァルナブルなムードを醸成している。TR-808のキック+ハイハット+スネアのディシプリンに律せられないことで、サガーの伸び縮みするフロウはいつも以上にふにゃふにゃと自由に駆け回る。「俺は神様に言ったんだ/『俺の命を守って。イっちゃいそうだからさ』」(“リヴィン・イット・アップ”)。そう、これが彼の「パンク」なのだ。そんなサグの2021年における仕事として、若い才能の作品をYSLから次々に送り出したことの重要さは強調しておきたい。(天野龍太郎)
listen: Spotify
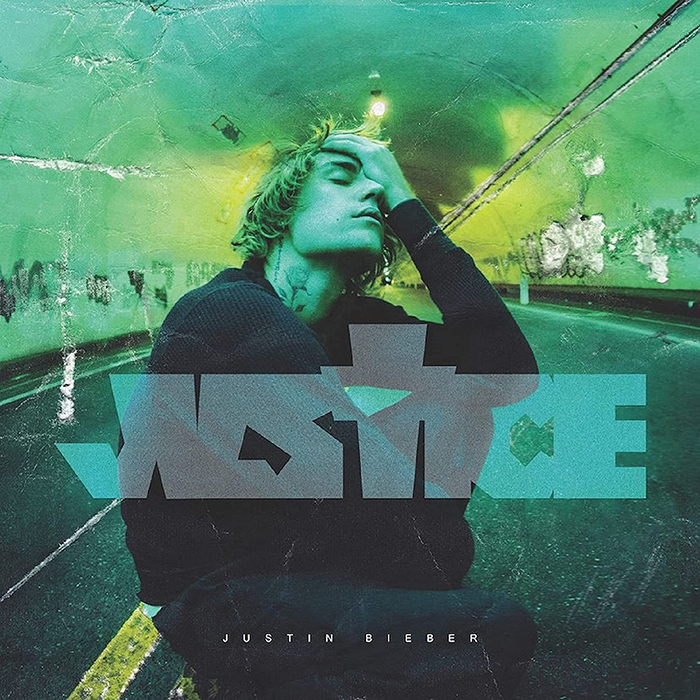
「俺は自由を失うんじゃないよ。かけがえのない不自由を、これから手に入れていくんだ」。前作からわずかなインターバルでリリースされた本作『ジャスティス』を聴いて連想したのが、2021年のアニメ作品『SSSS.DYNAZENON』におけるこのセリフだった。ジャスティン・ビーバーに限らず多くの“プロ”アーティストのキャリアとは、不自由な契約からの解放を目指す道筋でもある。初めは誰もがアマチュアとして表現の自由を持っているが、経済的自由がない。そのため契約によって自由を売り渡し、金を手に入れる。そして資本の力によってセールスと知名度にレバレッジを効かせ、一定のファンベースを獲得したところで表現と契約上の自由を取り戻すように動き、それがさらに富を生むようになる。これがポップ・ミュージシャンの一つの勝ちパターンである。そしてそれは株式会社創業者の勝ち抜けや、会社員のFIRE(経済的自立と早期退職)と仕組み的には大差がない。しかし、多くの成功者が実際には仕事を辞めないように、世界規模のミュージシャンの多くが引退しないのはご存知の通り。そこにはクリエイティヴィティのほか、スターダムの麻薬性、知名度という資産の運用、多くのスタッフの雇用を生み出していることへの責任など、あらゆる理由が絡み合っていることだろう。そうした事情が最も複雑に入り組み、アーティストを数年間に渡って縛り付けるのがワールド・ツアーだが、本作はパンデミックによってそんなツアーが中止され、エアポケットのような期間でイレギュラー的に制作&リリースされたアルバムだった。つまり、ジャスティン・ビーバーにとって、かつてない自由な環境のもと作られたレコードなのは間違いない。だが、興味深いことにここで歌われるのは、ヘイリーとの交際と結婚が生んだ安心とそれでも消えない不安、そして宗教の縛りによって寄りかかれるものを見つけた晴れやかなジャスティンの表情だ。多くの人はそれを”不自由”と呼ぶかもしれない。はじめに引用したセリフは、主人公の少年が現実を生きていくための宣言であり、“かけがえのない不自由”にはヒロインとの交際も含まれている。そう、“行動”と“責任”が問われるこの時代には、無邪気な自由よりも、不自由をいかに愛し慈しむかという心持ち、そしてそれを持続させる仕組みが求められている。もしかしたらジャスティンは世界で最も“不自由”なアーティストかもしれない。だが、それでも自らを突き動かすものに、彼は「正義」と名前をつけた。(照沼健太)
listen: Spotify

J.コールのリリシズムは意味を引き摺り、重く、古風で情念的に聞こえるだろう。彼の音楽もMVも、ネオリベラリズム的な当て擦りを面白い冗談のように笑う、頻繁に私たちのテレビやYouTubeに映る勘違いの連続のイメージとは無縁である。一方 で、サウンドは生楽器のループが偶然ではなく多く使われ、「なぜ嘘は心地良く響き、真実は痛みに満ちているのか?」(“the.climb.back”)といった聞く人によっては既視感のあるラインも少なくない。思い出せば、J.コールの過去の曲には「罪人として生まれたがより良き人間となって死にたい」というラインもあった(“Born Sinner”)。ヒップホップと信仰。良い悪いでも、正しい正しくないでもなく、音楽を音楽のみとして完結させない意思が存在せざるえない、そんな場と歴史に想像を馳せてもいい。第64回グラミー賞“ベスト・ラップ・アルバム”候補。(荏開津広)
listen: Spotify

サウス・ロンドン、ランベス出身のジョイ・エリザベス・アクサー・クルックスは、バングラデシュ・ベンガル人の母とアイルランド人の父の間に生まれた。2016年、17歳の頃にリリースしたデビュー・シングル“ニュー・マンハッタン”やそれに続く“シナトラ”の時点で、彼女はすでに、エイミー・ワインハウスやニーナ・シモン、ビリー・ホリデイへの憧れを滲ませたくすんだブルージーな歌声を携えて、トリップホップやジャズやレゲエやヒップホップをミックスしたきわめて英国的なソウル・ミュージックを志向している。そして、“ドント・レット・ミー・ダウン”(2018年)と“シンス・アイ・レフト・ユー”(2019年)というギターないしピアノの弾き語りの簡素なデモ、および〈ア・カラーズ・ショー〉への出演で、歌そのものの力によって脚光を浴び、2020年のブリット・アワードにおいてライジング・スター・アワードに選ばれた。満を持して上梓された1stアルバム『スキン』でまず注目すべきは、“フィート・ドント・フェイル・ミー・ナウ”や“トラブル”、“ウェン・ユー・アー・マイン”といったシングルである。エイミー・ワインハウスとマーク・ロンソンのコンビを思い出させるジョイ・クルックスとプロデューサー、ブルー・メイとのタッグは、レトロなリズム&ブルーズのスタイルを確信的に採用する一方で、マルチ・レイシャルであるクルックスの感覚を活かし、南アジア/東アジア的な旋律や意匠も用いる。それだけではなく、エレガントなストリングスとエレクトロニック・ダンス・ミュージックのエレメント、さらにレゲエからの影響をそこここに散りばめ、クルックスならではのR&Bが編み上げられている。「音楽は壁や国境や境界線を壊す」と、彼女はありふれた、けれども説得力のある言葉を口にする。クルックスはまさにそれをこのLPで、自身のストーリーを語ることで体現している。(天野龍太郎)
listen: Spotify

ムスタファを初めて聴いたとき、アラン・シリトーの小説を想起した。シリトーの小説の主人公たちは60年前のイギリスの労働者階級だけれども。トロント、リージェント・パークのプロジェクトに住むスーダン系ムスリムで詩人、と但し書きの多さに圧倒されたが、彼が語るストーリーはいたってシンプルだ。暴力が蔓延る団地で、仲間たちにとにかく外出してくれるな、生き抜いて欲しいと懇願するムスタファ。その願いも虚しく、曲になっているアリは2017年に、ラップ・クルー、ハラル・ギャングに一緒に所属していたスモーク・ドゥグは翌年に亡くなっている。スモーク・ドゥグはタイトルの由来であり、アートワークの右側にも映っている。曲に魅せられてクレジットをチェック、フランク・デュークスが全曲をプロデュースし、ジェイムス・ブレイク、ジェイミー・XX、サンファがレコーディングに参加……って一体どんな新人? と驚いた。そのカラクリは、詩人として12歳から注目を浴びた縁で、デュークスに引き立てられてザ・ウィークエンドやカミラ・カベーロに詞を提供して来たから。ポエットしての才能をジョニ・ミッチェルらにインスパイアされたというフォークに乗せたのが、本作の奇跡だ。描写力と低くて弾力のある美声が、ずば抜けている。また、南スーダンのディンカ族の音楽をサンプリングし、出自を伝えつつ音楽に広がりを持たせたのも賢い。地元の実話を語りながら、その祈りの深さ、片隅に追いやられた若者の普遍的な怒りが、本作を時代を選ばない名作たらしめている。ムスタファの存在は、2021年の数少ない吉報だった。余談だが、ディンカ族は世界一平均身長が高い人たちだそうで、ヴィデオでやたら細長く見える理由が判明した。(池城美菜子)
listen: Spotify

90年代以降のロック・ミュージック、つまりオルタナ、エモ、インディなどと名指されることとなったロックが内省的な性質を持ったのは、時代が暗くなったからでも、ラップがかつてのロックの役割を奪ったからでもない。音楽がスピーカーではなく、ヘッドフォンで聞かれるようになったからだ。他の誰とも共有しない聴取体験が当たり前のものとなり、内省的な子供達は耳元で鳴る轟音にのめり込んでいく。かつて日本のあるロックバンドは自らのアルバムをこう名付けた。ヘッドフォン・チルドレン。ニルヴァーナもレディオヘッドもミネラルもパラモアもバンプ・オブ・チキンも、全てヘッドフォンの子供たちのための音楽だった。 フィービー・ブリジャーズやジュリアン・ベイカーといったクィアな女性音楽家たちがインディやエモを受け継いでるのは、今がAirPodsの時代だからだ。それは外界をより強く遮断し、耳と再生機器の間を密閉する。きつく締まった状態で鳴らされる音楽は、内省的であると同時にエロティックだ。スネイル・メイル三年ぶりのアルバムも、緊密なエロスを持つ。現れるのは性と感情が縺れあった、強迫的な愛。「なぜ私を消そうとするの?(“ヴァレンタイン”)」という言葉が、荒いギターとつんのめるドラム、そして7度カーネルの鋭いメロディを伴って鳴らされる切実さ。報われない性愛を叫び続ける獣を表現するために、スネイル・メイルはエモとインディの形式を要請する。エモとインディはしばしば、白人男性の女性嫌悪(あるいは女性恐怖)と結びつく表現として批判されてきた。しかし、ミソジニーがエモの一時的特徴に過ぎなかったことを、スネイル・メイルのような音楽家は証明する。それは、同じくミソジニーと結びつけられてきたオタク文化を、女性達が自らのものとして表現するのと軌を一にしている。「ユリイカ2020年9月号 特集=女オタクの現在」で、寄稿者の多く(例えば王谷晶、岡田育、佐倉智美)が「女オタク」という言葉自体に違和感を表明していたのを、僕はこのアルバムを聴きながら思い出す。インディもエモもオタクも、そもそも性的性質の固定ではなく、性の揺るがしと問い直しを内包する文化だからだ。 今AirPodsから聞こえるロック音楽は、儀礼的なパーティのためでなく、度しがたい欲望を解きほぐすために鳴らされる。緊密で孤独な、痛々しく愛おしいエロティシズム。(伏見瞬)
listen: Spotify
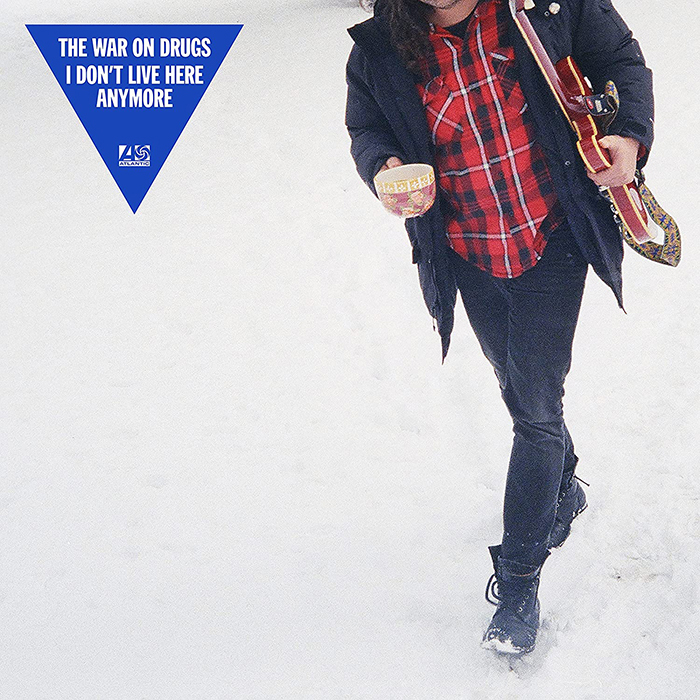
「今、ロック・バンドの存在意義とは?」。一部の例外を除いて、インディがカッティング・エッジな音楽表現の役割を降り、あるいはアンダーグラウンドへと向かい、ジャンルレス/立場レス/国境レスなコライトを取り入れることに成功したラップとR&Bが隆盛を迎えたこの10年間、世界中のあらゆるバンドがこの問いに晒され続けてきたのはご存知の通り。彼らロック・バンドは、それに対するアンサーとして機能する折衷的なバンド・サウンドを模索するか、無視するか、あるいはそんな疑問があることにすら気づかないかという大きく3つの方向性を取らざるを得なかった。要はロック以外の要素を取り入れるか、ロック的なものから遠ざかるか、あえてロック的であるかの3択だ。アイスエイジのように、それらすべてを放棄しながら同時にすべてに応えるような例外的なバンドもいたにはいたが、全体的にセールスとプロップスを両立させたのは、ロックを一つの絵の具としてパレットに乗せたバンドたちだった。そして、その現象はラッパーやポップ・シンガーがロック/ポップ・パンクを取り入れたり、そのまんまな“ロック・アルバム”を作ったりする流れと無縁ではない。つまりロックはもはや目的ではなく、手段の一つとなったわけだ。いや、2021年公開のドキュメンタリー映画『ザ・ビートルズ:Get Back』において、ビートルズの面々が50年代のロックンロールの引用と再解釈を試行しながら未完のアルバム『ゲット・バック』に取り組んでいたことが改めて提示されたように、そもそもポップ・ミュージックの世界でロックとは一つの絵の具だった(そもそも60年代前半のビートルズこそが最初のロックンロール・リヴァイヴァリストたった)。数々の物語によって、あたかもそれがポップ・ミュージック界の中心として永続してきたかのように錯覚しているだけなのだ。本作を通し、ウォー・オン・ドラッグスの中心人物アダム・グランデュシエルは、繰り返し忘却と前後不覚な幻について歌い続ける。何が正しいのか、どこにたどり着くのかは分からない。たしかなのは身体に染み付いたブルース・スプリングスティーンの音楽と、ボブ・ディラン“デゾレーション・ロウ”で踊った記憶だけ。ギターに限らずあらゆるパートを、定番的ギター・アンプJC-120で鳴らし直し、コンピューター上でベッドルーム・レコーディング的に制作したという表題曲が本作中で最もビッグでロックなサウンドに仕上がっているのは、コロンブスの卵か、批評か。いずれにせよ、ロック・バンドにとってこんなにも自由に音楽を作れる時代はこれまでなかったはずだ。(照沼健太)
listen: Spotify

3人ともラップの説得力が増している。言葉の輪郭とイメージが鋭く、時に発話を歪ませるフロウの快感も強い。例えば、荘子itは「近代人ほどいう物の哀れ/有り難がるのはもっと憐れ」というキラーを明確に発した後で、「繁栄を謳歌/安心安全を評価/今や右下降下」を「オーカゥ」「ヒョーカゥ」「コーカゥ」と崩して響かせる。没も「it's just 電光掲示/ミュートかましたジョン・ケージ」というリズム的にも文脈的にも小気味よいライミングをかました直後に、「バウババヷバード」「ウァウァウァワァード」と吃音的な躓きを加える。特に切れ味鋭いのはTaitanで、“OCCUPIED!”の「Hi,Alexa!」からスタートするライムは、粘り気とスタッカートを的確に使い分けており、邪悪さ全開の名芝居。前作までのカオスは少し分かりやすすぎたが、今作には簡単に紐解けない強度が出始めた。 Dos Monosは実際には不器用なグループで、ミニマリズムを目指しても、プログレ的なゴツゴツした文脈過剰に行き着いてしまう。彼らが強いのは、不器用さを貫く無鉄砲を持ち合わせているからだ。スタイリッシュとほど遠い暑苦しさの徹底が、Dos Monosだけのスタイルになっている。(伏見瞬)
listen: Spotify

アーマンド・ハマーは、各々ソロで活動しているビリー・ウッズとエルシドの二人のニューヨークのラッパーによるプロジェクト。通算5作目となる本作に着手したのは、実は前作『シュライン』以前だったという。プロデュースは全曲アルケミストが担当、『シュライン』がリリースされた2020年には、1990年代末には頭角を現していた彼の仕事が質量ともに、彼のキャリアのみならずシーン全体から見ても最高レヴェルに達していたことは、前回のこの年間ベストでも触れた通り。サンプルのセンス云々以上に、既存の楽曲からピンポイントで抜き出してきた(楽器の)音の組み合わせ方でも冒険している。リリックの言葉の組み合わせも唯一無二で、ビリー・ウッズは“ウィッシング・バッド”の途中の5ラインほどの中で、『千のプラトー』→監獄→『収容所群島』→アルゴリズム→フーコーと固有名詞を折り込み、(恐らくは)パノプティコンについて聴く者の意識を喚起している。また、 “チチャロンズ”(ブタの皮を使ったスナック菓子)では 「頭のなかで警官(pig)を殺してみろ」「自分はここで働いてるだけで、上の者ではないので」といったフレーズを通じて、社会における権力構造への注目を促し、アルバム・カヴァーで血に汚れたブタ(pig)の頭を二つ並べてはいても、コップ・キラー的なものとは全く別次元から問題を提起し、行動へと導こうとしているようなので、クリティカル・セオリー(批判理論)的なラップとも言えそうだ。さらに、1930~60年代にかけて、ニューヨークの都市計画に大きな影響力を与え続けた毀誉褒貶に激しい人物をタイトルにした“ロバート・モーゼス”などもあり、既存のいわゆるポリティカル・ラップあるいはコンシャス・ラップと比較したくもなるが、アーマンド・ハマーのラップ表現は土台から違い、本作でその個性が一層研ぎ澄まされた。(小林雅明)
listen: Spotify
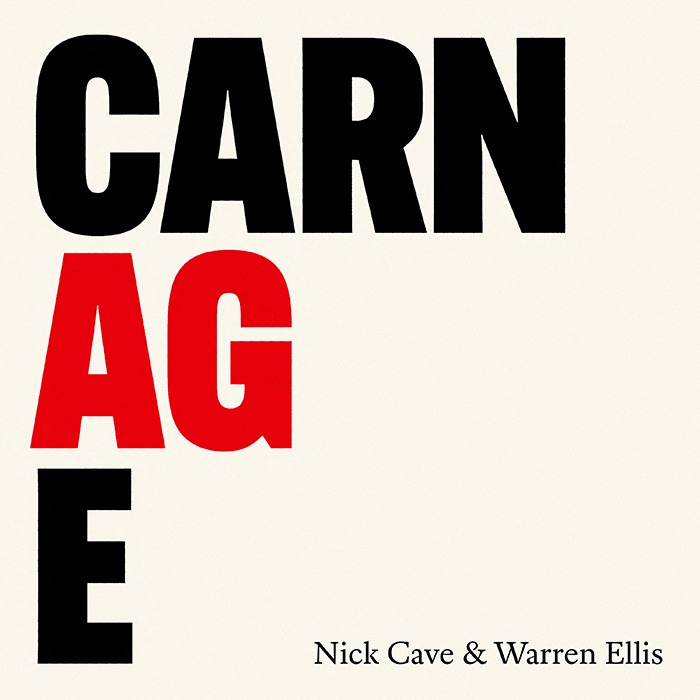
空の上にいる「あなた」のことを、近年のニック・ケイヴは強く思ってきた。ますます宗教音楽に接近したザ・バッド・シーズとの『ゴースティーン』の続きとして、ともに映画音楽を手がけてきたウォーレン・エリスとの初のオリジナル・アルバムである本作を、そして、ケイヴは“ハンド・オブ・ゴッド(神の手)”のイメージから始める。「神の手/空からやって来る」。荘厳なストリングスと不穏なビート、抽象的なシンセサイザーを覆うように降り注ぐ聖歌隊のコーラス。それらは超然と鳴らされ、ケイヴは何度も「空にある王国」を見上げる。『カーネイジ』は2020年以降に世界で起きたことに強く影響されて生まれた作品であり、平穏な空と対比されるように描写される地上では、デモ隊が銅像を倒そうとして、軍隊を掌握する権力者が彼らを撃ち殺そうとしている(“ホワイト・エレファント”)。その混乱をすべて消し去ろうとばかりに轟くゴスペル・コーラス……これはこの世を諦めた者の音楽なのか? それでも彼は、地上にこそ「あなた」を見出そうとする。後半の穏やかなバラッドたち――そこでケイヴは、「彼女の狂気と自分の狂気がともにあるとき、ある種の正気が形成される」ことを知る。「愛だけがある、少しの雨とともに/そして僕は、きみにまた会えることを願うよ」(“カーネイジ”)。天上の楽園ではなく、この混沌にまみれた世界をどうにか生き長らえるための愛を巡るポエトリー集。(木津毅)
listen: Spotify
▼
▼
2021年 年間ベスト・アルバム
21位~30位
2021年 年間ベスト・アルバム
41位~50位
2021年 年間ベスト・アルバム
扉ページ
