

チャンス・ザ・ラッパーの「ミックステープ」にヤング・サグと並んでゲスト参加し、ドラムにフィーチャーされた“ブロッコリー”では全米5位の栄光を手中に収めるなど、今年もっとも話題を振りまいた新鋭ラッパーの一人が若干19歳のリル・ヨッティである。ヨットやボートにちなんだ名前を名乗り、仲間をセイリング・チームと呼ぶ、船と海のイメージに憑りつかれた彼は、本作の冒頭で、『ファインディング・ニモ』のドリーが鼻歌交じりに繰り返す「ただ泳ぎ続けよう」という言葉を引用する。このとにかく楽観的でポジティヴな姿勢こそが、彼の新世代たる所以に他ならない。トラップ・ビートとオートチューン・ヘヴィなラップの組み合わせは、ヤング・サグやフューチャーから受け継いだアトランタの伝統を汲むものだが、リル・ヨッティの音楽は彼らと比べても遥かにメロディアスで快感原則に忠実。案の定、彼の一挙手一投足はピュリストや真摯な音楽愛好家たちから猛烈なバックラッシュを食らっているが、この男はそんな年寄りの戯言なんて気にしちゃいない。彼は自ら称するところの、「キング・オブ・ティーンズ」であり「キング・オブ・ユース」なのだから。(青山晃大)

「昔はよくグッチ着てたけど、あれ全部捨てた、なぜなら、あんなの俺じゃないから」と、収録曲“ザッツ・ノット・ミー”でライムしてたのが2014年だったから、スケプタが本作でアルバム・デビューを果たすまで2年以上が過ぎた。自身のレーベルからのリリースであることに加え、「そんなの俺じゃないから」という自分自身に忠実であろうとする信念は、全体の8割方を手がけたビートにも表れていて、例えば、“イット・エイント・セイフ”(これまた2年前の曲)からは、スリー・6・マフィアによる米メンフィス産の90年代中期のサウンドが聴こえてきてしまうし、さらに、ファレルとのコラボ“ナンバーズ”等と併せて、正直、こういうのもグライムなの? という単純な疑問が湧き、今も、わだかまりのように残っている。そのあたりを、むしろ、スケプタらしさが表れた本作の強みと考えるべきなのか? このアルバムが、アクセスしやすいグライム作品となり、本国英国では商業的にも成功した一方、ここ数年、毎年、来年は来る! と言われてきた米国では、発声の面では対極にあるマンブル(もごもご何言ってんだかわからない)ラップ全盛の今年、グライムはブレイクしなかった。(小林雅明)
>

仮に三作目にあたる本作が、自分対自分あるいは自分という存在(に対する疑問)にこだわった2013年の前作アルバム『ビコーズ・ザ・インターネット』、そして、2014年のミックステープ『STN MTN / カウアイ』の延長線上にあるものだったとしても、『ブロンド』(フランク・オーシャン)に対する評価の高い2016年には、広く訴求出来る作品になっていたはずだ。なのに、そうならなかったのは、やはり、彼自身が父親になったことが大きかったのだろうか(例えば、チャンス・ザ・ラッパーの『カラリング・ブック』と同じように)。チャイルディッシュ・ガンビーノの目線は、ダイレクトに自分の子供へ(何しろ“ミー・アンド・ユア・ママ”である)、さらにそこから自分対自分たちを取り巻く社会をより強く意識するようになり、その過程で滲みだしてきた、生(生き方)そのものでもある音楽=ファンクに身を委ね(ラップすることなく)、こういう時代だからこそ、素直に心の声を声に出してみたのだろう。(小林雅明)

今年もその多作家っぷりを見せつけたヤング・サグが『アイム・アップ』、そして“ウィズ・ゼム”がヒットした『スライム・シーズン 3』という二枚のミックステープを発表した後に放ったのが、この『ジェフェリー』だ。本作のリリースがアナウンスされた際、何よりも目を引いたのはその艶やかなジャケットだ。イタリア人デザイナーによるドレス(もともとユニセックスな視点から作られたドレスだ)を身にまとったヤング・サグ、いや、本名のジェフェリー青年は、何よりも自己に対して正直な心で本作を創り上げたことを主張しているかのようだ。元来、ホモフォビア思考が強かったヒップホップ・シーンにおいて、彼の行動は非常に革命的であったことも記しておきたい。ちなみに各曲のタイトルは、ワイクリフ・ジョンから射殺されたゴリラのハランベまで、彼のアイドルの名前をそのまま冠したもの。もともと精力的な活動を続けていた彼だが、今年はカニエ・ウエストやチャンス・ザ・ラッパー、ドラムら、良質な客演作品も目立った。来年以降、ジェンダーや音楽ジャンルまでをも超越した存在になるのかどうか、楽しみなところである。(渡辺志保)

制作のためコソボやアフガニスタンを旅したハーヴェイとは、ルポルタージュする主体であると同時に、異邦人として好奇の視線を集める客体でもあったのではないか。本作の曲作りがロンドンの街中に置かれたガラス張りのスタジオで行われたという逸話は、そうした反転する視座を彼女が意識していたことを窺わせて興味深い。2000年代以降の彼女の創作活動とは端的に言って、ハードコアな自己表現として差し出されてきた「私」を外の世界と紐付けるための試行錯誤、であった。英国人女性としての自我に促された前々作、第一次大戦下の母国に世界情勢を重ねた前作はその重要なプロセスだったわけだが、そうした意味では本作はその集大成、あるいは三部作の最後を飾る作品と言っていいかもしれない。そして、彼女の中で本作の意義が差し迫ったところにあったことは、かつてアメリカで人種や階級の分断を招いた都市政策から引用されたそのタイトルが物語るとおりだろう。そんな彼女の歌を、19世紀のチェンバー・ロックとでも言った仰々しく無骨な演奏に乗せたこの音楽は、この百花繚乱のポップ音楽全盛の年において、その強烈な異物感によって記憶に刻まれるモニュメントとなるに違いない。(天井潤之介)

ロックの宇宙人ボウイ最後の置き土産となった――と同時に、悲しみと混乱に満ちあふれた2016年をも象徴する一作。キャリア後期、とりわけ21世紀前後からのボウイは、自身のもっとも脂の乗り切っていた頃のソングライティングに立ち返ることで蘇生し、新たなる黄金期を迎え、体調不良を経ての10年振りの復活作だった前作『ザ・ネクスト・デイ』でも、その感覚にはブレがなかった。だが、長年、ロック界きってのイノヴェーターだったボウイにとって、それは必ずしも本意ではなかったのだろう。そんな彼が、癌宣告を受け、死を覚悟した状況において、最期の最期で再び革新者に戻れた。しかもそのタイミングで、彼自身の音楽の原体験であるジャズが、ロック史上屈指の未来の才能に対する発掘力を持った彼のアンテナに引っかかって来たのは本人にとっても幸せだったのではないか。勿論、気持ち的にはまだやりたいことはあっただろうし、僕らだってもっと彼の音楽は聴きたかった。だが、その「星」への帰り方はあまりに美しく、かつ、彼ほどの不世出の才能にふさわしいものだったと誰もが認めるものとなった。(沢田太陽)
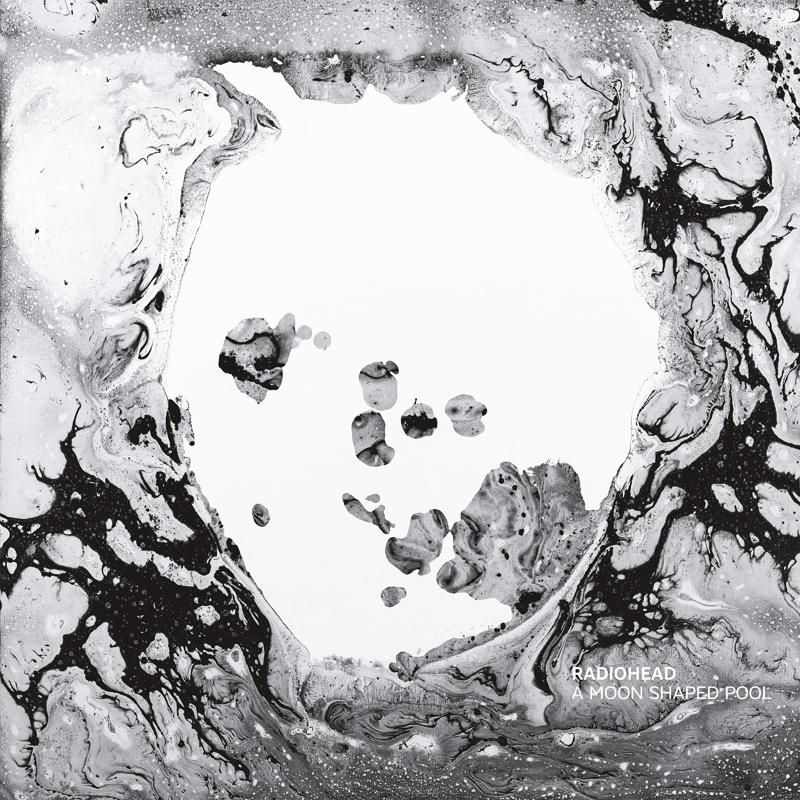
長らくこのバンドの最高傑作の一つとして挙げられていた“ピラミッド・ソング”を更新する名曲“デイドリーミング”の存在を筆頭に、近~現代音楽の要素が目立つ本作を聴けば、『アムニージアック』における重要なポイントは、『キッドA』でも試みられていた「ロック・バンドのイディオムで作られたエレクトロニック・ミュージック」ではなく、むしろ近~現代音楽の要素の導入だったのではないかと考えさせられる。十二音技法やトーン・クラスター、ミニマル・ミュージックといった現代音楽的なサウンドがありつつ、ポスト・クラシカル的なピアノ表現も盛り込み、最新のエレクトロニック・ミュージックと矛盾無く溶け合う磨き抜かれたバンド・サウンドで構成された本作は、『アムニージアック』の極めて真っ当なアップデートということも可能だからだ。そしてなにより素晴らしいのは、それらのサウンドが圧倒的なオリジナリティを獲得していながらも、どこか慎ましやかですらあることだ。一切のハッタリや誇張の無い高度な洗練に漲るのは「これこそが音楽である」という彼らのプライドに他ならない。本作がレディオヘッドの最高傑作であると宣言することに、些かの躊躇いもない。(八木晧平)

尊厳を守るために声を上げたマイノリティと、その状況に切迫した危機を感じたサイレント・マジョリティの対立が世界中を引き裂いた2016年。問題の多様化の果てに、もはや解決の糸口さえ見いだせないほど複雑にこんがらがった現代社会を、根っからのアウトサイダー気質を持つブラッド・オレンジことデヴ・ハインズは、途方に暮れたような黄昏のフィーリングをまといながら漂い続ける。ブラック・ライヴス・マター、フェミニズム、LGBTといった社会運動から、出自の異なる2人の男女が出会い恋に落ちる、自らの両親を題材にしたラヴ・ストーリーまで。淡く繊細に色付けされたファンク・サウンドに乗って、その思索は意識の流れのままに深く広く展開していく。このレコードは、多岐に渡るマイノリティのムーヴメントに感化されつつも、どのコミュニティにも明確な帰属意識を持てずに、漠然とした疎外感と生きづらさを感じている全ての個人に向けて、「君も僕も決して1人じゃない」と、どこまでも優しく手を差し伸べている。(青山晃大)

音楽的に豊かな才能を持ちつつも、一時はホームレスにまで身をやつしたほどの苦労人が、齢30にしてようやく手にしたサクセス・ストーリー。この『マリブ』には、その砂を噛むような人生がついに満開の花を咲かせた瞬間の喜びが目いっぱいに詰まっている。昨年ドクター・ドレの『コンプトン』にフックアップされ、続く本作でプロップスを確立したアンダーソン・パック。隆盛の続くヒップホップ/R&Bシーンの中でも、彼は間違いなく今年最も飛躍した新顔の一人。ただ、誤解を恐れずに言えば、彼の音楽には決して目新しい何かがあるわけではない。ここで歌われる崩壊した家庭というバックグラウンドは今のアメリカにはありふれた光景だし、LA流のネオ・ソウル、ファンク、ヒップホップを下敷きにした演奏も、刺激的というよりも非常にオーセンティック。むしろ、彼の最大の魅力はそのオーセンティシティにこそあると言っていい。ケンドリック・ラマー『トゥ・ピンプ・ア・バタフライ』を筆頭に、社会的な要因に突き動かされた一連の黒人音楽の傑作群と音楽的には共振を見せつつも、より普遍的で耐久性の高い美へと純化されたソウル/R&Bの形がここにはある。(青山晃大)

ホープレスネス。2016年の気分をこれほど的確に表した言葉は他にない。そして、あなたも本当は気がついているはずだ。我々の暮らす地球が、もはや瀕死の状態だってことに。男たちが支配してきた資本主義社会は、いよいよ限界だってことに。そして、壊れゆくその社会の行く末に、他ならぬあなた自身も加担してしまっていることに。ドローンによる空爆。全体主義の蔓延。進みゆく地球温暖化。すべてがその当事者の声として綴られていく一連のリリックをどう受け取るのかは、勿論あなた次第だ。しかし、同時にその苛烈なリリックは、怒りが滲んだアノーニの歌声をより美しく響かせるだろう。ハドソン・モホークとワンオートリックス・ポイント・ネヴァーの手による力強いエレクトロニック・サウンドは、ひたすらにあなたを鼓舞するだろう。そして、あなたはまたこのレコードを再生し、そのたびにこんな言葉と向き合うことになるのだ。「どこにも希望などない/なぜ私はウィルスになってしまったのだろう?」。アノーニはここで、いま地球上にいるすべての人々にむけて歌っている。それでも、あなたにはまだやるべきことがある、と。(渡辺裕也)
2016年 年間ベスト・アルバム
6位~10位
2016年 年間ベスト・アルバム
扉ページ
